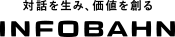「Plug-In思考」でマーケティングの理論と実務を融合させる!【「MARKETING・X-22 KYOTO-」セッション】

合同会社EQUITASが主催するカンファレンス「MARKETING・X-22 KYOTO-」が、2022年11月16日に開催されました。(参考URL:https://marketingx.jp/kyoto/)
その中から、インフォバーン取締役副社長である井登友一がモデレーターを務め、スケダチ代表で社会構想大学院大学特任教授・高広伯彦氏、木村石鹸工業社長・木村祥一郎氏が登壇されたセッション「マーケティングの思考と実践を多様化させるために、理論やメソッドをPlug-In として扱うということ」の模様をお伝えします。
※読みやすさを考慮し、発言の内容を編集しております。
********************
インフォバーンには、企業のマーケティング支援事業を担うIBX[INFOBAHN EXPERIENCE]部門、デザイン支援事業を担うIDL [INFOBAHN DESIGN LAB.]部門の二つの事業部門があり、井登友一はデザイン事業を立ち上げ、現在もデザインストラテジストとして様々なデザイン・プロジェクトを担当・推進しています。
ふだんはデザインやマーケティングの実務家でありつつ、一方で研究者としての顔も持つ井登が、「マーケティングの実践と理論をつなぐ」ことをテーマにした当該セッションの司会進行を担当いたしました。
マーケティング実務にも、理論の「Plug-In」を!
井登友一(以下、井登):このセッションは、「マーケティングの思考と実践を多様化させるために、理論やメソッドをPlug-In として扱うということ」というタイトルです。まるでフランス映画のようなタイトルですね(笑)。
もともとこのセッションは、私がモデレーターを拝命して「誰とやりたいですか?」と尋ねられた際に、すぐに高広さんと木村さんが思い浮かんで、「この三人で話すなら何が良いかな」と考えて出たテーマなんです。
私はふだん、デザインを主領域にしつつ、マーケティングの領域にも関わっています。デザインやマーケティングの世界というのは、ビジネス的な実務の領域と、研究者や学者が研究している理論やメソッドの領域が、付かず離れず関連し合っている世界です。
ただ、なかなかそこに難しさもあって、融合しきれているわけでもない。本当はもっと融合できると相乗効果が図れるのにな、と日々感じていて、以前からお二人とはお話ししていました。
そのなかで、特にマーケティングの領域は、実務の世界で良い成功事例がたくさんあるので、経験値だけで語られがちなところを理論でも説明していくと、多くの方が実践できるようになるんじゃないかと考えています。今回は、その視点から始まったセッションになります。まずはお二方から、自己紹介をお願いします。
高広伯彦氏(以下、高広):高広です。ふだんはコンサルティングのような仕事をしながら、社会人大学院でマーケティングやサービスデザインについて教えています。
木村祥一郎氏(以下、木村):木村石鹸工業株式会社の木村です。木村石鹸は来年に創業99年を迎える会社で、私は4代目の社長になります。今日はどちらかというと、学びの場に来たつもりで、とても楽しみにしております。
井登:司会を務める私は、株式会社インフォバーンの井登と申します。いまは大学院生でもございまして、目下、博士論文の〆切が迫って追い込まれております(笑)。実は、この三人には共通点がありまして……。
高広:みんな、同志社大学の卒業生なんですよ。今日はみなさん、良い話が聞けると思っているでしょう。僕らは同窓会のつもりで来ています(笑)。
井登:京都開催ですし、同志社大学の看板を背負えるように頑張りたいと思います(笑)。
それでは、製品開発においても、マーケティングにおいても、数年前に社長として事業承継されてからさまざまな面白い取り組みをされている木村石鹸さんの事例を拝借しながら、その成功事例をどういう理論に当てはめるとうまく説明がついて、他にも転用できるのかを探る、という立て付けで進めていきます。
このセッションのキーワードにもなっている、「Plug-In」という考え方。この提唱者は高広さんなんですが、まずはこの「Plug-In」の意味を教えてください。
高広:ご参加されたみなさんは、おそらくWebやデジタル関係の仕事をされている方が多いと思いますが、Webブラウザを使うときに、「アドオン」や「エクステンション(拡張機能)」を使いますよね。それとほぼ同義の言葉です。あるいは、アプリケーションに機能を足す際にも、「Plug-In」を使いますよね。本体に対してプラスαで「Plug-In」を付けることで、より機能が拡張されます。
実務家が理論やフレームワークを学ぶと、「それは実務でどう使うの?」という話がよく出るんですよ。でも、「実務にどう使うのか?」ではなくて、理論やフレームワークを「Plug-In」のように頭の中に差し込むことで、「今まで見ていたものと違う見え方がするぞ!」ということが起こるんです。それが次のビジネスの展開にもつながると思うんです。
もともと「Plug-In」というのは、コンセントにつなぐことから、ブラウザに組み込む意味に転用された言葉ですけど、それを思考法的なものに使えばいいじゃないかと。
マーケティングや経営学の成果は、基本的になんらかの企業の経営活動、経済活動、経営現象に基づいているじゃないですか。それなのに、意外と実務家からすると理論や研究成果は遠い存在だと思われている。
でも、理論を知ることで、「なるほど、そういう見方ができるのか!」「この考えは、うちでも使えるかも?」と考えられるようになります。
私は長いこと、セミナーやセッションに登壇してきましたが、昔はよく「画面に映し出されたスライドを共有してもらえませんか?」「具体的なケースはないですか?」と言われてきたんですよ。具体的なケースがわかると、より具体的にイメージしやすいからなんですけど、実際のところは、ケースをそのまま実務に落とし込んだとしても、直接的にその会社の事業で活かせる可能性は低いんです。
他社で成功したユニークなケースや施策をそのままにしておいては、自社では使えないわけですね。でも、そこから抽象化・一般化して、重要なポイントを抽出できれば、自分の会社でも使えるようになるんです。
私が勤めている社会人大学院では、学生は研究成果報告書を出さないといけないんですが、社会人大学院生が論文を書こうとすると、自分のことをずーっと書いてしまう傾向があります。だから私は学生に、「それはハッキリ言って、自分の経験を書いているだけの“エッセイ”にすぎないんだよ」と教えています。
自分自身の経験がスタート地点にあってもいいんだけど、その経験の中から、あるいは調べた事例から、マーケティングの方法論や理論とぶつけて一般化するプロセスがあって初めて、他の人や企業が使えるようになる。実務家でもある大学院生に求められるのは、他の人・企業でも使える「知に転換する」ことなんです。
そう考えると、たとえ大学院には行かなくても、多くの実務家にとって理論を知っていること――なんらかの理論を「Plug-In」として頭の中にさすこと――によって、見え方が変わるんじゃないかと考えまして、それを「Plug-In思考」と名付けてみました。
井登:ありがとうございます。いま初めて、「Plug-In思考」という言葉が世の中に生まれました。これからはこの言葉に、「高広, 2022」とクレジットがついて回りますね(笑)。
学術研究って、時間をかけてデータを集めて、理論をこねくり回して、先行研究を紐解いて、そうしたことをやりつくしたうえで、「一般的に言える」という理論が確立されます。
実際にマーケティングの世界には、非常に多くの理論やメソッドがあるんですけど、それをうまく引っ張り出してきて、いつでも使えるようにしていくのは、なかなか簡単なことではないんですよね。でも、頑張れば誰にでもできるとも思います。そこを今日はディスカッションしていきたいと思います。
高広:学術の知見と、実務の知見は、本当はぐるぐる回るように循環しているんですよね。学生にも、よくそのことを伝えています。
「選択肢がない」ことを逆手に取った「透明容器の洗剤」の成功
井登:そういうわけで、今日はさまざまな施策を実践されている企業であります、木村石鹸さんのユニークな事例をお借りしながら、「Plug-Inショー」をしていきます。
それではまず、自社ブランドにあたる「SOMALI」という製品のお話をしていただきたいと思います。
木村:では、まずはこれを“エッセイ”として(笑)。
いまは私たちは自社ブランド事業もやっていますが、もともとはOEM(※Original Equipment Manufacturing/他社製品を製造すること)がほとんどだったんです。でも、それだけでは厳しいということで、自社ブランドをやっていこうと話していました。
その第一弾としてつくったのが、「SOMALI」というブランドです。いまはハンドソープやボディソープのようなラインナップも展開していますが、もともとは「洗剤」です。トイレやお風呂を洗う、衣類を洗う、台所で食器を洗うような「洗剤類」として立ち上げた商品なんです。
ドラッグストアやホームセンターのような量販店で販売してくのは難しいと考えて、狙っていた販路としては、雑貨店やインテリアショップ、具体的な例でいうと、中川政七商店さんとか、ACTUSさん、D&DEPARTMENTさん。そうしたお店に置いていただいて、売れる商品をつくろうと考えていました。
そこで当時、ブログとかInstagramを見ると、水周りの商品の写真を上げている方がたくさんいたんですよ。おしゃれなキッチンやお風呂場の写真と一緒に、ですね。ところが、そうした写真では、だいたい海外の洗剤が置かれていたりとか、無印の容器に入れられていたりとかして、市販の一般的な洗剤が置かれているシーンがなかったんです。
それを見て、「売られているものをそのまま置きたくない人は多いんだな」と感じたんです。そこから、買ってそのまま水回りにおいても、空間を損ねない、インテリアにフィットする製品、というコンセプトで、インテリアショップに置かれるような洗剤をつくろう、と始まったプロジェクトでした。
実際に製品を見ていただければわかるんですが、「SOMALI」は洗剤が透明容器に入っています。

みなさんは、透明容器に入っている洗剤と聞いて、パッと何か思い浮かびますか?……実はほとんどないんです。それでも中には、透明な液を透明容器に入れている製品であれば、あるにはあるんですが、内用液に色がついているもので、透明容器に入っているのはほとんどないと思います。
なぜかというと、お風呂場に置かれたり、キッチンに置かれたりするなかで、内用液に色がついていると、退色するのがわかってしまうからなんです。しだいに濁ってしまう。しかも、店頭で陳列していても、ライトが当たるので変色してしまう。だから、だいたい着色容器か遮光性のある容器を使うのが一般的なんです。
それなのに、「SOMALI」は透明容器を使っていて、液体の色もオレンジです。液体に色がついているのも、洗浄力としてオレンジが油に効くからそうなっているのであって、色付けしようという意図はなく、ただ結果的についた色なんです。
透明容器を使ったのも、“あえて”ではなく、単にデザインが良いものを使いたかったから、結果的にそうなったんです。自社ブランドを始めようと思っても、大量生産はリスクがあるので、少量から始めたい。ところが、デザイン性のある容器から選べる選択肢はあまりなかったんですよ。
着色する必要のある容器の中にも、デザイン性の高いものはあるにはありましたが、そうするとロットが必要になって、何万個、何千個とつくらないといけなくなる。その点、透明の容器であれば、デザイン性が高いうえに数十個という少量単位でも仕入れられる。しかも、ノズルまで日本製のものを用意できる。
そういう流れで、なかなか選べる容器がなかったので、その狭い選択肢から考えて、「透明にしよう!」と決めたんです。
社内的にはめちゃくちゃ反対されましたよ、やっぱりリスクがあるので。実際に製品化した「SOMALI」も、退色したり、濁ったりはします。でも、それは「仕方がないことだ」として決断しました。
「天然の原料を使ったがゆえに、色が変色したり退色したりするのも、この製品の一つの個性だ」という考えに立って、そういう説明をしよう、と社内で話していました。ネガティブなものを個性として伝えていこうと発想を変えて展開したのが、自社ブランドの第一弾になりました。
おかげさまで、いまは販売から7年目ですけど、ギフト需要も増えて、会社のブランドとして大きい存在になっています。
井登:ちょうど「SOMALI」を始められる時期に、木村さんとご飯を食べながら、「自社ブランドをやるんですが、周りは反対ばかりですよ」というお話を聞いていましたね。まだその当時の木村石鹸さんの事業としては、大半が生協向けのOEM製造だったんですよね。
木村:そうです。生協向けのOEMで安定もしていたので、「なぜゼロから始める必要があるんだ?」という声が上がっていました。しかも、開発サイドの人間からしたら、「透明容器なんて、クレームが来るんじゃないか!?」と思いますよね。
それでも、なんとか社内で説得して、「それも個性にして売っていこう」と、採用してもらいました。最初は苦労しましたけどね。
VUCA時代に求められる「エフェクチュエーション」の発想
井登:選べるものも少ないし、できることも限られているし、やりながら進めるしかない、といった感じですね。それが会社としても大きなブランドに成長したということで、それだけでも非常に面白い事例なんですけど、それではこの特殊にも思える事例を、高広さんに「Plug-In」していただけるでしょうか。
高広:はい。では、この事例を理論観点から見たら、どういう理論に当てはめることができるのか。
この事例から“Plug-In”したい理論は、「エフェクチュエーション(effectuation)」です。エフェクチェーションというのは、サラス・サラスバシーというインド人の研究者が、博士論文で書いた理論です(※邦訳書としては、『エフェクチュエーション:市場創造の実効理論』/監訳:加護野忠男/碩学舎/2015)。
これは、優れた企業家の意思決定プロセスを体系化した理論です。たとえば、Twitter買収で話題のイーロン・マスク、日本だと孫正義さん、柳井正さんといった経営者のエピソードとして、現場の人から「朝と昼で言っていることがころころ変わるので、たいへんなんですよ」という話をよく聞くじゃないですか。でも、実はそれは、卓越した起業家の素晴らしい資質なんじゃないかと考えられるわけです。
特に、VUCA(※Volatility・Uncertainty・Complexity・Ambiguityの頭文字を取った言葉)と言われる不確実性の高い現代は、企業も未来がはっきり見えていない状態にあります。タイミングごとにいろいろなことを考える必要があるので、そんな時代に「朝令暮改」というのは実はすごく良い能力なんだ、と言っているような話なんです。
「エフェクチュエーション」に対して、もう一つ覚えてほしいのが、「コーゼーション(Causation)」という言葉です。この二つは対になる言葉で、「コーゼーション」というのは、ゴールがあって、その目的に向かって進みましょう、というものです。
マーケティング的には「STP分析(※Segmentation→Targeting→Positioningの順に市場分析をしていく、フィリップ・コトラーが提唱した古典的なフレームワーク)」から始める考え方ですね。市場を定義して、競争分析して、マーケットリサーチして、事業計画をつくって、資源と利害関係者を獲得して、時間とともに変化する環境に適応するというもの。
でも、そんなものはガラッと環境が変わったら、どうなるかわかりませんよね。たとえば、富士フイルムは事業環境が変わって、デジタルに移行していきました。そうした事例は世の中にたくさんあるんです。
みなさんも経験したことがあると思いますが、「これは絶対に目的を間違っているよ。でも上から言われているから進めないといけない」と、目的を変えられずに集団で突っ走って失敗することってありますよね。
この「コーゼーション」に対して、「エフェクチュエーション」は“手段”を重視します。「いま取れる手段は何?」という発想です。行き先やゴールは正直、いまの時代はわからないですよ。そこで、そのとき、そのときに最良の手段を取ることにフォーカスするのが、この「エフェクチュエーション」なんですね。
つまり、世の中の歩みが予測可能なとき、このゴールに向かえば大丈夫だという時代には、複数の手段を講じてゴールにたどり着けば良かったんですが、それが通じない時代になってきた。そうした事業環境の変化があるなら、そもそも市場の定義とか競争分析が変わってきますよね。競合と思っていた人たちとの戦いだけじゃなくて、異業種からの参入もあるし、そもそも自分たちの業種自体が崩れる可能性もあるわけじゃないですか。そうした状況なのに、果たして市場の定義や競争分析は役に立つのか……。
そこで、その対になる「エフェクチュエーション」では、「自分が誰であるのか」「何を知っているのか」「誰を知っているのか」という3つから始めるんです。まず「自分(自社)」なんですよね。
その3つの先に、5つの原則がありまして、「手中の鳥の原則」「許容可能な損失の原則」「クレイジーキルトの原則」「レモネードの原則」「飛行機の中のパイロットの原則」というものです。
「手中の鳥の原則」というのは、「取れる手段を取りましょう」ということです。先ほどの話でいくと、「透明な容器」というのは、まさに「取れる手段」だったわけです。
「透明な容器にすると、色が変わるのが見えてしまう」というのも、「そのリスクは、うまく説明したら良い」と考えれば、「許容可能な損失の原則」に入ってきます。
あるいは、「レモネードの原則」というのは、形の悪いレモンとか、ちゃんと生育していないレモンも、潰してレモネードにすれば売れる、というものです。要するに、「持っている資産をどう活かすことができるのか」という話ですね。
「飛行機の中のパイロットの原則」というのは、飛行機が飛んでいるときに、パイロットがトラブルを抱えたら終わりですよね。だから、飛行機がそうなったときに取れる手段を(あらかじめ)講じておく、というものです。
こういったスキルが卓越した起業家にはある、というのが、サラス・サラスバシーが論じたことです。
そういう意味では、木村石鹸さんが取られた手段、特に透明な容器のお話というのは、まさにこの理論があれば、うまく説明がつく話だと思います。企業における事業活動のなかで、木村石鹸さんのお話と同じような場面に出合ったときに、この理論を「Plug-In」しておけば、乗り越えられるかもしれないわけです。
あの「柿の種」も、偶然の“失敗”から生まれた!?
井登:誤解されないように高広さんのお話の補足をすると、サラス・サラスバシーは「時代が変わったから、もうコーゼーションは必要ない」と言っているわけではないんですよね。変わらず「コーゼーション」も重要で、管理可能な状態でやれる場合は、「コーゼーション」の発想は素晴らしいのでやっていくべきだ、と。
ただ、そうじゃない状態なのに、そこに拘泥すると泥沼にハマる。いまどういう状態にいるのか、あるいは同じ製品でもライフタイムバリューのなかで変わっていくので、どの時期なのか。だから、「コーゼーション」の時期と、「エフェクチュエーション」の時期と、いまがどうかを考えたときに、選択可能なものを増やしていくのが大事、というわけです。
高広:そうです。この両方を使いこなすことが大事です。
井登:この「エフェクチュエーション」による成功事例は、身も蓋もない言い方をすれば、「ただ思い付きでやっているんじゃないか」と思われそうですし、そこには思い付きの要素もあるとは思いますが、そう言って終わらせては学びがありません。
ここまでは木村石鹸さんの個別事例を高広さんに「Plug-In」していただきましたが、一般的にも説明できるようになっていることを示すために、別の事例もお話しいただけますでしょうか。
高広:有名な事例として、「柿の種」があります。みなさんの中に「柿の種」がどうやって生まれたかを知っている方はいますか?
実は「柿の種」にも誕生秘話があって、めちゃくちゃ「エフェクチェーション」に当てはまる事例なんです。
紹介する日経電子版『NIKKEI STYLE』の記事では、「金型踏んづけて柿の種、試行錯誤の柿チョコ 誕生秘話」というタイトルがついていますが、金型を間違えて踏んづけてしまって、「さて、どうしようか?」というところから生まれたのが、いまの「柿の種」なんですよ。もともとは小判の形でつくろうとしていたんです。それを変形した金型のまま製造したら、ものすごく売れた、というのが誕生秘話です。
これは「レモネードの原則」と「手中の鳥の原則」に当てはまりますよね。決して「失敗した」で終わっていないんですよ。目的志向型で「絶対に小判型にしないと」という発想からは、いまの「柿の種」のヒットは生まれていないんです。
井登:本物の柿の種子って、ふつうはこんな形じゃないじゃないですもんね。「柿の種」の形は、新潟にある柿の種子の形なんですよね。創業者の出身地である新潟固有の柿は、種子が曲がった形で、「それに似ている形になったから、さらに良い」となった。
完全に後付けと言えば後付けですけど、それを「後付け」ですませると単なる面白い話で終わりますが、理論的に見てもそこに有効性がある。何が有効性があるかを、特殊な例と考えすぎずに扱っていくことで、再現性も出てきますね。
高広:そうです。「エフェクチュエーション」を知っていると、「これは、あの事例と同じだ」「これとこれは共通点があるな」と発想が生まれてきます。
「正直さ」を武器に変えた、「キャッチコピーがつけられない」シャンプー
井登:この感じで続けたいと思います。では、木村石鹸さんの例をもう一つお願いします。自社ブランドの「12/JU-NI(ジューニ)」について、ぜひお話してください。

木村:これはいちばん最新のブランドで、2年前に出たシャンプーとコンディショナーのブランドです。木村石鹸はもともとはシャンプーの製造を行ってなくて、やる予定もなかったんです。
ちょっと言い方は悪いんですが、この製品は開発者が勝手に作っていたものなんですよ。多胡健太朗という者が開発したんですが、彼にとってシャンプーの製造はライフワークなんですね。
もともと彼はシャンプーの原料メーカーにいて、商品開発をしたくてシャンプーのOEMの会社に行ったんですけど、いろいろとあって開発できず、木村石鹸に入れば自由な時間が取れるということで入社して、ライフワークとして開発を続けていたんです。
それで突然、「こんなものができましたー」と社内で報告がありまして、実際に使ってみたら、とても良かったんです。
ただ、木村石鹸ではシャンプーは扱っていないし、話を聞いても木村石鹸っぽくないんですよ。木村石鹸は、名前の通り石鹸のイメージがありますし、自然派な安全志向が基本なんです。
だから、仮にシャンプーを販売するにしても「ノンシリコンが良いんじゃないか」と思ったので、「ノンシリコンなの?」と聞いても、「シリコンはガンガン使っています」と。「じゃあ、自然派って謳える?」と聞いても、「一切ないです、ケミカルです」と。ただ、「自分にとって理想的な、本当に髪に良いものができたんです!」と言うんですね。
そうしたキャッチコピーを付けようがないものができたので、「どうしようかな~……」と困りまして、最初はよく木村石鹸を知っている方に向けた会員限定で販売するのが良いかなと思っていたんです。
ところが、そんなときにデザイナーに相談したら、「謳い文句がないことが、むしろ売りになるんじゃないか」という言葉が返ってきたんです。
すでに販売されているシャンプーは、いろいろと必死に謳い文句をつけているけど、この製品にはそういうのは一切ない。それでも、とにかく良いものができてしまった。そういうスタンスは、木村石鹼っぽいんじゃないか。そう言われて、確かにそれは面白いなと感じました。
真っ正面から「髪を本気で良くする製品なんだ」と売ることを考えたら、「正直さ」が軸として見えてきたんです。それで、「SOMALI」が透明だったので、こっちも内容物がすぐに見えるように、透明容器にすることにしました。
そのうえで謳い文句として、「髪に合う人合わない人がハッキリ分かれる」ということを全面に押し出す。基本的に、どんなシャンプーも化粧品もそれはそうなんですよ。全員に合うわけじゃない。あえては押し出していないだけなんですけど、「正直さ」を売りにするなら、そこを全面に出したほうが良いということで、広告のメッセージや、サイトの商品説明に、全面的に「合う人合わない人が分かれます」と打ち出したんですね。
その姿勢に共感して、支持していただいて、試してみたいという反応が来ました。それで使ってみたら髪に合った、という方が増えていって、いまでは自社ブランドとしてはいちばん大きなブランドになっていますね。
井登:ちょうど2年くらい前から始められて、僕もTwitterなどを見ていましたが、すごい反響が消費者の方からありましたよね。そこでよく目にした言葉は、「木村石鹸は正直すぎるぞ」という反応です。「『合わない人には合いません』『あまりに良い製品ができてしまったので、広告を打ちます』なんて、正直すぎるだろう、木村石鹸!」という感じで。
ややもするとこうした打ち出しは、レトリックとして「狙ってやっている」と捉えられがちなんですけど、何せ木村石鹸さんは社員にマーケティング専従の方がいらっしゃらないんですよね。製品開発の方が広告もやっているような体制で商売をされているので、これも素でやっているんですよ。そこを消費者の方も面白がっている面もあるし、興味を持たれる面もある。
いわゆる時流というか、昨今の世の中の流れとして「シャンプーと言ったら、こうだよね」というのとはまったく違うところにあるのに、響く人がいて、支援者が生まれて……。これも常識では説明がつかない特殊な事例なんですが、ここで高広さんに「Plug-In」をお願いしましょう。
高広:「Plug-In」の前に、広告の話を聞いて思い出したことがありました。
私は松下幸之助さんの広告哲学が好きなんですけど、松下さんは広告を打つ前に、まず「良い商品をつくった」という自負があるんです。「人々の生活を豊かにする良い商品をつくった」という前提があって、それなら多くの人に使ってもらうべきなんだけど、そのために何をしなくちゃいけないか。その段階に達したときに広告を打つ、というのが松下幸之助さんの広告哲学だったんです。
いまは風潮として、ちょっと違うじゃないですか。多くの広告が、無理に服を着させるようなことになってしまっているんですけど、まさに木村石鹸さんのお話は、松下幸之助の哲学と同じだなと思いました。
「“意味”のとらえ方」でイノベーションは起こせる!
高広:話を戻すと、この「12/JU-NI」の事例にも「エフェクチュエーション」の考え方は当てはめられますが、ここでは別の理論を話したいと思います。
それは「意味のイノベーション」という考え方です。ロベルト・ベルガンティというイタリア人の理論ですね。本当は、井登さんのほうが専門なんですけど、私が説明させていただきます。
私は原著の『Overcrowded』を読んだんですが、邦訳書もタイトルを変えて出ています(※『突破するデザイン:あふれるビジョンから最高のヒットをつくる』/監訳:八重樫文/日経BP/2017)。そこでは、技術主導型や市場牽引型のイノベーションに対して、それらが飽和する中での第三のイノベーションを提唱しているんです。
市場や競合他社を見て、どこも他の企業との差別化戦略を考えながら、いろいろと製品やサービスをつくるんだけど、結局は似たものができて飽和してしまうんですね。技術主導型なら「こんな新しい技術ができました」、市場牽引型なら「お客さんの新たな声を聞きました」というところからスタートするんですが、どちらにせよ、次第に市場の中での取り合いになって飽和状態になってしまう。
そこでの一つの考え方として、ブルーオーシャン戦略(※それまでには存在しなかった新しい領域を見つけ出し、事業を展開する戦略)を取る手もありますが、ブルーオーシャンを探すのは、実際にはめっちゃくちゃ難しいんですよ。
そうではなくて、そもそもの製品やサービスの“意味”というものを考えるのが、「意味のイノベーション」なんです。イノベーションを「技術革新」としてだけでとらえるのではなく、人々が感じる“意味”というものに注目しようという考えですね。
「技術によるイノベーション」と「意味によるイノベーション」を考えると、変化のスピードや変化のステップとして、技術主導型は基本的には急進的な変化が起こせます。たとえば、カシオのデジタルカメラによって、一気にカメラ市場が変わったということがありました。それに対して「意味のイノベーション」は、さらに急進的な変化をもたらす可能性が高いと、ロベルト・ベルガンティは書いています。
時間がないので、ごくごく簡単に説明すると、技術的なイノベーションの難易度が高くなるなかで、いまは製品の「意味のイノベーション」を問われているんです。
もともと、クラウス・クリッペンドルフという研究者がいて、この方はサイバネティックスや言語学の畑の人なんですけど、「デザインとは、われわれは人工物に意味を与えること」という言葉を残しています。そこから発想して、ベルガンティは「意味のイノベーション」を考え出したんです。
あるいはイノベーションについて、「ユーザーに話を聞いて、ユーザーの課題を解決する」という発想に立つと、これは「デザイン思考」ですよね。
私は、あまり「デザイン思考」を信用していないんですが、なぜかというと、ユーザー主導の見地に立って、ヒアリングしてポストイットを貼って……としていくことで、本当にユーザーの課題が現われるとしても、それだとどの企業でも最終的には同じ課題にたどり着いてしまうじゃないですか。じゃあ、同じユーザーの課題を解決しようとしているんだとしたら、そこに差は生まれますか、という話ですね。
そう考えるから、いわゆる世の中で言われている狭義の「デザイン思考」には、否定的なんです。
こうしたユーザー主導の発想は「アウトサイド・イン」と言うんですが、それに対して「意味のイノベーション」は作り手主導です。作り手の中にある「これは好きになってもらえる!」「これは使ってもらえる!」という部分を活かしていく。こちらは「インサイド・アウト」という発想で、“意味”を生成していくことになります。その過程が重要だというのが、ベルガンティが提唱している考え方です。
井登:ベルガンティはイタリア人なので、「イノベーションとは、なんですか?」と聞くと、「アモーレだ」と言うんですよね。つまり、「愛である」と。「人々に何を愛してほしいと思っているのかを、一生懸命に考えるんだ」と、こう答えるわけです。
高広:そのあたりの話は、ものすごく話したいことがあって、京都学派の西田幾多郎という哲学者なんかも、「愛」という言葉をけっこう使っているんですよね。そういうことも含めて、「愛」は面白いテーマになるんですが、その話は今日はできないので、次にいきます。
ベルガンティが語る有名な話として、キャンドル(ローソク)があります。キャンドルの消費量って、実は増えているんですよ。2000年くらいから増えている。じゃあ、90年代までと2000年以降の間で、みなさんは電気を使わなくなりましたか? ……使ってますよね。じゃあ、キャンドルは、どのように使われているんでしょう?
キャンドルはもともと、「灯り」だったわけです。家を照らす灯りだったものが、「ムードをつくる」という、まるで違う使われ方をしているんです。モノは同じなのに、“意味”が変わったんです。この例は、「意味のイノベーション」を語る際に、いちばんよく使われるデータです。
先ほどの「12/JU-NI」のお話に戻ると、ノンシリコンや自然派といった意味付けは、いまの業界の主流なんですよ。誰でも主流から外れるのは怖いですよね。
でも、主流じゃなくても、製品に対する“意味”を、ある種のイノベートをして伝えられるかが大事なんだということが、この木村石鹸の事例には見て取れるんじゃないかなと思います。いかがでしょうか?
木村:私の“エッセイ”が解釈されて面白いです(笑)。
高広:では、もう一つ事例を。もはや“意味しかない”という他の事例を持ってきました。「Liquid Death(リキッド・デス)」です。みなさんはご存じでしょうか?
これは、“ただの水”です。パッケージには「MOUNTAIN WATER」と書いてあって、「Liquid Death」とロゴが入っていて、スカル(骸骨)が描かれていますが、ただの水なんです。
クラブとか、ハードロック系のライブ会場に音楽を聴きに行ったとき、健康志向のペットボトルを飲んでいたら、格好悪い感じがするでしょう。「Liquid Death」は、そういう人が飲んでいても格好悪くないパッケージなんですよ。ただの水ですが、デザインも含めて新たな“意味”を提供しているのが、この「Liquid Death」なんです。
ポイントとして、中身は変わっていないんです。大きな潮流のなかで言われていることを、どういう“意味”としてとらえ直すか、変換するか。クラブやライブ会場に足を運ぶ人々に対して、「本当は水を飲みたかったけど、こういう感じで飲みたいんだろう」と提案する。そこには、そうした音楽愛好家に対する“愛”が現われているわけです。
井登:「うまいこと言っただけちゃうか?」という声が返ってきそうなところですが、ベルガンティはキャンドルの例を使いながら、それに対しても説明していますね。
単に時代をとらえただけの提案では、他の企業もすぐにマネできてしまうので続かない。そうじゃなくて、文化や社会、時代の変化をとらえて、ある瞬間に「今だ」というタイミングで提案する。それができるためには、実はむちゃくちゃ前から長期間にわたって考えているんだ、と言っているんですね。
現代のキャンドルの意味付けは、アメリカ生まれのキャンドル・メーカーである「ヤンキーキャンドル」から始まっているんです。キャンドル・メーカーとしては、何百年という老舗ばかりの中で、ヤンキーキャンドルは1969年に創業しているので、めちゃくちゃ新参なんですけど、市場をすべて持っていったんですよね。
でも、急に成功したわけではなく、そうなるまでにもずっと考えていたんです。「いまは香りだ!」「癒しが来る!」という発想じゃなくて、社会の変化の仕方をずっと何年も見ていることで、「これだ!」というのが生まれてくる。
それが「意味のイノベーション」なので、ベルガンティは単なるコピーライティングや表面的なマーケティングではなく、「意味は研究開発の対象である」と言っています。多くの企業はそう扱わないけど、意味を研究開発の対象として扱って柔らかい頭で考えることで、製品は変わっていなくても、周りの意味が変化していっていることに気づける、と。
高広:そうした発想を生むには、関西文化にあるような、新喜劇みたいななある種の「ナンセンス」が求められると思います。「意味をなさない=ナンセンス」があって、それが面白い話になる、という関西みたいな場所は、「“意味”をどうとらえるか」ということに対して、実はとても自由なエリアなんじゃないかなと僕は思います。
井登:今日は時間の関係で、二つの「Plug-In」しか用意できませんでしたが、本当はもっとたくさんあると思います。個別の成功経験や特殊解が、理論として一般化されてくると、汎用性が出たり、再現性が生まれたりして、特殊な業界で起こっていることが、別の業界でも転用できるようになる。
私たちマーケター、デザイナーは、そうした理論をたくさん持っておけばおくほど良いですよね。そういう頭のモードを多くの方に理解していただけると、マーケティングはより面白くなってくると思います。
******************************
マーケティングにおける「理論」と「実践」。その間には、少なからず溝がありますが、セッション中に高広氏がおっしゃっていたように、両者が循環することで、マーケティングはより魅力的に、より有益になっていくのではないでしょうか。
モデレーターの井登友一は、集まった日々マーケティング活動を行う実務家たちに向け、「マーケターの方同士で、お互いに持っている『Plug-In』をどんどん共有してはいかがでしょうか」と投げかけ、セッションを締めくくりました。