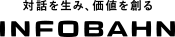地方移住は? 地方メディアは? 生き残る町は?【鈴木円香対談Q&A】

2023年2月14日に、一般社団法人みつめる旅・代表理事の鈴木円香さんをお招きして、弊社代表取締役会長(CVO)・小林弘人との対談を実施いたしました。オンライン配信を行った当対談イベントの最後には、ご視聴いただいた方々からたくさんの質問をお寄せいただきました。その回答の一部を、記事としてお届けします(本編はこちらから〈第1回〉〈第2回〉〈第3回〉)。

※読みやすさを考慮し、発言の内容を編集しております。
********************
Q)「地方移住」の現実は厳しいでしょうか?
A)「お試し」の気持ちで始めてはどうでしょう。
――首都圏に住んでいるのですが、リモートワークも多くなり、最近、地方移住に憧れが出てきました。ただ、「合わなかった」「現実は厳しかった」という人の話もよく聞きます。やはり人によって合う合わないはあるでしょうか。鈴木さんはいずれ五島に移住する気持ちはありますか?
鈴木円香(以下、鈴木):合う合わないはあると思いますね。私は本当は移住したくて、子育てが終わったら五島に移住しようと着々と準備を進めています。ただまあ、合う合わないという話で言えば、「いきなり移住しなくてもいいんじゃないかな」とは思いますね。
小林弘人(以下、小林):そうですね。
鈴木:少しずつそこに通いながら、いろんな季節を過ごしてみて。ハイシーズンに行ったら、その次は真冬のローシーズンに行ったり、「本当になんの娯楽もないところだ」っていうようなことも1カ月くらい体験してみたりして、慣らし期間はやっぱり持ったほうがいいと思います。
あとは、付き合いやすい人とだけ付き合うっていう考え方でもいいと思うんですよ。五島だと20代、30代の移住者が年間200組以上移住しているので、けっこう移住者コミュニティだけでも付き合える人は、たくさんいるんですよ。
小林:すごいですね。そんなにいっぱい。
鈴木:楽しく過ごせちゃうんですよ。私もかなり仲良い人は、同世代の移住者だったりもします。それだとなかなか地元のディープな人と関わる時間はなかったりしますけど、それでもいいんじゃないかなって。いきなりディープなところに入っていくのは難しいと思いますし。
5年くらい経ってから、ようやく地元の方から声をかけてもらえるようになった、というくらいの時間軸で考えてもいいんじゃないですかね。無理しないことです。
小林:なるほど。ちょうどニュースとしても最近、福井県池田町(※1)という町で、移住者向けのマニュアルを配って、「あなたは観察されてますよ」みたいな、かなり厳しいことが書いてあったと話題になりましたね。
それぞれの地域によって特有のしきたりや雰囲気があるから、僕は言っていることはわかるし、理解できるんですよ。だけど、活字にされて渡されると、逆に「やっぱり移住するのはやめようか」みたいになっちゃうこともある。
だから、お試し移住的な受け入れをしている市町村も、最近は出てきてるんですよね。そこでは本格的な移住の前に、ちょっとお試し泊みたいなことができるんです。
鈴木:ありますね。別に移住するからにはって、無理してその地域に順応しようとは思わなくていいんじゃないかなって思います。
小林:そうですよね。その地域のルールのなかには尊重しなくちゃいけないものもある一方で、だからといって単によそ者ということで何か不当な差別を受けたりするのもおかしい。そういうところはたぶん、今後は人が集まらなくなるし、大変なことになってくると思います。
僕が今、お付き合いさせていただいているところには、オープンマインドな自治体も多いんですが、背景に「待ったなし」な状況があるんですよ。「とにかく人がいないせいで猿の被害がすごいから、誰か来て追い払ってほしい」とか、誰でもいいから来てほしいというところも多い。
だから、移住先の選択肢も、いくつかもたれてもいいんじゃないかなと思いますね。
鈴木:そうですね。いろんなオプションを持つのがいいと思います。
それと、行く人だけが苦労して順応しようとするんじゃなくて、受け入れる側である地域の意識も変わらなきゃいけないとも思いますね。人生をかけて、家族連れで移住してきてくれるなんて、ありがたいことじゃないですか。
小林:移住者は税金も払いますからね。
「最近、若い人たちに人気」とか「コロナ禍以降、移住者が増えている」とかとは別に、昔から移住者に対して優しいところは、脈々と続く移住者のコミュニティがあったりするんですよね。そうすると、新参者でも「ちょっとあいつを紹介しようか」みたいな感じで交流がしやすい。
それでも、テスト期間はあると思うんですよね。当事者同士ですらテスト期間とは思ってないでしょうけど、やっぱり探り合う期間というのはありますよね。そもそも人と人の関わり合いは、すべてそうじゃないかとは思うんですけどね。
鈴木:そうですよね。そのなかでも移住者コミュニティはありがたいものです。
小林:知り合いが沖縄で、そういった移住者のためにWebサイトをつくってあげているんですよ。「何か困ることがあったら、連絡してくれ」っていうサイトを、コロナ禍よりもっと昔から運営しています。
鈴木:私も五島に行ったら、しょっちゅう車のバッテリーがあがっちゃうんです(笑)。そうしたときに、本当にコミュニティの存在はありがたいですね。
小林:なんでバッテリーが?
鈴木:東京で私が乗ってる車は自動でライトが消えてくれるんですが、向こうで乗る車は手動なので、消し忘れてバッテリーをしょっちゅう上げちゃうんですよ。
小林:あっ、形式が古いんですね。
鈴木:それでいつもみんなに助けてもらってます。「また鈴木さん、上げちゃったのか~」って。
――――――――――
※1 福井県池田町
詳細は右記記事を参照のこと。「移住者は「都会風吹かさないで」…福井県池田町の広報誌に載った“七か条”に住民反発、考えた区長会の思いとは」『福井新聞 ONLINE』2023年2月9日配信〈https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1722329〉
Q)地方発信のネタ元はどこから?
A)自分自身の「感動」が第一。
――編集者として地方から発信される際に、「これは面白い」「これは広く伝えていきたい」と感じるのは、どのようなきっかけが多いでしょうか。何かしらの直感が湧いたときでしょうか。生産者などの人柄や熱意を感じたときでしょうか。
小林:インスパイアされるその源泉をもっと細かく教えてくれという話ですが、いかがでしょうか?
鈴木:やっぱり、そのときの感動じゃないですかね。具体的な地名は伏せますけど、東北の人口2万人ぐらいの小さな町があって、そこの村長さんから「うちでも何かやりたい」と相談されたことがあるんです。それで現地に行って2泊くらいしながら、一緒にネタ探しをしたんですけど、私が一番感動したのは、道の駅で売られていた梅干しだったんですよ。
地元のおばあちゃんがつくった、いろんな種類の梅干しが、棚いっぱいにズラッと並んでいたんですけど、その中にものすごくキレイなピンク色の梅干しがあって。こんな見事な梅干しをどうやってつくったんだろうって、すごく感動して、「地域中の梅干しづくりのおばあちゃんと、梅干しをつくるイベントをやりたい」って話しました。
小林:梅干しですか。
鈴木:これだったらフルコミットしてでもやりたいってくらいに思いましたね。それは企画にはなりませんでしたけど、そのぐらいのちっちゃなネタでも十分に面白いことはできると思いますね。
小林:そうですよね。ルールはない気がします。
鈴木:なんでもできますよ。広島県のとある島から相談を受けたときも、「柑橘キャンプをやりませんか」って提案しましたね。
小林:それはなんですか?
鈴木:あらゆる柑橘類が採れると聞きまして。柑橘好きの人は一定数いるので、「柑橘尽くしの柑橘キャンプをやりましょうよ」と、閑散期に人を呼ぶ手段として提案しましたね。ネタはいくらでもあると思いますよ。
小林:そこを見つけられるかどうかは、何か才能が必要というよりも、「自分がどこに感動できるか/したか」というところですよね。それが共感を呼ぶことにもつながってきますから。
Q)東京中心のメディアはズレている?
A)「東京だからこそ」の意義はもうない。
――新聞やテレビなどのメディアは、東京の視点が中心だなと感じます。鈴木さんも小林さんも東京の出版社などで働かれてきたと思いますが、そうしたズレを感じることはありますか。また、ローカルにも元気がありそうなメディアはありますが、地方メディアの可能性についてはどう感じられているでしょうか。
小林:いかがでしょう。まずズレについては?
鈴木:ズレは出版社で働いていたときから、思っていましたね。今はどうかわかりませんが、私が本を編集していたころは、紀伊國屋新宿本店のような東京の大型書店の売り上げにみんな一喜一憂していたんですよ。
小林:POSデータがわかる書店(※2)ですね。
鈴木:そうやって東京で本が売れているかどうかが、一番のベンチマークになっていました。私は兵庫県の地方出身なんで、ずっとその違和感はありましたね。東京中心の視点で企画が通って、本がつくられて、東京の書店の売れ行き次第でいろんなことが決まっていくっていう、その素朴な構図に対して。
それはWebメディアに移ってからも、Webメディアは出版社以上に取材の費用が限られているので、結局は東京にいる編集者や記者が費用をかけずに取材できる範囲で記事をつくりがちになるので、結局は東京に偏っちゃうんですよね。
小林:それはよくわかります。
鈴木:だから、東京中心になる歪さについては、メディアにいるときから一貫して疑問に思っていましたね。
それで、こうしてポンッと五島に出たときに、「いや、むしろ東京以外の視点というのがマジョリティーで、東京は日本におけるマイノリティーなんじゃないの」ってさらに思いました。「こっちのリアリティのほうが、圧倒的に日本人にとってのリアルな感覚なんじゃないの」って。
そういう意味で、地方のメディアにもこれから可能性はあるんじゃないですかね。テレワークができるようになったことで、逆に地方メディアも東京にいる人材を潤沢に使えるようになったじゃないですか。そもそも地方か東京か、どっちの媒体かっていうのが、あんまり意味をなさなくなった時代なのかもしれないですね。
小林:まさにそう思いますね。僕は「分散化するオシャレ雑誌」とでも命名したい現象が起こっていると思っていまして。昔のオシャレ雑誌って、「下北沢のここに行け」「自由が丘のあそこに行け」みたいな感じでしたけど、もうそういう時代ではない。
僕は二拠点に近い形で、プライベートで岐阜県高山市によく行ってるんですけど、高山にも素敵なお店がたくさんあるんですよね。それで地元の人が、フライヤーとかイラストの入った小冊子とかで、そうしたお店を取り上げていて、ものすごく良く出来ている。そういうのを実際に見ると、「もう東京のほうがダメじゃん」「東京の商業出版のほうが遅れているかも」という感覚がします。
いや、より正確に言うなら、「進んでいる/遅れている」ということではなく、「分散化してる」んだなと思います。東京の出版社などでスキルを磨いた人たちが地方に行ったり、雑誌に憧れた地方の人たちが自分で制作したりと、移住イノベーターの話(※第二回記事を参照)と同じで、そうした面白い人がどんどん増えて、質も上げてきているから、どこかの瞬間にもう逆転しているのかもしれないなと。
鈴木:そうですね。逆に言うと、「東京のメディアだからこそできる」という領域は、どんどんなくなっているというのもありそうですね。
小林:そうですね。「東京に最先端の情報が来る」という考え方もまた、狭い考えですよね。少し海外に行くと、「こんな面白いこと起きているのに、何で日本の人は知らないの?」みたいな情報がたくさんあるんです。
そこがもっとフラットになっていって日本の地域と世界がつながったら、もう「ええ!? 東京の人は知らないの、これ?」というムーブメントだって起こるかもしれません。いろいろと、都市と地方の関係も逆転していくんじゃないかなと思いますね。
鈴木:もうすでに、どんどん逆転は起きてる気もしますね。
――――――――――
※2 POSデータがわかる書店
紀伊國屋書店による「Publine」をはじめ、契約した出版社がPOSデータを見られるサービスを、いくつかのナショナル書店チェーンが展開している。大型書店は東京を中心に都心部にしかないため、必然的に都心に比重が偏った参考データとなる。
Q)衰退せずに生き残れる町はどんな町か?
A)才能を集め、育てられる地域。
――10年ほど前に、全国で多くの町が消滅することを具体的に予測した「増田レポート」が話題になりました。それ以降も変わらず人口が減り続けるのが確定的な日本のなかで、(都市部を除いて)生き残れる町と衰退する町とは、どんなポイントで分かれると思いますか?
小林:日経新聞のサイトに公開された、「人口減少待ったなし」の市町村を表したヒートマップがあって、最も待ったなしの地域が赤く表示されているんです。それで日本全体を見ると、あちこちが真っ赤なんですよ。つまりは、どこもかしこも待ったなしになっている。
単純に税収が減っていて維持が難しいから、市町村合併していかないと経営的に苦しいという、経済的な問題を抱えているところは多いですね。アメリカでも前に、デトロイトが財政破綻をしています。財政破綻する自治体は、今後も出てくる可能性がありますし、一番の課題は経済面じゃないかと思いますね。
鈴木:そうして、「どう生き残るか」ってなったときに、「観光地としてインバウンドを」とか「軍事基地を誘致する」とか、そういう話になっちゃうんですよね。どうしても、「無理にでも人を呼ぶしかない」みたいな話になっちゃうところで、何か第三の道はないのか。そういう道は国の施策としても、ビジネスサイドからも出てくる動きだろうし、自分たちはそれ以外の第三の道を何か模索していきたいなと、いろいろとやっているんですけど……。まあ才能が集まる場所、才能を集められる場所にすることじゃないかなというのが、一つの仮説ですね。
小林:才能さえ集めちゃえば、あとはなんとかなるというね。
鈴木:才能を集めてどうするかという具体的な話の前に、才能が一番の力の源泉じゃないかなという仮説ですね。
小林:那須のほうにカフェが有名な町並みがあるんですが、そこは1軒素敵なカフェができたところから、あらゆるカフェをやりたい人たちがどんどん集積していって、それから観光客を呼べるようになったという実例ですね。意図した戦略通りに成功するとは限りませんし、何が幸いするかはわからないと思います。
第三の道として僕が面白いなと思う例として、ある市町村で、ベーシックインカムとまではいかなくても、移住者に田んぼ付きの家1軒を200万円で譲渡するという取り組みをしているところがあります。そうしたライフコストの安さも、移住者としては地方の魅力の一つですよね。
あるいは過疎地域だと、獣害に悩んでいるような地域がたくさんあるんですね。そうすると常設の店でなくても獣が来ないようにしてくれれば、ということで、定期的に音楽イベントを開く場所になっているところもあります。人がいない場所だからこそ、ものすごい音量を出しても問題ないから、主催者側にも好都合なんです。
そうした逆転の発想で、町や村に何ができるのか。その意味でも、奇抜なアイデアが思いつく人、良い意味で変な人を集める。やっぱり才能が集まる場所っていうのが、一番なのかもしれませんね。
鈴木:逆境を楽しめる才能ですよね。人口も減ってる、お金もない、何もないみたいなとこに、「むしろそれがチャンスじゃん」って来てくれるような面白い才能を集めてくる。
あとは教育ですね。五島が生き残る道として大事だなと私が思っていることが二つあって、一つは才能を集めてくることで、もう一つは才能を生み出すこと。
たとえば五島で育った子はみんなバイリンガルに育つとか、五島だからこそ世界レベルの教育が受けられますとか、魅力的な教育環境がないと、やっぱり家族連れの人は集まってこないんですよ。逆にそれがあると、海外からでも簡単に人が呼べちゃう。海外から移住者が直接来てくれるくらいの、バリ島にある「グリーンスクール(※3)」みたいなものを五島につくるとか、そういうレベルのことをやらないと、なかなか生き残っていくのは難しいと思ってます。
小林:確かに、そうですね。僕も移住者視点でのポイントとしていつも考えるのが、医療と教育、つまりは病院と学校なんですよね。小学校、中学校まではいいとしても、高校になった瞬間にものすごく遠くまで行かないと学校がないというケースが多々あります。
長野県佐久市なんかは、オルタナティブ・スクールが今はたくさんできていて、移住者がものすごく増えてるんですよ。佐久市は昔から病院は充実しているので、子育て世帯に人気が出てきています。
この2つをまずどう置くか。現実にその2つを置くのは、なかなか難しいんですけどね。それでも、お金に余裕のある資産家の人たちのなかでも「日本は教育が問題だよね」と感じる人が増えているので、面白い学校をつくるのは、その地域にとって大きな武器になると思いますね。
――――――――――
※3 グリーンスクール
竹でできた校舎、自給自足を重視した運営、自然環境を活かした授業などの特長を持ち、世界中から子どもたちが集まるインターナショナル・スクール