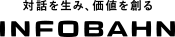ブランディングで漁業にイノベーションを! 地方に広がるブルーオーシャン【小西圭介対談2/3】

2023年4月7日に、株式会社ニュースケイプ代表の小西圭介(こにし・けいすけ)さんをお招きして、弊社代表取締役会長(CVO)・小林弘人との対談を実施いたしました。
「漁業ブ」の活動を通じて、専門であるブランディングを武器に日本の漁業を支援する活動をされている小西さん。自然環境保護におけるハードル、高齢化や後継者不足などのなり手の問題、地場産業としての経営の困難など、漁業は「サーキュラーエコノミー」「持続可能性」の観点から見て、さまざまな社会課題に直面している産業です。
小西さんが関わっている日本酒の「獺祭」とフグの養殖を掛け合わせた取り組みなど、事例を織り交ぜながら、第一次産業、地場産業の未来について、議論しました(第2回/全3回、第1回はこちら、第3回はこちら)。

日本の漁業を守るにはオープンイノベーションを
小林:漁業にいろんな新しい流れがあるなかで、ただやっぱり新しいなり手、新規の参入者がいないという課題は根深そうですね。Uターンか、もしくは全然住んだこともないけど、そこに行って漁師になりたいみたいな方は、あまりいないのでしょうか。
小西:私も漁に毎月のように参加させていただいていた時期があって、めちゃくちゃ面白いんですけど、正直やっぱり漁師さんのお仕事というのは、本当に大変でもあるんですよね。
たとえば、魚の旬は魚種によっていろいろありますけど、多くは脂の乗る冬じゃないですか。そうすると当然ながら海は非常に寒いんですよね。ブリとかカニとかを獲る漁師さんが、その寒い中、朝早くに海に出て、何時間もかけて獲って来てくれるから、われわれは当たり前のように美味しい魚を食べられているんです。
小林:たとえば、農業でも高齢化は進んでいますが、全自動農業とか、収穫にロボットを使ったりとか、オートメーション化も進んでいるんですけど、海だと難しいんですかね。
小西:北欧の漁業などはものすごくシステム化されていて、陸上げや加工を少人数で回せるよう自動化されたり、船上で獲れた魚の情報が共有されることで、オンライン入札で競りも完了したりする産業になっています。その点では、まだ日本の場合は一部の遠洋漁業を除いて、魚種多様性も問題なども絡んで、その仕組み化がなかなか難しいという実情がありますね。
進むとしたら、今一番有望なのは陸上養殖でして、これは大手商社も多く参入しています。この数年、漁のリスクとして、海温上昇やそれによる魚の生態系の変化、赤潮の影響などによって、魚がなかなか獲れにくい状況がすごく顕著になってきています。
陸上養殖はその自然のリスクを避けながら、恒常的な育成ができるし、トレーサビリティーもはっきりしていて管理もしやすいということで、設備投資や電力コストなどの問題はありますが、たぶんあと10年~20年もすると、魚も工場でつくられるものが大半になりそうなくらいにまできていますね。
小林:プラントベースの魚ということですか。
小西:そうです。今の状況を見ていると、需要としてそのあたりが伸びてくるのは、もう明白な未来だと思います。

他にも、いろんな形で地域性を守ろうという動きは出てきていますね。大きなところでいうと、環境省が最近、「地域循環共生圏」という大きなコンセプトを打ち出しています。これは地域内のいろんな産業が交流しながら、総合的に価値を高めていこうという取り組みです。
小林:産業同士が交流して、というのは大事なポイントですよね。以前から企業では、部署横断でオープンイノベーションをやりましょうという議論は言われてきましたけど、行政や産業の垣根についても、同じことが言えると思います。
たとえば、この管轄は農水省、こっちは環境省とか、この問題はこの産業、こっちはあの産業とかではなく、そういった垣根を全部ミックスできたら、エリアのオープンイノベーションが生まれてくるはずなので、それはすごく理解ができます。
小西:水産庁も最近、「海業」という言い方をしています。漁業も、観光も、あるいは再生可能エネルギーも、大きく海に関わるいろんな産業をまとめた捉え方ですね。
ただ、そのことの価値は言われだしても、まだなかなか官庁の中も垣根を超えにくいところはあります。
小林:業界を超えるのもまた大変ですしね。
僕も生物多様性の問題に対して、「自然会計資本」という考え方を使ってどういうイノベーションを起こせるかを考えるイベントをしたときに、やっぱり地域の行政区分が一つのネックになってるんだと指摘されました。
本当は山の生物多様性を考えるなら、その山麓周辺はもちろん、その山麓から流れている川から海にいたるまで全部つながっているので、包括的に考える必要がある。要するに、自然はどこまでもつながっているので、何県だからここまでだという理屈は本来なら通らないという話です。
こうした面もブレークスルーしていくようなイノベーションのあり方だったり、地域創生のあり方だったりを探る必要があると感じます。
小西:まさにおっしゃる通りで、今の都道府県という自治体の行政区分は、明治以降につくられていて、文化的なものはあんまり継承してないところがあります。むしろまだ江戸時代の藩のほうが、ある種の文化的な固有性のようなものがあったと思います。
地域性というブランディングを考えたときにも、やっぱり自治体を超えて広域でやらないと、なかなかブランドをつくれないなとは思いますね。
小林:そうですよね。そこにヒントがあるような気がします。
「フグ」×「獺祭」で生まれる新たな価値
小西:今いくつかの地域の漁港で、生産者さんと一緒に活動しているんですけど、その中の事例としてご紹介したいのが、山口県のフグの生産者の方が取り組んでいる、養殖のトラフグのブランド化です。

何がユニークかと言うと、「獺祭」という日本酒がありますが、その製造元である旭酒造さのご協力で、今までは廃棄されてきた獺祭の酒かす(焼酎かす)を餌にして、フグを育てているんです。
このリユースにはいろんな意義があって、地域の資源循環の面もありますし、実は栄養源としても優れているんです。酒かすって「かす」という言葉を使いますけど、実はものすごく栄養があって、酒かすを加工した商品も出ていたりしますよね。
それを使いながら、山口県がフグの名産地であるという地域性も含め、養殖ならではの取り組みとして地産ブランドをつくっていこうと、今いろんなマーケティングのお手伝いをさせていただいております。
小林:まさにこれはサーキュラーエコノミーですね。
小西:フグの餌はキビナゴなどの稚魚を使っていることも多いんですが、それを酒かす中心に変えること自体、サステナブルな側面があります。
しかも、これがめちゃくちゃ美味しいんですよ。この漁師さんはもともとエンジニアをやられていて、家業を継いで漁師さんになったんですけど、いろんなデータを取って、常に養殖を改良していっているんです。たとえば、そのかすを与えることで、データ分析でもうまみ成分が1.5倍くらい上がって、歯ごたえも非常に良くなる。フグ刺しは、歯ごたえが旨味の重要なポイントなので、すごく商品力が上がっていっているんです。
小林:こういう時代だから、もうデータドリブンですね、お魚も。
小西:お客さんの視点で価値を考えたときには、魚の品質は重要ながらなかなか見えにくいところなんですが、お酒とのペアリングはわかりやすいので提案しやすいんですよね、そのフグの品質はわからなくても、獺祭と合わせて美味しいと言われると、食べてみたいと思うじゃないですか。
小林:裏側にストーリーもありますもんね。
小西:はい。いろいろな面でブランド化しやすい取り組みで、うまくいっています。
小林:僕もお話を聞いていて、獺祭をすっごく飲みたくなりました笑。
小西:ぜひ試食会に来てください(笑)。去年は、生産者である山口県の養殖場と、獺祭さんの製造現場を巡る漁業ツーリズムみたいなこともさせていただきました。ご参加いただいた方の満足度も、非常に高かったです。
やっぱり獺祭のように象徴的なブランドがあると、やりやすいんですよね。どうしてもサーキュラー的な取り組みは、地味になりがちじゃないですか。そこを高付加価値化していくっていう意味で、改めてブランドの力は大事だなと感じます。
ブランド価値というのを見たときに、特に食に関してはナショナルブランドの時代はちょっと終わってきているなという実感があるんです。要は大量生産をして、マスメディア、マス流通でブランド作ってくるという20世紀的なブランドの作り方っていうのは、もうちょっと終わってきているなと。
もっとリアルな価値が求められていて、その一つはやっぱり地域性だと思うんですよね。土地や自然環境、あるいは文化、コミュニティー、そういうものと紐づいた価値は、消費する意味、モノを買う意味につながってくると思います。ビールも、今は地ビールばっかりになってますよね。
私は「リ・ローカライズ」という言い方をしてるんですが、新しい意味での「地場」の価値が、実はこれからどんどん主流になっていくんじゃないかっていうふうに思います。
小林:本当にそう思います。世界中、いろんな国際空港を経由して旅していても、同じブランドショップが入っているじゃないですか。なんでわざわざ海外まで旅して、東京で買えるものをここで買わなきゃいけないのかなと思います。タックスが安いというような価値しかない。
逆に、イタリアに行ったときに地場のレストランが入っていて、ちょっと違うなと感じたんですよね。そういう空港のほうが、これからは流行るような気がしました。
小西:あと、これはリテール全般の話ですけど、EC中心になってくることで、リアルの店舗の価値が問われてきていますよね。そこへの回答の一つは、やっぱり新しい「地場」性だと思うんです。その土地の拠点になっていたり、コミュニティハブになっていたりということが、リアル・リテールのこれからの価値になっていくと思います。
未発掘のイノベーションのタネが地方には眠っている
小林:以前、電通にいらっしゃったときは、大企業のクライアントを中心にやられてきたと思いますが、そこから漁業ブの活動をされるなかで、小西さん自身の実感として大きく何が違いましたか。
小西:地方には豊かな文化や自然、人も含めて本当にいろいろな資源があって、かつ社会課題の宝庫、と言ったら語弊があるかもしれませんが、本当に課題がそこら中に転がっているんですよね。
小林:そうですよね。「犬も歩けば棒に当たる」じゃないですけど、町を歩けば社会課題に突き当たるみたいな。
小西:こんなチャンスはないと思いましたね。大企業だと、どうしても大きなマーケットでビジネスをしないと成長できないといった論理が付いて回ります。一方で、スモールビジネスは、むしろ競合のいないところ、誰もやってないところを狙って、ブルーオーシャンを探すことができる。
冗談抜きで、漁業はあらゆるところでブルーオーシャンなんですよ。人がいないけど、誰かがやってくれたらという仕事がたくさんあるので。そういう意味で、地域にはものすごいチャンスがあるし、実はまだ日本には眠っている資源があって、活用できる道があるんだということを行くたびに発見します。
小林:もうまったく同感で、僕も林業の視察などで、いろんな地方の現場にも行くんですけど、まだイノベーションという言葉以前の課題があって、すごくアイデアも出てくる一方で、産業構造自体が自分だけではどうしようもないようなところがある。政策の話から、あるいは地球環境の話からというのも含めて、本当に山積しています。
それでも、そうした状況をもう少し認知してもらって、「そこを解決しよう」という人たちが集まってくるとだいぶ変わってくるんじゃないかなと思いますし、そういう世の中にコロナ禍を経て、突入してるようにも思います。昔よりも地方にイノベーターの人たちが増えたなとは感じていて、僕は今あちこちで、東京よりも地方のほうが面白いと言っているんですよ。
小西:そうですね。いろいろな壁は確かにあって、そもそも現実として、移住するのはなかなか難しいじゃないですか。私自身も、地方の仕事をやるならその地に納税したいと思っていながら、移住はできていないので、本当は住民票を2つ持てるといいなと思うんですが……。
小林:ああ、その発想はなかったですね。
小西:それは戸籍制度とか昔からのシステムの問題もあって、なかなか変わりにくいものなんですが、ただ法人であれば、会社や支社を地域につくったりすることで納税できるんですよね。だから、日本の企業が地域にたくさん会社をつくると、もっと地域でお金が回ると思うんですよ。
今までは工場や営業所みたいに、ある種の搾取の構造というか、人がいなくなると撤退していくというやり方しかやってなかったんだけど、「社会課題解決という価値を生み出す場」としての観点で、新しい地方との協業の仕方を多拠点も含めて考えていらっしゃる方は最近すごく増えているとは思います。
地方創生の文脈で「関係人口」という言葉が長く使われてきて、正直、移住促進を諦めてきているなかで出てきた言葉だと思うんですけど、もっとポジティブな多拠点のような形を含めて、いろんな形で人が移動することで価値が生まれるっていうのがあると思います。自治体も、もうちょっと多拠点移動人口の誘引にシフトしていってもいいんじゃないかなというのは正直ありますね。
小林:それは本当にそう思います。アメリカのネバダ州で開かれるバーニングマンという巨大なイベントが、誰もいないところに何万人も世界から人が来て、その夏だけで1年間ぶん、その近くの村が潤うような経済価値を生んでいるように、観光以外で、移住者がいなくてもどうやって活性化させるかという考え方も、ありなんじゃないかなとは思います。

小西:観光だけでなく、もっと地域共創や社会課題解決など、目的ベースで地域と関わるっていうのは、漁業もそうですし、あるかなと思っています。
どうしても、やっぱり現場に行かないとわからないことって多いんですよね。私はもともと漁業の知識がなかったんですが、勉強しながら漁師さんの話を聞いたりしているうちに、驚くようなことを知ったり、そこにビジネスチャンスを見つけたり、そういう体験をたくさんしていっています。
小林:頭の知識だったり、ネットで検索するとか、最近だとChat GPTに質問するとかだけじゃなくて、足を運ばないと情報化されていないことも多いですよね。要はデジタルになっていない情報というのは、たくさんあるなというのはありますよね。
小西:最近だとフードテックがすごく盛んですけど、漁業の場合でも、最近水産IoTとか、ゲノム編集とか、いろんな領域での技術開発や事業化が進んでいます。ただし、シーズ(※新規開発のために企業が持つ技術などの要素)主導で生産者の実態や顧客ニーズに合っていないものも多かったりします。
また、意外と発掘されていないニーズというのがあったりします。たとえば、うちのメンバーが富山の魚をタイやベトナムにブロックチェーンの技術を使って運んで、向こうでプロモーションするという仕事をした際に、魚も好評だったんですけど、それ以上に特殊保冷箱という技術に関心が集まったんです。いわゆるコールドチェーンの温度帯で5日ぐらい電気なしで保管できるような保冷技術があるんですよ。
日本では当たり前になっているんですが、向こうに行くとコールドチェーン自体がないわけですよ。冷蔵輸送自体が普及していないから、港で獲ったものが都市まで運ばれたら、みんな腐っていっちゃったりとか、劣化してしまう状況があるんです。そういうことは現場に出て行って初めて気づくことで、意外な発見でした。「小西さん、保冷箱をつくりませんか」と漁協の方に言われました。
小林:それは思いもよらない新しいビジネスですね。
小西:これは一つの例なんですけど、やっぱり本当にニーズというのは、現場に行かないとわからないんだなと、あらためて感じました。
小林:それは逆に、企業にとってはチャンスが見つかるということですよね。
〈第3回につづく〉
※水産ビジネスは世界的な成長産業! 知られざる漁業の課題と可能性【小西圭介対談1/3】
※真の「パーパス経営」とは何か? ガバナンス目的を超えた意義【小西圭介対談3/3】
小西圭介(こにし・けいすけ)
株式会社ニュースケイプ 代表取締役
東京大学教養学部卒業後、1993年に株式会社電通に入社。20年以上にわたって同社のブランディング・サービスをリードし、業界リーダー企業から、D2C・スタートアップなど100社を超えるクライアント、地域や自治体との取り組みでビジネス成長を加速するブランドづくりの経験を積む。
デービッド・A・アーカー(UC Berkeley Haas School名誉教授)が副会長を務める米国プロフェット社(SF)に出向した際には、数多くのグローバルブランド企業の戦略コンサルティングに従事。日本唯一の直弟子として、同氏とともに日本企業に経営戦略課題としての「ブランド」を浸透させてきた。
近年はブランド・アクティビストとして、ビジネスが環境や地域・人やコミュニティの社会変化の主導的な役割を果たす、新しい共創型のブランド戦略モデルを提唱・実践している。著書に『ソーシャル時代のブランドコミュニティ戦略』(ダイヤモンド社)などがある。
小林弘人(こばやし・ひろと)
株式会社インフォバーン代表取締役会長(CVO)
1965年長野県生まれ。『WIRED(日本版)』を1994年に創刊し、編集長を務める。1998年より企業のデジタル・コミュニケーションを支援する会社インフォバーンを起業。「ギズモード・ジャパン」など、紙とウェブの両分野で多くの媒体を創刊するとともに、コンテンツ・マーケティング、オウンドメディアの先駆として活動。
2012年より、日本におけるオープン・イノベーションの啓蒙を行い、現在は企業や自治体のDXやイノベーション推進支援を行う。2016年には、ベルリンのテック・カンファレンス「Tech Open Air(TOA)」の日本公式パートナーとなり、企業内起業家をネットワークし、ベルリンの視察プログラムを企画、実施している。
著書に『AFTER GAFA 分散化する世界の未来地図』(KADOKAWA)、『メディア化する企業はなぜ強いのか?』(技術評論社)など多数。
※株式会社ライトパブリシティ社長・杉山恒太郎さんとの対談記事はこちら
※一般社団法人みつめる旅代表理事・鈴木円香さんとの対談記事はこちら