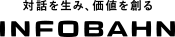「ユーザーの消費」を促すのではなく、「受け手の心」を変えよう!【杉山恒太郎対談3/3】


※読みやすさを考慮し、発言の内容を編集しております。
********************
黒子であり、表現者でもある幸福なポジション
小林弘人(以下、小林):『広告の仕事』という本は、「杉山恒太郎史」にもなっているというか、ある種の集大成となるような本でもありますよね。これまで広告業界のレジェンドとして、「ピッカピカの一年生」(※1)とか、「セブン-イレブンいい気分」とか、誰もが知っているような広告のクリエイターとしての杉山恒太郎さんの仕事術、制作の秘密も語られています。
杉山恒太郎(以下、杉山):本当は隠したかったんだけどね。担当編集者に全部暴かれました(笑)。
小林:暴かれてますね。この本を読んで僕がビックリしたのは、杉山さんはお名前を隠されながら、広告の仕事をされていたことです。あまりに売れっ子すぎて。
杉山:もうね。自分で言うのもなんだけど、実際に売れっ子だったんですよ。本当にたいへんな時期が何年かあって。
小林:もう言っちゃっても大丈夫なんですよね。まあ、書かれてますけど(笑)。
杉山:そのころ、ライトパブリシティに入る前に勤めていた電通には、怖い人がたくさんいたんだよ。「お前はもう名前なんかいいよな」って言われて。
それで僕も、本当にいいって思っていたの。広告の仕事って、表現者でいながら匿名でいられるというのが、実は幸せなポジションなんだよね。業界の中ではある程度名前が売れないと、良い仕事が来ないということもあるかもしれないし、もちろん責任がないというわけじゃないんだけど、一般的に言えば広告制作って黒子の仕事なので。
黒子でありつつ、表現者でもある。表現者でありながら、匿名でいられる。それは実は、とても幸せで自由なんですよ。そう思っていたから、「お前はもう名前なんか出なくていいよな」って言われたら、「はい、別にいいですよ」って言って。
小林:そうするとペンネームを使われていたんですか? ペンネームというか、広告ネーム?
杉山:いや、そういう名前もなくて、ほぼ名前を出さなかった。
小林:出されていないときの作品で、僕が知っているものもたくさんありましたよ。初めて杉山さんの仕事であると知ったけど、「これ見た、これも見た」って。詳しいことは、この本を読んでいただければ、具体的に載っています。
杉山:何もやましいことは一切していませんから(笑)。けど、それよりも純粋に「つくりたい」という気持ちのほうが大きかったので、あまり気にしていませんでした。
―――――――――――
※1 ピッカピカの一年生
小学館の学習雑誌『小学一年生』のCM。子どもの素朴な姿を捉えた映像と印象的な歌で世間に浸透する。1978年放送から長く愛され、令和に入り復活。
ビデオ撮影という「パンク」が、「ピッカピカの一年生」を生んだ

小林:広告の仕事ということでいうと、これまでにも表現手段として、80年代にはたくさん素晴らしいもの、それこそアート作品のような広告が出てきました。また90年代から21世紀にかけて、デジタル技術も入ってかなり変わってきています。
ただ最近だと、僕らみたいにWeb制作をやっていると、どれだけPVを稼ぐか、どれだけリンクで誘導させるか、どれだけユーザーを囲い込むかとか、数字が先に来ちゃいがちで、ユーザーの態度変容に求めているものが、すごく短期的になりがちなんですね。
瞬間的な、刹那的な行動変容ですよね。だから、心理的な態度変容とはまた違うところが、主流になってきていますが、そういうことも含めて、お話を聞かせてほしいです。
杉山:そこは、とても個人では世間を変えにくいところなんですよね。
小林:だけど、僕はこの本で書かれている、杉山さんのお仕事である「ピッカピカの一年生」も、「セブン-イレブンいい気分」も、世の中にいる受け手のフィーリングを変えたということについて、すごくそうだなと思ったんですね。「フィーリングを変える」ということは認知を変えることであり、ひとつの長期にわたるマインドのリセットというか、態度変容につながることじゃないかと思いました。
杉山:そうだな~。「ピッカピカ」のときは対象が、4月に小学校に入学する子どもたちで。ワクワクドキドキした子供たちの表情を日本中を回って撮ったので、素朴な可愛らしい子が出てくるコマーシャルということになるんだけど。そのとき、僕はまだ20代だからね。
よく「お若いのに、お子様がお好きなんですね」って言われたけど、正直なところ、子どもは大嫌いだったんだよね(笑)。あんなわけのわからないもの、うちには要らないって。今はちゃんと娘が二人いるんですけど、そのときはね。
小林:つくられたときは、まだ独身で、お子さんはいらっしゃらなかった?
杉山:そうですね。……というか、スタッフ全員、子どもがいなかった(笑)。
小林:それはすごいですね。
杉山:だってさ、違うんだよ。子どもが撮りたかったんじゃなくて、ビデオを使いたかったの。あれは日本で初めて、電気的な映像、ビデオを使った初めての広告なんですよ。
小林:ビデオというのは、手持ちのビデオ? 市販品の?
杉山:手持ちというか、それまではフィルムだったから。
小林:あー、まだフィルムが主流の時代に。
杉山:主流も主流。まだそれ以外は一本もない。テレビ番組では使っていたけど、コマーシャルでは使ってなかったんだよ。番宣みたいなものには、ビデオも使っていたかもしれないけど、いわゆる広告としてはまだビデオは使ってなかったんだよ。
僕が電通に入ったころって、化粧品だ、ファッションだ、車だって、それぞれの分野にスターがいたわけ。みんな格好良くてさ。
それで、アメリカではビデオという安くつくれる映像が始まったと聞いても、みんな苦々しく思っちゃって、あんなアートから離れた、ギラギラした、奥行きのない、深度のないものなんて、俺たちにはとんでもないよ、安くつくれるなんて質が悪いだけだと。まあ、ビデオというのはある種の制作における価格破壊だったんだよね。すごく毛嫌いしていた。
でも、僕はビデオの映像というのが、それこそジャーナリスティックに感じられて、まるで生中継のように広告が制作できたら、面白いだろうなっていうことを薄々気づいていたの。だから、これを誰よりも早くやりたくて、題材自体はなんでもいいと思っていた。
そこに、たまたま小学館の仕事が来たんだ。『小学一年生』という学習雑誌の広告で、当時の学習雑誌って、小学一年生が買うと、二年生、三年生って続いて、六年生まで買ってもらえるから、最初の『小学一年生』がものすごく大事なんだよ。しかも、学研という超ライバルがいた。
それで、「そうだ、ここでビデオを使える」と閃いてね。なぜなら、やっぱり化粧品とか、飲料とか、車とかを扱うような巨大な企業ではないじゃない、出版社は。まあ、出版社の中では講談社とか小学館とかは、大きな会社かもしれないけど。
小林:産業規模としては、出版業界は小さいですからね。
杉山:だから、いくら大事なキャンペーンでも、お金を使うという、その使い方が全然違うわけ。そこで、僕は日本人の子どもたちの映像が、まるで生中継のように飛んでくる、そういうモノをつくりたいって言って。もしフィルムだったら、絶対に可能性のない予算なんだよ。ところが、最先端のビデオというテクノロジーが生まれたおかげで、僕のやりたいことができるようになったわけ。まさに手持ちに近い映像として。
小林:まるでパンクですね。スリーコードと勢いだけで勝負するという感覚。
杉山:これはチャンスだと思ってさ。お金はないけど、これだったら日本中を回れる。「ピカピカの一年生」は最終的にはかわいい素朴な表現として生まれたけど、どういう広告かと聞かれたら、日本で初めて「ビデオという先端テクノロジーを使った広告」なんだよ。
「ピッカピッカの~一年生~♪」という歌も、当時コマーシャルソングはたくさん流れていて、いくらでも僕は歌えるんだけど(笑)。そこには専門の作曲家と、コマーシャルソング専門の歌い手がいた。それも壊したかったから、絶対にそうじゃない人たちにお願いして。
小林:いわゆるエキスパートに頼むんじゃなくて。
杉山:じゃなくてね。それで、ザ・ハプニングス・フォーという忌野清志郎も憧れたバンドがあるんだけど、僕もどうしても一緒に仕事をしたいと思っていて。それで依頼して、実はザ・ハプニングス・フォーがつくっているんだよ、あの「ピッカピッカの~一年生~♪」って曲は。それも掟破りだね。
だから、あらゆるものが実験、実験、実験でつくられているんだよ。
小林:めっちゃパンクだったんですね。いまのイメージだと、ほのぼのして可愛らしい感じですけど、制作の裏側はパンク。当時、今までやっていたベテランの人たちが、「こんなのは使えねーよ」と怒るような、クオリティのある種のローファイさ。そこを逆手にとった勝負だったんですね。
杉山:いわゆるドレスダウンだよね。どうやってドレスダウンするかという勝負。
僕はまだ経験が浅くて、フィルム制作もそんなにやっていなかった。フィルム制作というのは、現像というブラックボックスがあるから、やっぱり経験とそれによる技術が必要なのね。その点、ビデオって、親が子どもの運動会を撮るようになったように、それほど経験とか技術とかが必要ないものじゃない。逆に言うと、僕もビデオでしか映像の力を発揮できなかった。
その後、サントリーの「ランボー」(※2)とかをつくりだすころには、いっぱしにフィルムも覚えて、そのころの作品はすべて35mmフィルムでつくっているんですけど。当時の僕には、それが精いっぱいでもあった。だから、当時のスターになっている先輩たちに対するカウンターカルチャーなの。
―――――――――――
※2 サントリーの「ランボー」
サントリー・ウイスキー「ローヤル」のCM。フランスの詩人・ランボーをモチーフにした静的かつアーティステックな映像で、大きなインパクトを与えた。
変化は怖くない、変化しないことが怖い

小林:いまの若い人たちが杉山さんのお仕事から学べることは、ちょっと強引ですけど、「いま現在流行っているものじゃなく、そのカウンターをぶつけてみろ!」というところですかね。いまできる新しい要素をうまく組み合わせて、メジャーにしてしまうような態度というか。
杉山:そうだね、でも、僕はずっと同じ場所にはいないからね。
小林:それもまたひとつ、杉山さんのすごさですね。
杉山:若い子よりも、僕のほうが変わり身が早かったりする。というか、世代的なものだと思うんだけど、むしろ変わっていかないと怖くなる。変わることは怖くないんだけど、変わらないことが怖い。
小林:なるほど、その気持ちはわかります。
杉山:そういう世代なんだろうね。
小林:逆に、変わったり、人と違ったりすることを怖がる若い人が増えてきた感じがしますね。
杉山:そんな気がする。それは仕方ないことかもしれない。
小林:そんななかで、先ほどPVの話を出しましたけど、先に数字ありき、KPIありきという話ですね。KPIを達成しなかったからダメだというような仕事の受け方、やり方に対して、幻滅してしまっている人たちもいる気がするんです。もちろん、数字というのは大切な尺度ですけど、これからの広告としては、どういうふうになっていきますかね。
杉山:KPI、KPIと言ってくる人はたくさんいるじゃん。もちろん目標だから、その視点も大事だと思うんだけど、僕はよく「ここは数字にしないほうが賢くないですか」とも言うね。
PanasonicとSONYで時価総額がかなり開いたじゃない。じゃあ、SONYが何をしたかという社長だった平井一夫さんの話を読んだことがあるんだけど、SONYには生意気な人がたくさん集まるから、自分は現場のことは現場に任せておいた、と。
でも、二つだけ厳命したことがあって、一つは「規模を追うな、違いを追え」ということを言い続けた。もう一つは「KPIに数字をつけるな」と言ったんだ、と。KPIに数字をつけると、その数字が独り歩きして、ただ数字達成のために動くようになっちゃうじゃない。
小林:なっちゃいますね。
杉山:でも、KPIって本来は違うじゃん。本当は何かを大きく変えるために、ある大きな目標数字をつくるもの。
僕の仕事としてわりといまは、単品の広告よりも企業のブランディングの仕事が多いんですよ。リフレーミングというか。それで、人気企業に対しては、売上数値的なことではなく、「あなたの会社はこんなに立派な会社なのに、人気企業ランキングではこんなに低いところにいますよ。せめて50位に入りましょうよ」とか、あるいは「数字以外のKPIをつくりましょう」と言ったりしますね。
小林:すごく面白いなと思うのは、時価総額として、世界で初めて3兆円を突破したのがAppleだったじゃないですか。でも、生前に僕もインタビューをしたことがあるんですが、スティーブ・ジョブズのやり方は、数字を追うのとはすごく違うんですよね。めちゃくちゃdifferentなことをやって、ブレイクスルーを果たしている。
杉山:「Think Different」なんだよね。
小林:まさにです。数字を追って、この金額を達成して、この市場規模を狙おう、とやっていたんじゃなくて、「宇宙をへこませる」というレベルで考えてやっていたんですよね。それで結果的に数字がついてきたわけで。
そういう事例があるにもかかわらず、いまだにみんな「KPIだ」「この数字を狙おうぜ」と言い続けている。Appleのことは他次元で起きた、凡人には再現性の低い話だと思って無視しているのか(笑)。それよりも先に、パーパスだったり、志だったり、どういう衝撃を与えるかっていうのが、すごく重要で。
杉山:そうですよね。やっぱり、Appleは良いことをたくさん言っているよね。まず、あそこは調査しない、マーケティングをしないって決めているじゃない。なぜかというと、顧客は自分が欲しいものがわかっていないからだ、と。欲しいものをつくったうえで、「これでしょう、あなたが欲しいものは」と提示する商売なんだから。と。その通りだと思うね。
形式知と暗黙知の話は本にも書いたけど、暗黙知としては、人間の欲望の80%くらいは自分自身でもわかっていないと言われるでしょう。
小林:小説とか映画とか、特にそう思いませんか。「あなたが読みたかった/観たかったのはこれでしょう」という提示の仕方ですもんね。
杉山:うん。そこにヒントがあるんじゃないかな。
小林:いまはAIで、Web記事のタイトルを考えてくれるものがあるんですよ。このタイトルを付けたら、何%PV数が向上するかを数字で出してくれる。でも、僕はそれは思考停止に与することになると思っています。
実際に聞かれたことがあるんです。ある日、Webアナリストから、突然、数字がスパイク(※急激な上昇)したけど、理由がわからない。「小林さんならわかりますか、見てください」と頼まれて。
いざ見たら、すぐにわかることで、要するにコピーを付ける観点がガラッと変わっていたんですよ。今までやってきたタイトルのつけ方のパターンから逸脱したんですね。それによって、数字がスパイクした。
むしろ、なんで本読みならすぐに気がつくであろう、コピーライティングの視点が変わったという単純な事実がわからないんだろうと、けっこうビックリしました。AIが指示した通りにコピーを付けたら、次も安定したPV数が稼げるかもしれないけど、それ以上に行きたかったら、そこを越えないといけない。
そうしたことが、これから人間によるクリエイティビティに求められていくかもしれませんね。新しいというより、古き良きクリエイティビティですね。
********************
杉山恒太郎(すぎやま・こうたろう)
1948年東京都生まれ。立教大学卒業後、電通入社、クリエーティブ局配属。90年代にカンヌ国際広告祭国際審査員を3度務めたほか、英国「キャンペーン」誌で特集されるなど、海外でも知られたクリエイター。99年デジタル領域のリーダーとしてインターネット・ビジネスの確立に寄与。トラディショナル広告とインタラクティブ広告の両方を熟知した稀有なキャリアを持つ。電通取締役常務執行役員等を経て、2012年ライトパブリシティへ移籍、15年代表取締役社長に就任。主な作品に小学館「ピッカピカの一年生」、サントリーローヤル「ランボー」、AC公共広告機構「WATERMAN」など。国内外受賞多数。18年ACC第7回クリエイターズ殿堂入り、22年「全広連日本宣伝賞・山名賞」を受賞。
〈光文社HPの著者プロフィールより〉
小林弘人(こばやし・ひろと)
1965年長野県生まれ。1994年、『WIRED(日本版)』を創刊し、編集長を務める。1998年より企業のデジタル・コミュニケーションを支援する会社インフォバーンを起業。「ギズモード・ジャパン」など、紙とウェブの両分野で多くの媒体を創刊。コンテンツ・マーケティング、オウンドメディアの先駆として活動。2012年より、日本におけるオープン・イノベーションの啓蒙を行い、現在は企業や自治体のDX(デジタル・トランスフォーメーション)やイノベーション推進支援を行う。2016年には、ベルリンのテック・カンファレンスTOAの日本公式パートナーとなり、企業内起業家をネットワークし、ベルリンの視察プログラムを企画、実施している。著書に、『AFTER GAFA 分散化する世界の未来地図』(KADOKAWA)、『メディア化する企業はなぜ強いのか?』(技術評論社)など多数。