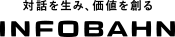伝説の広告クリエイター・杉山恒太郎へのQ&A【杉山恒太郎対談+α】


※読みやすさを考慮し、発言の内容を編集しております。
********************
Q)「プロ=対価を得る」というプロフェッショナリズムに対して
――「プロ=対価として報酬を受けるべき」というプロフェッショナリズムもあると思いますが、その観点についてはどう考えられますか。
杉山恒太郎(以下、杉山):プロとアマチュアリズムについては、『広告の仕事』(光文社新書)にも書いたんですが、「対価をもらうのがプロで、対価をもらえないのがアマチュア」というわけではないことを、かつてイギリスである方から教わったことがあるんです。
「君はアマチュアリズムというのは、プロになれない人のことだと思っているんじゃないの?」と聞かれて、「えっ、違うんですか?」と答えたら、「違うよ。アマチュアリズムというのは、“プロになりたくない人”のことを言うんだ」と。そこで「そうか!」と思ってからは、僕は「プロのアマチュア」になろうと思ったの。
「やっぱりプロの仕事をしないとね」とか、「プロは結果だよね」とか、やたらと「プロ」という言葉を使うでしょう。以前は僕も使っていたかもしれない。でも、それからいわゆる「プロ」と同じ実力を持ちながらも、“プロになんかなりたくない”という「アマチュアのプライド」も持っている人にならないと、「本物のプロ」にはなれないと思ってね。言葉にするとややこしいんだけど(笑)、それが僕のいまのところの答えかな。
小林弘人(以下、小林):「プロの罠」というものもありますよね。「自分はプロだ! だからこれを使わないといけない」とか、「プロなら、このレベルのクオリティじゃないと許されない!」とか。
杉山:対価をもらわないとプロじゃないということで、「無料じゃあ、仕事を受けないよ」とかね。
小林:それは自由ではないですよね。
杉山:めちゃ不自由。
小林:アマチュアというのは、そこの制限がない。自分自身で決めた何かを求めて、新たなところにも行けるところがある。その二つの心を、うまくバランスを取りながら持つのが大事ですね。
杉山:うまく言ってくれるね。今度からはそういうふうに言うよ(笑)。

Q)最近の面白い広告について
――最近見て、これは面白いなと思った広告事例が何かあれば、教えてください。
杉山:ちょうど去年の12月に『世界を変えたブランド広告』(日本経済新聞社)という本も出したんです。日経新聞の文化欄で連載した広告の傑作を紹介する記事から選定して、たっぷり加筆して出した本なので、詳しくはぜひそれを読んでいただきたいんですけど……。
そのなかでもいちばん刺激的だったのは、『The New York Times』の広告かな。そのキャンペーンは、ドキュメンタリーのようでありながら広告になっている。
『The New York Times』というのは地方紙で、もともとは70万~80万部の発行部数だったところから、積極的にデジタル化して購読者数が1000万人を狙えるところにきている。その成功の裏にあったキャンペーンで、テーマは「ポスト・トゥルース」なのね。
小林:トランプによる「フェイクニュース」という言葉が流行っているなかで、「真実とは何か」を問うキャンペーンですね。
杉山:いまは僕はそういうモノをやりたい。半分ドキュメンタリーが入るようなリアリティ。
昔は理想の物語を僕が考え、僕がつくり、それをみなさんに送って、「いいでしょう、これ。この世界を知ってください」ってやっていたんだけど、いまは自分たちが理想の物語をつくるよりも、みんなで一緒につくりたい。
要するに、いま求められている物語のつくり方自体が、ナラティブなものになっている。ナラティブ・コミュニケーションもストーリーテリングも、日本語に訳すと両方とも「物語」になるんだけど、ナラティブは自分自身がつくる物語。
小林:物語を伝えるのではなく、いわば「物語る」ですね。
杉山:そうですね。物語るというスタイルを取りながら、お互いに理想的な物語を、ブランドワールドをつくっていくという。だから、なるべくナラティブにしていきたいというのがある。
もちろん本音を言えば、昔のように理想の制作費をいただいて、35mmフィルムで贅沢な映像をたっぷり撮って、豪勢に音楽を使って……ということをやりたい気持ちは、いちつくり手としてないわけではないけど、さすがにもう無理だろうなというふうには思っている。
だったら、それに代わって、僕自身が達成感があってカタルシスも感じられるのは、『世界を変えたブランド広告』で紹介している中で言えば、『The New York Times』なんですね。
小林:ぜひみなさん、その本も買って読んでください。
Q) パートナー企業はクライアントの目標設定にどう関わるべきか?
――「数字ではない目標設定」というお話が出ましたが(※第3回記事を参照)、クライアントに対峙するパートナー企業としては、そこにどう参与すればよいでしょうか。
杉山:ライトパブリシティは広告制作会社と言われるけど、もともとはデザイン会社で、「あらゆるものにデザインを」という考えでやっているんですね。意外とみんな、広告の中にデザインがあると勘違いしているんだけど、デザインする対象の一つに広告があるんです。
いまのご質問に対して具体的に言うと、企業と付き合うときには、まず言葉をつくります。要するに、クライアント企業の価値の再定義を徹底的にやるんですね。よくコンサルタントは社史を徹底的に読むと言うんだけど、われわれもそうするの。社史を――人に読ませる前提でつくられていないので、つまらなかったりはするんだけど――ちゃんと読み切ると、創立者、「0→1」をやった人の想いやアイデア、熱い気持ちがちゃんと書いてある。だから、そこからいまの時代の価値へと再定義をして、ステートメントをつくるんですよ。
そのステートメントは、互いにかなり議論しながらつくります。ステートメントさえつくれれば、あとはそれにのっとって、こういう世界観がいいとか、この音楽がいいとか、判断があんまりぶれなくなるんだよね。
しかも、ステートメントというのは、お互いにシェイクハンドだからさ。向こうからしても、「こいつらはうちの根幹を理解しているな」ということになる。だから、徹底的にインタビューして、社史を読み込んで、そのうえで時間をかけてステートメントをつくる。それで初めて表現が来るんだよ。
小林:なるほど。クリエイティブの前の互いの認識合わせですね。助走のところ、実際にはその時点で構築は始まっていると思うんですけど、そこが重要なカギを握るというわけですよね。
杉山:いまはどうかわからないけど、欧米では昔は面談があったんだよね。だから、小林クリエイティブディレクター、杉山クリエイティブディレクターという者が、経営者に面談に行って、そこで彼らに自分自身のフィロソフィーを伝えて、それから会社のことを聞いていた。
これが実はいちばん合理的なんだよね。プレゼンさせて、表現を競わせて、コンペとして測るわけじゃなくて、「うちのことをいちばん理解しているのは、小林君という青年だな」とか、「彼の話を聞いたら、フィロソフィーも共感できる」とか、そういうことで決まっていた。だから、面談ってすごく重要だったんだよ。責任者がどういう人かわからないのに、クリエイティブを頼むのは怖いじゃない。
それに近い話で、われわれはステートメントをとにかくつくる。その柱をつくってから、クリエイティブやプレゼンに入る。
小林:どうしてもこの会社と仕事をしたいというときには、ラブレターを書いてもいいかもしれないですね。「貴社のステートメントはこれです」というラブレターを、相手に提案してみる。
杉山:そうすると、「うちのことをわかってくれている人がいるんだ」となるよね。そのときに難しいのは、できれば経営者、責任者とやり取りしたいところなんだけど、そうそうできないことだね。日本のサラリーマン社会は、上におもねって、おもねって、おもねっちゃうからさ。おもねりのデパートになっちゃうから。
小林:実際に忖度はすごいですからね。「上がこう言うんじゃないか」とかなんとかで、「それで君はどう思うんだ?」って言いたくなることは、ありますよね。

Q)コンサルティング・ファームによるエージェンシー買収について
――アクセンチュアによる「Droga5」の買収など、コンサルティング・ファームによるクリエイティブ・エージェンシーの買収の潮流がありますが、それについてどう評価されていますか?
杉山:いや~、それはもうめちゃくちゃ時代だな~と思っています。「Droga5」という会社をみなさん知っていますか? この10年で見て、おそらく世界最先端のクリエイティブ・エージェンシーですね。じゃあ、余談だけど、Droga5ってなんでこの名前か知っている?
小林:面白いんですよね、このネーミングの由来が。
杉山:創業者がシドニー出身の5人兄弟の末っ子で。子どもが5人もいると、お母さんがシャツでもなんでもたくさん洗濯しなきゃいけないじゃない。それで、誰の服かわからなくなるから、長男に1、次男に2って書いていて、彼は5って付けられていたから、そこからDroga5って名付けたらしいの。
小林:まるで「The Jackson 5」みたいな(笑)。
杉山:かわいい話だよね(笑)。そのDroga5は、さっき話した『The New York Times』のキャンペーンも制作していますね。
そうした優れた制作会社は、昔だったら絶対にWPPとか、日本で言えば電通とか、メガ・エージェンシーの傘下に入っていたじゃない。やっぱりさ、自分をどこに売るべきか考えたときに、コンサルティング・ファームに売るというのが、いまの時代を表しているし、裏を返すとアド・エージェンシー、メガ・エージェンシーの時代ではなくなったともいえる。時代の象徴だなとは思いますよね。
小林:一つのクリエイティブだけをお願いしたいというより、顧客との接点やブランドパーパスなどを含めた戦略の依頼になっているというところもありますよね。
杉山:昔は企業の宣伝部が強くてね。僕が若いころの宣伝部長といったら、鬼の宣伝部長として君臨していてさ。社長の参謀だったんだよね、宣伝部長って。
若い人には自慢話のように聞こえそうで申し訳ないけど、サントリーとかの宣伝部長に企画を出すと、「お前は本当にこれをやりたいのか?」と聞かれて、「やりたいです!」と言ったら、「わかった、撮影の準備をしておけ、おれは社長の説得をしてくるから」って。そういう時代もあったんだよ。
小林:まだ内容も決まっていないのに。
杉山:それはおとぎ話として(笑)、いま小林さんが言ったように、どんどん広告の役割が企業戦略そのものになってきているし、ちゃんと背景にパーパスを据えて伝えないといけなくなると、責任はどんどん上に行くんだよね。広告代理店の相手は、主に宣伝部だったでしょう。でも、コンサルティング・ファームはもっと上位と付き合っている。
そこでクリエイティブを決められちゃうとさ、広告代理店はどうすればいいのってなっちゃうじゃない。だから、Droga5のような超優秀なクリエイティブ・エージェンシーをコンサルが買収してしまうというのは、アド・エージェンシーにとっていちばん痛いところだよね。
ただ、結局は買収と言っても人と人の問題だから、そこでDroga5がいままでのように自由闊達にやれるかどうかというのは……。
小林:これから見守るところですね。
杉山:そう。買収したほうの器量、度量にかかっていると思いますね。それでも、この流れ自体は止められないと思います。
********************
杉山恒太郎(すぎやま・こうたろう)
1948年東京都生まれ。立教大学卒業後、電通入社、クリエーティブ局配属。90年代にカンヌ国際広告祭国際審査員を3度務めたほか、英国「キャンペーン」誌で特集されるなど、海外でも知られたクリエイター。99年デジタル領域のリーダーとしてインターネット・ビジネスの確立に寄与。トラディショナル広告とインタラクティブ広告の両方を熟知した稀有なキャリアを持つ。電通取締役常務執行役員等を経て、2012年ライトパブリシティへ移籍、15年代表取締役社長に就任。主な作品に小学館「ピッカピカの一年生」、サントリーローヤル「ランボー」、AC公共広告機構「WATERMAN」など。国内外受賞多数。18年ACC第7回クリエイターズ殿堂入り、22年「全広連日本宣伝賞・山名賞」を受賞。
〈光文社HPの著者プロフィールより〉
小林弘人(こばやし・ひろと)
1965年長野県生まれ。1994年、『WIRED(日本版)』を創刊し、編集長を務める。1998年より企業のデジタル・コミュニケーションを支援する会社インフォバーンを起業。「ギズモード・ジャパン」など、紙とウェブの両分野で多くの媒体を創刊。コンテンツ・マーケティング、オウンドメディアの先駆として活動。2012年より、日本におけるオープン・イノベーションの啓蒙を行い、現在は企業や自治体のDX(デジタル・トランスフォーメーション)やイノベーション推進支援を行う。2016年には、ベルリンのテック・カンファレンスTOAの日本公式パートナーとなり、企業内起業家をネットワークし、ベルリンの視察プログラムを企画、実施している。著書に、『AFTER GAFA 分散化する世界の未来地図』(KADOKAWA)、『メディア化する企業はなぜ強いのか?』(技術評論社)など多数。