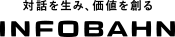「何をしたいか」を問うことから、お店のデザインも始まる【田中元子対談2/3】

2023年5月8日に、株式会社グランドレベル代表の田中元子(たなか・もとこ)さんをお招きして、弊社代表取締役会長(CVO)・小林弘人との対談を実施いたしました。
「どんなひとにも自由なくつろぎ」をコンセプトに、2018年にグランドレベルが開業したユニークな喫茶店「喫茶ランドリー」。まちに暮らす人々のコミュニティとなるべく運営されるこのランドリー付き喫茶店は、その理念が多くの方から共感を集め、志を共有する全国のさまざまな施設のデザインへと広がっています。
ただ、田中さんがそこで大事にしているのは、「合理性」や「オシャレさ」ではないとおっしゃります。コミュニティづくりにおいて最も大事な視点とはなんなのか。田中さんと小林が語り合いました(第2回/全3回、前回記事はこちら、第3回はこちら)。

表面的なオシャレさより大事な「デザインの意図」
小林弘人(以下、小林):「喫茶ランドリー」(※前回記事を参照)はいろんな媒体に取り上げられていて、視察が絶えないというお話もうかがっています。
田中元子(以下、田中):今でもよくいらしてくださっています。視察していただいて、お話しさせていただいて、交流できることは嬉しんですが、表面だけを見て、「オシャレでした」という感想で終わってしまうときは、意味がないのかなとも感じます。


小林:視察と言っても、何を見ていくかというところですよね。単純にその場所のルールだったり、雰囲気の良さだったりだけを知って、「こうやればいいんだ、簡単じゃん」としか感じないなら、そこは違いますよね。
そこには、田中さんが考えたデザインの意図だったり、メッセージがあると思うので、そこが伝わっていないまま、単にマネをして1階を開放的にするだけでは、やってもあんまり流行らないだろうなと思います。
田中:そうなんです。「オシャレな1階をつくって、まちを華やかにしましょう」ということが言いたいわけじゃない。そうしたお店がないよりはあったほうが当然いいです。けど、私がしたかったこと、伝えたかったことは、1階の表層を華やがせる、賑やかせるということだけじゃないんです。
本当の華やかさというのは、切って貼ってつくれるものじゃなくて、内側からにじみ出るもので、それはそこに人がいないときでさえ、その存在が心に浮かぶものです。
特にお店として運営している喫茶ランドリーは、活動するスタッフやお客さんが、そこでどんな体験をしているのかということが、存在感としての良さにすごく関わっています。シンプルにオシャレなお店をつくりたかったなら、「喫茶ランドリー」のようなデザインにはしなかったです。
小林:ある種の建築物としての作品性とか、店構えとしてのオシャレさではなく、そこでの体験が重要ということですよね。
田中:そうです。グランドレベルという会社を設立する前は、私はライターとして、建築関係の取材をすることが多かったのですが、そこで感じていたのは、「デザイン」というものが、狭い範囲で語られていたということでした。建築物としてきちんとしたものをつくる、洗練されたものをつくるということをベースに、デザインが語られてきた。けど、それって要するに「予想外ではないもの」ですよね。
デザインというものはもっと多様だと思っています。スーパーの広告チラシのデザインが洗練されていないのも一緒で、訴えたいことによって必要なデザインは変わるものです。「喫茶ランドリー」の場合も、他のプロジェクトでも、洗練させていくことより、人がリラックスしたり、ワクワクしたり、ここでこんなことをやったら楽しそうだと発想してくれたり、そういうことが起きやすいデザインは何かということを考え続けています。
パッチワークでは最良のデザインは見つからない
小林:ご著書を拝読しても思ったことですが、田中さんはそのためのディテールにかなりこだわってますよね。
田中:人の性格やそれによる行動のほとんどは、物理的な環境によって押し出されるものだと思っています。どういう環境に人がいるのかが、人の気持ちを大きく左右します。
たまたま行った場所で、たまたまその風景を目にして、その時、その瞬間、いろんなことを想うことが、その人をつくっていく。そういうことを意識して、ディテールのデザインを考えています。
小林:すごくわかります。僕はゴールデンウイーク中に、一人でバイクに乗って東京近郊に行ったんですよ。そうしたら古い建物をリノベした素敵なカフェを見かけたんです。最近、あちこちにそういったところは増えてますけど、これは見たことがないなと思って、そこに入ったんですよ。
それで、コーヒーも美味しかったし、ケーキも食べたらそれも美味しかったんですけど、そこでのコミュニケーションにガッカリしてしまって。もう全然、店員さんとコミュニケーションが成立しなくて、「『今日のおすすめ』ってありますけど、何ですか?」って聞いても、「ああ、そこに出てますよ」みたいな返事しかしてくれなくて……。
田中:あら、それは塩対応ですね。
小林:せっかくすごく良い雰囲気のお店で、外を眺める景色も素敵だったのに。しかも、客は僕一人しかいなかったので、もう少し僕はいろいろと対話したかったんですよ。それなのに全然、取り付く島もない。
田中:そういうお店、ありますよね。私はよく、「補助線のデザイン」という言い方をします。「ある存在があることで、何かやってみよう」と思ってくれるようなものをつくりたい。真っ白な画用紙だと手が動かないけど、そこに補助になる線や何かがあると、「あっ楽しそう」「私はこれをやろうかな」と動き出す。その補助線のデザインには、物理的な環境と、そこにあるサービスやソフト、そこで起きるコミュニケーション、3つを同時に設計・デザインしなくてはいけないと考えています。
塩対応の店員さんがやるなら、塩なデザインをしておけばいいんですよ(笑)。そういうことが大事なときもあります。たとえば洗練された高価なものに触れるときに、気さくな店員さんがラフに話しかけてくるのはおかしいし、アットホームなデザインにしておきながら、塩対応されたらお客さんは「何で?」となる。見たい/見せたい風景と、そこで起きる/起こすコミュニケーションとが、ちぐはぐなことが多すぎますよね。
デザインの世界は洗練させるとか、人懐っこいとか、一つの正しさがあるわけじゃないので、そのオーナーがお客さんに何を見てほしいのか、何で経済を回したいのか、そういう視点でデザインをチューニングしなくてはいけないと思っています。
小林:ちぐはぐなんですよね。先ほどのお店でも、まさにそれを感じたんですよ。
田中:よくわかります。たとえば、古民家の再生とか、古い感じへの改修をする店が増えていますが、経年変化を感じさせる空間って、本来なら人懐こさやリラックスできる空気を与えているはずなのに、店員さんが塩な対応を取ると、そこにギャップができて、いっそう寂しいものになってしいます。
小林:まあ向こうとしては、こんなオヤジが来たんで、早く帰れって感じだったのかもしれないですけど(笑)。
田中:いやいや(笑)。デザインもそうですが、私は正しさとか、これが絶対だとか、そういうものはほとんどないと思うんです。一方で、地球の裏側まで行っても、美しい花とか美しい夕日に、「オエーッ」って嗚咽する人間はいないですよね。つまり、人間には、誰もが持っている本能や感性があります。
だからこそ、どういう空間をつくる人でも、「こういう風景を見たい」「こういう稼ぎ方をしたい」ということと、「こういうデザインするんだ」「こういうコミュニケーションを取るんだ」ってことが、ちゃんとつながっていてほしいんです。
小林:そこが言語化できてないし、意識すらされていないのかもしれないですね。「デザイナーはあの〇〇さんにお願いしました」「コーヒーはここの豆をこういうローストで提供しています」とかって、みんなバラバラに考えていて、「どういう空間にしたいか」というトータルな視点が欠けている気がします。
田中:すごくパッチワーク的になってしまいがちですよね。そこはもっと問われなきゃいけないと思います。たとえば、エリアマネジメントやまちづくりでも同じで、どう生きていきたいのか、何を目指しているのか、という問いについてたくさん哲学していかないと、最良のデザイン、コミュニケーションのあり方なんてわからないはずなんです。
みんなが良いと言ってるもの、流行っているものが、自分たちのプロジェクトに合うとは限らないわけです。同じ機能でも、自分のやりたいことに向いてないかもしれない。自分に似合う服を探すのと同じで、ただ良いものに飛びつくんじゃなくて、そこは精査する必要があります。
無個性なまちを生む「経済的合理性」という罠
小林:これは僕が勝手に捉えているだけかもしれませんが、やっぱりヨーロッパのまちに行くと、「どう生きていきたいのか」「何を幸せと思うのか」という価値がにじみ出ている気がします。
明確にそこをつくるうえでのルールだってあるかもしれませんけど、ルールとは違う形で、それぞれが全体に醸しだすものがあるので、「あのまちにまた行きたいな」と感じさせるんですよね。
田中:私は宗教について疎いですが、他の多くの国は、その国の人たちみんなが同じものを信じられているな、それが日本より強いなと感じることがあります。それが宗教である必要はないんですが、幸せであること、よりよく生きることがどういうことかについて、普段から話し合ったり、共感し合ったりする土壌が、日本にももっとあったらいいなと思っています。
小林:僕は日本の場合は、極端に合理主義的すぎるのかなと思っています。たとえばターミナル駅を降りると、お決まりの本屋さん、お決まりのハンバーガーショップ、お決まりの服屋さんがあって、経済的にはそれが成功なのかもしれないんですけど、長期視点で見ると似た街が増えてしまうので、そのまちに行く必要がまったくないという。
田中:おっしゃる通りです。最近は特に「差別化したい」と言いながら、「とはいえ経済的に」と言って、家賃を確実に払ってくれそうなナショナルチェーンをどこでも入れてしまいます。結果、どこもローカル性が見えない、同じようなまちになってしまう。
まちをつくるのに、短期的にものを見がちだからでしょう。行政も担当者がすぐに変わったり、ビジネスの世界でも、「明日、明後日にこれを売って、いくら稼げるか」って話がされますが、まちに個性が生まれたり、愛着が育まれるためには、もっと長いスパンでものを見ることが必要です。
多くの方が頭ではわかっているのかもしれません。でも、いわゆる経済合理性というものから一歩身を引くとなると、誰がイチ抜けするかというところで……。
小林:イチ抜けられない。足抜けがなかなかできない。
田中:そうなんです。そのことよりも、誰かが良いと言っているか、今何が流行っているかに頼っちゃうんですよね。
「そのまちがどう好きなのか」という態度が問われている
小林:それでも、そうやって足抜けができないところに、ふわりと移住者がやって来て、しがらみがないぶん、ささっとやっちゃって、それが流行りだしちゃうという。そういう感じで、少しずつ良さが拡大していって、気づいたら「あ、このまちいいじゃん」となるようなことも、徐々に実際に起きているとは思うんですよね。
田中:そうですね。若い方やまちで何かをしたい方にとっては、地方都市のほうがすごく可能性があるとも言えます。東京より家賃も安いし、町会長とか市長さんとか、行政のキーマンにもすぐ会える。フットワークの軽さが違います。
しがらみの渦中にいる人は、なかなか自分の頭で考えにくくなっています。誰かが反対するから、風紀を乱すから、やれないという結論になりがちです。でも、外から来た人は、自分の頭で考えてることを主軸にして動きます。「僕にはこのまちがこう魅力的に見えるから、それを活かしたことをやります」と動いてガラッと状況を変えたりする。そういうことは、いろんな場面で必要になっていると思っています。
小林:本当にそうですね。地方創生に悩まれている方にお話をうかがうと、「自然が豊かだし、人もいいし、良いまちなんだよ」とおっしゃるんですけれど、どこも同じ方向に向かってしまうので、表面に見えるものが特別なものに見えないんです。むしろそのまちの奥深さというものを隠しちゃってる感じがするんですね。
田中:自然が豊かで空気や水がおいしくて、いい人がいるというのはその通りなんですけど、どこも同じなんですよね。そうではなく、本当に必要なものは、そのまちがその豊かさをどう扱っているかという態度だと思うんです。
小林:扱い方というか、表明というか、そこにある哲学ですよね。
田中:そうです。ここに海がある、山があるというだけじゃなくて、「ここが素敵でしょう」といって見せられるだけでも価値が変わる。そこには、「あっ、この人がこんなに大事にしてるものなんだ」「こういうところが好きなんだ」っていう想いが紐付くし、そのように扱われているというストーリーが付いてくる。さらに、そういう態度のあるまちだったら、見せ方や伝え方も自然と変わっていくのだと思います。
〈第3回につづく〉
※「想定外」こそを楽しむ。ランドリー付きの喫茶店で生まれるコミュニティ【田中元子対談1/3】
※「‟自由”を楽しむ強さ」を持とう!「マイパブリック」で表れる個性【田中元子対談3/3】
田中元子(たなか・もとこ)
株式会社グランドレベル代表取締役
1975年茨城県生まれ。2004年より建築関係のメディアづくりに従事。2010年よりワークショップ「けんちく体操」に参加。2016年「1階づくりはまちづくり」をモットーに、株式会社グランドレベルを設立。さまざまな施設や空間、まちづくりのコンサルティングやプロデュースを手がける。2018年「喫茶ランドリー」開業。2019年「JAPAN/TOKYO BENCH PROJECT」始動。主な著書に『マイパブリックとグランドレベル』(晶文社)、『建築家が建てた妻と娘のしあわせな家』(エクスナレッジ)ほか。主な受賞に「2018年度グッドデザイン特別賞 グッドフォーカス[地域社会デザイン]賞」、「2013年日本建築学会教育賞(教育貢献)」ほか。
小林弘人(こばやし・ひろと)
株式会社インフォバーン代表取締役会長(CVO)
1965年長野県生まれ。1994年に『WIRED(日本版)』を創刊し、編集長を務める。1998年より企業のデジタル・コミュニケーションを支援する会社インフォバーンを起業。「ギズモード・ジャパン」「ビジネス インサイダー ジャパン」など、紙とウェブの両分野で多くの媒体を創刊するとともに、コンテンツ・マーケティング、オウンドメディアの先駆として活動。2012年より日本におけるオープン・イノベーションの啓蒙を行い、現在は企業や自治体のDXやイノベーション推進支援を行う。2016年にはベルリンのテック・カンファレンス「Tech Open Air(TOA)」の日本公式パートナーとなり、企業内起業家をネットワークし、ベルリンの視察プログラムを企画、実施している。
著書に『AFTER GAFA 分散化する世界の未来地図』(KADOKAWA)、『メディア化する企業はなぜ強いのか?』(技術評論社)など多数。
※株式会社ライトパブリシティ社長・杉山恒太郎さんとの対談記事はこちら
※一般社団法人みつめる旅代表理事・鈴木円香さんとの対談記事はこちら
※株式会社ニュースケイプ代表・小西圭介さんとの対談記事はこちら