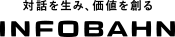テレビもラジオもオワコンじゃない!? 「番組」をブランド構成の一つと考える、トラディショナルメディアの捉え方【AWA2023レポ―ト】

2023年6月6日〜6月8日にかけて開催された「Advertising Week Asia 2023」。最終日の最後のセッションとなった「自らが演者となりトラディショナルメディアを使うその仕掛けとは?」の内容をお届けいたします。
グレートワークス取締役COO/貝印執行役員の鈴木曜さん、ディグラム・ラボ代表取締役の木原誠太郎さんが登壇され、当社社長である田中準也がお話をうかがいました。
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌。「4マス」とも言われたトラディショナルメディアの存在感が薄れていると指摘される時代に、鈴木さんはラジオ番組を、木原さんはテレビ番組に関わられ、ご自身で出演もされるなど、精力的に活用されています。
普段からデジタル領域でもご活躍されているお二人が、なぜ今ラジオ/テレビに力を入れられているのか? その戦略とメディア観に迫りました。
※読みやすさを考慮し、発言から内容を編集しております。
※出典明記のない掲載画像は、すべて運営事務局よりご提供いただいたセッション当日の写真です。
********************
番組スポンサーではなく、自ら演者となる関わり方

田中準也(以下、田中):「自ら演者となり、トラディショナルメディアを使う仕掛けとは」というテーマでお話いたします。まず自己紹介をしておきますと、本日の進行を務めますインフォバーンの田中と申します。どうぞよろしくお願いします。
鈴木曜(以下、鈴木):グレートワークスというスウェーデンのクリエイティブチームで、CCOをやっております。あと、貝印という刃物屋さんで、CMOとCCOをやっています。鈴木曜と言います、よろしくお願いいたします。
木原誠太郎(以下、木原):心理学と統計学で人間の性格をズバっと明らかにする自己分析ツール、ディグラム診断を運営してます、ディグラムラボ代表の木原誠太郎と申します。よろしくお願いします。
田中:それでは、本題に入りましょう。今日はラジオ番組のパーソナリティーを自らやっている鈴木曜さんと、TBSで自身のテレビ番組を持っている木原さんに、トラディショナルメディアになぜ自ら出演して、何を伝えようとしているのか、何を実行しようとしているのか。頭の中を少し紐解いていきたいなと思います。
まず曜さんは、どんな番組をやっているんでしょうか。
鈴木:TOKYO FMで毎週土曜の深夜2時から2時半まで、『AUGER Kiss our humanity 心に触れて“整える”時間』という番組をやっています。心を自分から整えるということを題材に、毎回ゲストを呼んでいます。そのパーソナリティと番組の企画・制作、ゲストのアサインまで。その辺りは最大限にコネクションを使っていて、お二人にも出ていただきましたね。

田中:出演させていただきました(※田中準也出演回の模様はこちら)。AUGERというのは、貝印の製品ブランドで、グルーミング(身だしなみ)・ツールですよね。
鈴木:AUGERは、グルーミング・アイテムを揃えたブランド名です。貝印というのは、ShickとかGILLETTEとかのカミソリ・ブランドの競合でもあるんですけど、基本的には、刃物を軸にしてブランド展開をしているんですね。医療用のメスもつくっているし、爪切りもつくっているというところで言うと、カミソリメーカーじゃないんです。
その貝印で新しいブランド、他の企業ではやらないブランドを展開しようというところで、立ち上げたグルーミング・ツールのブランドです。
田中:新ブランドの立ち上げとともに、このラジオ番組の企画もスタートしたんですか。
鈴木:そうです。いろんなメディアプランを立てたなかで、カルチャー寄りのこともしっかりとやっていこうと。若い方のグルーミングに対する関心が高くなっているなかで、そこを捉えていこうと、新たにラジオ番組を企画していたら、最終的に自分が出ることになったという流れです。
田中:はい、そのあたりをのちほど深く聞いていきたいと思います。木原さんはTBSの『スター★性格診断SHOW』を。これは深夜といっても、月曜日の23時台(※毎週月曜23:56~)ですね。

木原:そうです。裏だと、日本テレビの『月曜から夜ふかし』が放送されている時間帯のあとですね。ちょうどTBSの『news23』が終わったタイミングで始まる番組です。もともと10年ぐらい前からテレビには出ていまして、最初はフジテレビで加藤浩次さんがMCの『性格ミエル研究所』という番組をやっていました。
それからご縁があって、この4月から今度は麒麟の川島明さんと番組をさせてもらうことになったんです。簡単に言うと、僕自身がゲストの性格診断をする番組ですね。
田中:ディグラムラボ自体は、toBのビジネスですよね。
木原:toCとしても無料で公開はしています。ただ基本的なビジネスでいうと、ディグラムラボは、事業会社さんと一緒に診断コンテンツをつくったり、そこからデータの分析をやったり、「この性格の人はこういう化粧品を使うよね」といったサイコグラフィックベースのマーケティングをやったりしています。
何かtoCを意識したときに、性格診断自体をテーマに番組をつくっていこうという話になって、演出をしながら、自分で出役もやってるという形ですね。
田中:ただ出演するだけじゃなくて、自分で企画を考えて、台本を書いて、ゲスト全員の性格診断をされているわけですね。
「入場制限」のあるラジオ番組は、製品ブランドの一部
田中:ラジオやテレビというと、特に若い方のなかには、もう聴いてないよ、見てないよ、という方もいると思いますし、もちろん全数としては減っていますけど、まだまだ届く人には届いています。
そこで、なぜこのトラディショナルメディアを使っているのかをお二人に聞いていきたいと思います。事前にお二人と打ち合わせをしたときには、いくつかキーワードが出てきました。「VSにはしない」「文化をつくる」「入場制限」「制約」「ブランデッドコンテンツ」「普段会わない人とのコミュニケーション」「ビジネスや事業への還元」「最少人数で最大の効果」「やれることは全部やる」などなど。
少しかいつまんで「入場制限」というところを話すと、ラジオもテレビも制約条件がありますよね。たとえば、ネット上で記事コンテンツをつくろうと思ったら、2000文字でも1万文字でも書けるわけです。その点、ラジオもテレビも30分や1時間といった番組の尺がある。あるいはラジオは音だけとか、テレビにはオーディエンスとのインタラクティブ性がないとか。そうした制限について、「入場制限」という言い方をされていたんですけど、にもかかわらずなぜラジオを選んだのでしょうか?
鈴木:最初からラジオを使うことが目的だったわけではないんですけど、ブランドを立ち上げて広げていくには、やっぱりカロリーがかかるんですよね。いろんな方の力も必要とします。
今のデジタル時代には、YouTubeでみなさん情報を手に入れたり、自分の好きなコンテンツを選んだりするなかで、あえて誰でもつくれるわけではないメディアを自分で持つ、ブランドで持つということをすると、今まで出会わなかった方々が、その番組に出ることを通じて世界観の体現者になってくれるという。そういう立て付けをしたいなと思って、ラジオを。

田中:広告的な使い方ではない感じですよね。
鈴木:そうですね。どちらかというと、ブランドの立て付けの一部。それも商品と同じようにブランド構成の一翼を担うような形にしたかったんですよ。だから、ラジオで商品の宣伝もしてないですし、むしろあまりしたくないと思っています。あくまで世界観の一つなので、広告というより、その場所でブランド体験を展開しているようなイメージですね。
田中:その世界観をつくる、カルチャーをつくることで、ブランドを知ってもらうことにつながればいいと。出演者の方が知るということも重要ですよね。
鈴木:重要ですね。コミュニティ・マーケティングとまでは言わないですけど、ラジオは入場制限があるがゆえに、出演すること自体の価値は、まだあんまり変わっていないと思うんですよね。僕も、デジタルメディアに記事を書いていただくこともあるんですが、両親から電話が来るのは新聞に載ったとき、みたいなことです。結局、そういう意味での役割はあまり変わってないと思います。
新たな形のメディアが出てきて、そこにすごく力はあるけど、だからといってトラディショナルメディアの価値が薄れているわけではない。選んで使っていくべき、というふうに感じています。
田中:対立構造にする必要はないんじゃないか、と。
鈴木:そうです。それこそ今は、ソーシャルメディアとか、動画配信コンテンツとか、いろいろな手段を選べる時代の中で、それぞれのメディア特性がより際立つ戦術を使っていったほうがより高い価値を生めると思います。
社会の反応を知る「実験場」としてのテレビ番組
田中:木原さんの場合は「ディグラム」というサービス/プロダクトがありますが、それでも宣伝したり、流布したりするためにテレビ出演されているわけでもなさそうですよね。
木原:そうですね。流布するためにやっちゃったら、単なる広告になっちゃうので。そもそも「性格診断」というコンテンツをつくっているプレイヤー、それでビジネスをやっている人たちがほとんどいないので、まず楽しんでもらいたいと考えています。
SNSとかAIとか、そういう時代のトレンドのなかでも、「自分のことを知りたい」というニーズは絶対なくならないですし、それがわかるという楽しさを伝えたいんです。だから、裏ではむちゃくちゃデータを回しているんですけど、そのデータを回している姿は見せないで、エンタメとして出す。要するに、吉本の芸人さんだったり、グラビアアイドルの方だったり、一般人のメタファーとなる代表者に対して、それを当ててみた反応を見ているんです。
実はSNSで拡散することに関しては、僕らは強いんですよ。僕はもともとSNS時代のmixiにいたので、診断コンテンツの破壊力も知っていて、出すだけでもブワーッとすごく広がるんですよ。
逆に、テレビみたいな放送法があって、公的な管理下にあるところで何かやってみようとすると、よくよくしっかり考えないと伝わらないんですよね。どうすればそのキャズムを越えるのかを考えた結果、自分自身がエンタメに走って、出役としても100%以上伝えられるようにしたほうが、早いという判断をしました。だから、広告ではなく、自分が出役になるという判断をした感じですね。
田中:「やれることは全部やる」とおっしゃっていた意図は、そこにあるんですね。
木原:自分がやれることで目に前に来るものは、全部バッと取ります。

田中:会社の社長でもあり、サービスの責任者でもある自分が前に出ていく。それをあえてデジタルコンテンツではなくて、制約があるテレビで、というのは、チャレンジでもあり、そこをまた実験場にしている感じがします。
木原:そうですね。僕はそう思ってませんけど、テレビがオワコンと言われ始めてもう10年以上経ちますよね。みんな、デジタルでできることへのトライについては、めちゃくちゃ考えてるわけですよ。そのなかで逆に、僕らみたいなデジタルに強いコンテンツが、テレビに行ったら、どんな表現ができるかというチャレンジは、今だに誰もしていないんですよ。
ある意味で、これは社会調査の一つだと思っていて、社会に対して何かのメッセージを出すとか、できることを全部フルスイングでやりたいというときに、実際に影響力があって伝わりやすいのは、テレビのほうが伝わりやすいところがあると考えました。
その文脈に乗せてから、SNSはじめWebの文脈に乗せていく。僕は雑誌とか、どんな媒体の取材も受けるんですけど、やっぱりテレビ発のコンテンツというのは、まだ破壊力があるなというのが僕の感覚ですね。
「制約」の中で生まれるプロフェッショナルの力
田中:制約があるからこそ、ラジオもテレビも、コミュニティや文脈をつくりやすいのかもしれないですね。
鈴木:制作リソースが、その制約下でものを作るために成熟、発達しきっているというのもありますよね。ラジオって普通にしゃべるだけなので、ある意味では誰でもできることなんですけど、ラジオ局のスタジオに入って、プロの力を借りて番組収録することで、やはり伝わりやすいパッケージになるんですよ。
僕らがこれをうまく活用してものをつくるっていうときに、その力がすごく役に立っている気がしますね。
田中:トラディショナルメディアとプラットフォームの違いについても、お二人の考えをうかがいたいです。「生活者との距離感」「ストーリーによる世界観」とった話を、曜くんは事前にしていましたよね
鈴木:まあ365日、毎日、人間がオンラインに常時接続できる時代になっているなかで、そこにいたり、何かを起動したり、購入したりしないと、その世界観に触れられないという意味では、トラディショナルメディアはとても不自由なメディアなんですけど、その不自由さとプレイヤーの少なさが、需要と供給のところで特別なモノではあり続けている。YouTubeをはじめとするデジタルメディアもめちゃくちゃすごいんですけど、そことは生態系が違う気がして、だから共存していけると思いますね。
田中:共存なんですよね。だいぶVS構造という見方はなくなってきたと思うんですけど、今だにそういう捉え方をされることもあります。でもお二人と話していると、あらためてそれぞれの特徴を知ったうえで、両方使ったほうがいいなと思います。

ストーリーによる世界観というところでも、トラディショナルメディアには、その瞬間だけ没入させるという力が、まだあると思ってるんですよ。
木原さんの番組の収録を見させていただいたんですが、その現場を見ると、演者さんの反対側にいるスタッフの数がすごいんですよ。テレビには映らない本当に黒子なんですけど、スタッフ全員が同じ黒いTシャツを着て、タレントさんが入る前の隙間時間にお弁当をガッと食べられていて、入られたらピシッとなって。それは今どきはYouTubeの世界にもある景色かもしれませんが、番組をつくるというところにかける、職人の方々の本気というのは、またすごいものがあるなと感じました。それに、失敗しないじゃないですか。
木原:そうなんですよね。
田中:30分の番組をつくるという尺の中で、40分ぐらいしか時間をかけてない。それなのに、本当にみんな間違わない。テイクツーが一切ないくらいでした。しかも、僕が見学したのは、初回放送の収録だったんですよ。それでも失敗なしで、むしろアドリブがバンバン出ていました。
木原:テレビは演芸の世界なので、しゃべっているときにマイクで裏と会話ができるぐらい円熟していないと、演者として第一線は張れないと思うんですよ。表でしゃべりながら、裏の意図を察せないと、次は呼ばれないんですよね。
そうした芸の世界を感じられるのは、テレビが一番だと思います。そのなかで、僕の立ち位置は、どうあっても性格診断のプロなので、プロとして絶対に外さずに、その収録現場をいかに盛り上げるか、つまり視聴率を取るかなんですね。
熱量がこもったテロップが出るような面白いコメントというのは、台本には載ってないんですよ。そのときの空気を察して、一言パンッと発したものは、やっぱり数字に反映されるんですね。あのとき、フジモンさん(FUJIWARAの藤本敏史)が言ったボケは面白かったなと思ったら、ちゃんとそこで数字が跳ねていたりするわけです。そういった独特の制約下だからこそのクリエイティブが、やっぱりあるんですね。
田中:成熟しているメディアで、職人芸を磨いたプロフェッショナルなスタッフが阿吽の呼吸で制作しているところに、クリエイティブのグルーブみたいなものが生まれるんですかね。
木原:フロアディレクターさんがカメラの裏側にいて、よくハハッと笑うんですけど、実は笑っているときは面白くないときなんですよ。本当に面白い話には、無言になって頷くんです。盛り上げるために笑っているだけで、乾いた笑いなんですよね。それもまた一つの演芸で、このままではマズいと思って、みんな時間の中で違う球をどんどん投げてくるんですよ。時間の制約の中で、何ができるかを全力で考えているところが、テレビの面白いところですよね。

田中:最後に、この後の展開として、何か言える範囲で仕掛けとか、考えているところがあれば教えてください。
鈴木:僕のラジオにいろんな方々に出ていただいていて、しかも僕がブランドと親和性が高いと思った方、ブランドのコンテンツの一部になっていただきたい方を選定しているので、そういう方々をつなぐためのデジタルプラットフォームを、ラジオの裏側でつくろうかなと考えています。
表側は変わらずにやっていきますけど、裏側にそういう仕組みをちゃんと入れて、しっかりとコミュニティとして出演者の方にブランドのファンになっていただくとか、その後もブランドの後押しをしていただくための仕掛けは、何かつくっていきたいと思います。
木原:今もテレビの影響力はもちろんあるんですけど、やっぱり10年前よりはテレビって出やすくなったんですよ。昔はみんなテレビに出たがったので、むちゃくちゃ出づらかった。その障壁が下がったので、僕自身はもっとテレビの情報発信量を増やしていきたいと考えています。ちょっとずつビジネスも、そういう方向に舵を切っていこうかなと思っています。
田中:ちょっと失礼な言い方かもしれないですけど、実はお二人とも地道に活動されていますよね。ブランドの世界をつくる、文化をつくる、というのは、すごく地道な活動をする必要があるんだということを改めて感じたセッションでした。また機会があれば、この三人でお話ししたいと思います。今日はどうもありがとうございました。