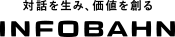価値を最大化するデザインの役割とは【「Design Dimension 2023 KYOTO」レポート】

地域における「デザイン経営」をテーマにしたカンファレンス「Design Dimension 2023 KYOTO」が、2023年11月11日に開催されました。
(参考URL:https://www.dxdimension.jp/2023-kyoto)
さまざまなデザイナー、経営者などが集い、デザインと経営についての議論が交わされるなかで、インフォバーン取締役副社長である井登友一が、パナソニック株式会社のデザイン本部長である木村博光氏、KESIKI Inc.のエグゼクティブ・ディレクターである井上裕太氏とともに登壇いたしました。そのセッション「価値を最大化するデザインの役割とは」の内容を記事としてお届けします。
「モノからコトへ」で本当に「モノ」の価値は失われているのか?
井上裕太(以下、井上):「デザインの価値」というテーマで、ピュアに、デザインそのもの価値というのはどういうことだっけというのを、まさに最前線でご活躍のお二人にお聞きするセッションでございます。最初は二人に自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
井登友一(以下、井登):株式会社インフォバーンでデザイン・ストラテジストをしています井登友一と申します。かれこれ四半世紀以上デザインの仕事をやっていますが、いわゆるノンデザイナー出身で、消費者リサーチをするリサーチャーとして仕事を始めたのが社会人としてのキャリアのスタートでした。そのなかでデザインリサーチに触れ、今は広くデザイン領域で企業を支援する仕事をしています。パナソニックさんにも長らくお世話になっています。
昨年、『サービスデザイン思考ーー「モノづくりから、コトづくりへ」をこえて』という本を書いたんですが、その執筆動機として、この10年くらいに感じるようになった課題感がありました。かつてはユーザーの利用状況、利用環境、利用文脈を、丁寧にリサーチしていって、機能やコンセプトを改良してアイデアを出せば、どんな製品であれサービスであれだいたい良くなっていました。ところが、今は同じように努力をしている企業がたくさんあるし、多くの製品・サービスがすでに良くなっている。すると、これまでのやり方では、わざわざ「この製品がほしい!」と選んでもらうのは難しくなっていきます。要するに、顧客中心デザインとか、顧客ニーズを理解して応えるといった視点は、依然として重要ではあるけれども、それだけだと行き詰り感が生まれているんです。
加えて、今は「モノからコトへ」と言われて久しいですよね。私はUXデザインの領域がメインなので、モノからコトへの「コト」の大事さはよく理解しているつもりです。一方で、製造業の方との仕事も多いので、そうした潮流に対する戸惑いの声もよくうかがいます。でも、「モノからコトへ」と語られるうちに、あたかもいつからか「モノ」に価値がなくなったような空気が生まれてしまっていますが、果たして本当にそうなのでしょうか。今日はそうした問題意識も含めて、話題をご提供できればと思っております。
井上:あらゆるビジネスがサービス化する世界において、モノとコトとの関係を結び直すということですね。それでは次は、木村さんに自己紹介をお願いします。
木村博光(以下、木村):はい、パナソニック株式会社のデザイン本部に所属しております木村と申します。プロダクトデザインを中心に、大きな流れとしては黒物家電から始まって白物家電へというのが私のデザイナーとしてのキャリアになります。最近では、パナソニックは「Make New」という変革のアクションワードを掲げていますが、先ほど井登さんがおっしゃっていたような課題に、われわれも悩んでいるところです。
われわれも「モノ」の再定義が必要だと感じていまして、ドライヤー、掃除機、食洗器のような従来からある「モノ」についても、今一度そのユーザー体験から見直して、リデザインしていっています。そのなかで先般、「LAMDASH PALM IN」というシェーバーが、グッドデザイン賞のファイナリストに選ばれました。
他にも、賃貸住宅にわれわれの家電をインストールする「noiful(ノイフル)」というサービスを展開したり、商業施設などの空調のソリューションビジネスに取り組んだり、どんどんスケールを広げて「まちづくり」の事業にも注力したりしています。パナソニックとしては一貫した一つの世界観をつくっていきたいということで、「360UX」と称して、単に商品をデザインして実装するだけではなく、あらゆるものを一貫した体験として提供することにトライしています。
とにかく私たちも、先ほど井登さんがおっしゃっていた通りで、今は自分たちの存在意義が問われているという認識でおります。製造業はずっと、家電をつくっていれば良かったんですけど、そうではなくもう一度、意味のある未来社会をちゃんと描いて、そこからバックキャストして現状とのギャップを明らかにし、「モノ」をより良くしていこうという発想へとシフトしています。先ほどお話しした「Make New」というアクションワードも、「未来の定番をつくろう」という意志を込めています。
新しい価値提案に、モノとコトの区分けはない
井上:ありがとうございます。私は毎年、グッドデザイン賞の審査員を務めているんですが、「モノからコトへ」という流れはその受賞トレンドとしてもありました。実際に大賞や大賞候補に残るのはソーシャル的な活動を評価されるものが多かったんですが、今年はパナソニックさんの「LAMDASH PALM IN」が大賞候補になり金賞を受賞しました。トラディッショナルど真ん中とも言えそうなシェーバーをどうデザインするかという問いが、現代的な意味を持つことにつながったというのは、個人的に痛快というか、すごいことだなと感じておりました。
木村さんがお話しされたように、パナソニックさんは未来までをデザインでとらえようとされつつも、やはり基軸はモノづくりにありますよね。全体を統括されるなかで、そのあたりどんなことを考え、気をつけていらっしゃるんでしょうか。
木村:やっぱり僕らも結局は、高度経済成長時代の延長で考えてきたところがずっとあったわけです。だけど、それが立ち行かなくなるなかで、もう一回、社会課題から見つめ直してデザインしていきたいし、それを解決できるデザインの力をモノを通じて示したい。そこから生まれたのが、まさにこの「PALM IN」というシェーバーです。シェーバーというのは、すごく男性的でガジェット感のあるプロダクトですよね。
井上:特に最近は、かなりゴリゴリッとしたデザインが多いです。
木村:そうですよね。6枚刃になって剃り味がどうこうといった話をうちもずっとしていたんですけど、そうじゃなくて時代性も含めて、何が今求められているのか。それをストレートに追求していって「PALM IN」という製品が生まれました。ぜひ、そのことについて、リサーチの観点から井登さんに聞きたいなと思っていました。
井登:デザインアワードの話で言うと、数年前まではグッドデザイン賞も上位賞はモノに与えられるという伝統がありましたが、2018年に「おてらおやつクラブ」が大賞を受賞されて、それが転換期とよく言われていますよね。海外では先行して、2014年のUKデザインアワードで、「GOV.UK」という公共サービスのデジタル・トランスフォーメーションに賞を与えたという印象深い出来事がありました。
その流れに対して、今回「PALM IN」が評価された背景には、決して「モノからコトへ」からの反動・回帰という単純な話じゃなくて、「今までモノとコトを何で分けて考えていたのか」という視点があるのではないかと私は考えています。シェーバーが持っている、髭を効率よく、肌に優しく、安全に剃るというカミソリから進化した機能的観点からリサーチをしていたら、おそらく「PALM IN」はもっと違うプロダクトになっていましたよね。機能的な差異だけでは、今までのシェーバーと意味的には何ら変わらない。その点で、「PALM IN」は、「シェーバーの意味」を変えたんじゃないでしょうか。
シェーバーに「カワイイ」なんて概念はなかったでしょうし、触っていたくなる手触りとか、ソープディッシュみたいな置皿とか、「朝に短い時間で効率よく済ませたい作業」としての髭剃りとは発想からして違っています。おそらく一部の人にはすでにあった、髭剃りという行為に対する意識の変化がすくい上げられた結果、生まれたプロダクトなのかなと思います。
木村:実際に制作の背景として、入社してくる若い社員を見て、意識の変化を感じたことがあります。若い子たちはわれわれと全然違って、スキンケアに余念がないんですよ。スチーマーを持っているのは当たり前という感じで、とにかく美意識が高い。
これだけ美意識に変化があるなら、われわれの製品だって変わるべきだろうというのもありましたし、井登さんが先ほどおっしゃったように、目の前の人のリサーチは当然するんですけど、それだけではこぼれ落ちるものもたくさんあります。逆に、「美意識は10年後にどうなっているんだろう」と考えることで、「じゃあ、今はどうあるべきなのか」という発想の飛躍ができたんです。今と未来の両方を行ったり来たりできる、実装もできるし未来を空想できることは、うちの強みだと思いますね。
井登:面白いですね。シェーバーで言うと、肌に合っている、人間工学的に正しい、安全性を担保されているといった機能合理性は重要なんですけど、その合理性の延長線上にはあんまり先がないですよね。ただ、合理性がないと「なぜこれがいいのか」という説明ができないわけで、社内でもプロジェクトが進まない。合理性を考えることと合理性から距離を取ることの両輪が求められるわけです。
たとえば、男性もスキンケアをするという周辺から起きている変化をつかまえて、従来シェーバーでは合理性として扱われてこなかった部分に可能性を見つけていく、ということをわれわれデザインリサーチャーは日々やっています。当然、目の前のユーザーが欲していることは拾いつつ、従来のユーザーとは違う領域の人たちから変化の兆しをもらう。一部の人しかまだやっていないけれど、確実に一部では起きている何か差異であったり、変化を拝借してくると、今の合理性では説明がつかなくても、5年、10年経って合理性として融合していったら、ちゃんと説明がつくようになります。リサーチを生業としている側からすると、いかにその両方をちゃんと見るかが頑張りどころなんです。
「両利きの経営」を実現するマネジメントとは?
井上:向き合うべき問いが変わるんですね。つまり、「より良いシェーバーとは何か」ではなく、「10年後の美意識とは何か」という問いに変わると。その問いを解決する過程で、合理と非合理を行き来したり、クラフトとしてのディテールと未来への妄想を行き来したりする、その振れ幅がジャンプの源泉だと感じました。
ただ、これは頭ではなんとなく納得しても、実践するのはそうとうハードルが高いとも思います。お二人には、いろいろな成功例と失敗例があると思いますが、何かジャンプの起点になったものとか、こういうものがあるとジャンプしやすいとか、そういう感覚をもう少しうかがいたいです。
木村:難しいですね……。振り返ると、今出したような事例は、一般的な家電とは違う切り口だったりします。パナソニックでは、王道の洗濯機、冷蔵庫なども製造していまして、それはそれで非常に重要な成熟商品ですし、どう進化させるのか、アップデートしていくのか、という面でも新しい取り組みをしています。成熟と新規の両方をやっていることは、一つ大事なのかなと思っています。成熟を知り尽くしているからこそ、ジャンプアップもできるようなところがあって、その起点になるのは「人」なので、最終的には人の問題に戻ってきますね。
井登:マネジメントの観点で言うと、チャールズ・オライリーとマイケル・タッシュマンという研究者が提唱した「両利きの経営」というコンセプトがありますよね。そこでは「知の探索」と「知の深化」という語が出てきます。これはよく誤解されがちですが、両利きの経営というのは、既存領域を深化していく人、新しい領域を探索していく人と、「人」に目がいきがちなんですけど、二人が言っているのは「マネジメント」のことなんですよ。
もう一つ、大事なのは「モノ」の力です。先ほどお話ししたように、新しい提案、新しい意味は、そもそも既存の意味の体系からはみ出しているので、説明できないんです。ところが、実物が手元にあると、説明されなくてもふっと理解できると思うんですよ。たとえば、「PALM IN」なら、若い人たちが自分たちのライフスタイルの中に存在しているシーンが、すぐに思い浮かびそうですよね。新しい意味を提案しようと思うなら、その意味を「モノ」に凝縮していくことで、それ自体が説明になる。「PALM IN」は、そのことを表す非常に良い事例ではないでしょうか。
木村:ありがとうございます。まさにそうだと思います。良くないデザインほど、一生懸命に説明しなきゃいけない。プレゼン上手な人の力で売れる製品にあるのは、デザインの力ではありません。良いデザインというのは説明を必要としない、クリエイティブが持つ力がありますよね。それは経営からも我々が求められているものです。
デザイン経営のような話もありますし、私たちデザイナーの役割として、コミュニケーションにもブランディングにも、と普段は言っているんですけど、本当に期待されているのは、そうしたクリエイティブの魔法みたいなものを私たちがどう発揮するのかだと思います。もちろんロジカルな部分もありますが、もっと感性的なところで、「これでわかるでしょう」と見せられる力。私はいつも「切り口」という言葉を使いますが、いろいろな要請や情報を統合していってきれいにまとめあげる作業と、それを鮮やかな切り口として見せることこそが、僕らつくり手の力ですよね。
井上:お話を聞いていて思い出したのが、台湾の「Gogoro」というEVスクーターの創業者の人が言っていた話です。それまで高校に入るとバイクやスクーターを親に買ってもらっていた慣習から、どう電動スクーターに切り替えてもらうかを考えたときに、0.3秒でパッと見た目からして違うなと思わせる必要がある。その後も、彼らは3時間、3日、3週間、3カ月と、それぞれに感動体験をつくっていると言っていました。これも説明ではなく、感動体験によって人の習慣も変わるし、社会のシフトも起きていくという話ですね。
もう一つ、お二人にうかがいたいのは、組織全体でデザインパワーの価値を最大化しようとしたときに、マネジメントをしているからこそ見えている世界をうかがいたいです。
井登:私たちのチームは、“Design as R&D”、研究開発としてのデザインという言い方を意図的にしています。たとえば、「次の時代をつくるシェーバーをデザインしよう」という号令がかかってからシェーバーについて考え始めるのではなく、デザイナーが常に考えている状態のほうが理想ですよね。シェーバーだけでなく、日々、男性のスキンケアとか、グルーミングとか、習慣とかを気にして見ている。すると、プロジェクトが立ち上がった時点で、すでに大きな差が生まれています。
製品ごと、事業ごと、とセクションが分かれてしまっていると、どうしてもプロジェクトに自分がアサインされた、さあ考えよう、ということになりがちです。そうではなく、個人的なR&D活動、チーム的なR&D活動として、普段からかしこまらずに定期的に話し合ったり、いろんなテーマを設定して考えたりと、気楽なR&D活動を続けていることが大切だと考えています。そうしたメンバーが一人でも多いほうがいいし、それは組織文化にも染み込んでくるものだと思うんですよ。これまでにも優秀なデザイナーやトレーニングを積んだ人なら自然とやってきたことだとは思いますが、超越的な能力を持った個人だけに閉じずに、それがみんなに開かれている企業は今後ますます強くなると思います。
井上:なるほど。一つの解釈ですけど、プロトタイピングというのは、ビジョンと実装の結節点だと思っているんです。流行りとしての「デザイン思考」は終息するかもしれませんが、プロトタイピングはある意味で、営業でも人事でも誰でもできたほうがいいし、それを組織に染み込ませていくことは全組織的なテーマになりそうだなと思いました。
木村:そうですよね。両利きの経営の話も、まさに体質化させていくことだと思います。少し違う切り口で言うと、実はこの京都に来たことそのものが、われわれにとって人材育成やチームビルディングの一環なんですよね。京都に来たことで集まる人が変わるし、新しいネットワーキングができる。そこから製品が変わって、目指す世界観が変わる。そうして共感性を持って人が集まってきたときに、今はグーグルの「360度評価」のような視点で人を採用していっています。
その同じ志を持った仲間をベースにマネジメントするなかで、20代のうちにと言わず、3年目でもトップクラスの商品を手がけられるような状態をどうつくれるかを考えています。それでジャンプアップする人が出てきたり、タレントが出てきたり、それをフォローするベテランが出てきたり、あるいはまったく違うUXのナレッジを持ち寄る外部の方が入ってきたりと、流動性と成長の連続性をどうつくっていくのか。まさにマネジメントの腕の見せどころなのかなと思います。
井上:確かに縦割りになっていていたら、3年目に大打席に立つチャンスはなさそうですもんね。
木村:昔は3年目なんか丁稚奉公で、とてもじゃないけどそんなことはできませんでした。私もそうでしたけど、3年目はまだ弟子も弟子で「蓋のここだけやれ」といった状態でしたから。それでも、私たちの時代のデザイン教育でも、すでに「社会課題を見てデザインするんだ」ということは言われていたじゃないですか。デザイン教育と企業での実践との間に、正直なところギャップは感じてきました。今はそれがないように、ちゃんとデザイン教育を受けて入社してきた子たちに、適切な機会をどれだけ出せるかが大事だと思いますよね。
未来につながる「価値」創出に、デザインが求められる役割とは?
井上:ありがとうございます。デザインの価値というときに、クラフトのパワーを持ちながら、どれだけ未来を構想できるかという話がありましたが、ビジョンのほうについても聞きたいなと思います。たとえば、パナソニックは、「水道哲学」のような圧倒的な未来のビジョンを持ちながらプロダクトをつくってきた会社だと思うのですが、デザインの現場にいればいるほど、要件が多すぎて発想を飛ばしにくい部分もあると思うんです。デザインが未来像をつくることにどう寄与しうるか、というテーマでもお二人にお話をうかがいたいです。
木村:われわれの会社は、それこそクラフト偏重でした。そこをどうブレークスルーするかを試行錯誤していたなかで、今やっと結実してきたところだと思います。それができたのは、先ほどの両利きの話もそうですし、採用も含めてデザインのダイバーシティーを広げていったこともそうですが、結局は結果が出たからだと思いますね。
デザインが色・形だけを扱っていた時代から、未来構想によって新しいコンセプトをつくろう、ビジネスモデルをつくろうと言っても、結果をともなった実績が出せたときに初めて広がりが生まれたと思います。われわれがつくったものがどんどんエンハンスしていって、隣にいる商品企画者、設計者に伝わって、事業上長、社長と伝わっていって、最終的にはエンドユーザーに届く。それくらいのパワーを持ったものを構築してリリースする積み重ねで、信頼関係をつくってきたと思います。
井登:おべんちゃらで言うわけじゃなく、パナソニックは偉い会社ですよね。家電という概念、家庭用電化製品という概念は、実質的に松下幸之助さんがつくったものだと思っているんですよ。一面的には家庭における家事の利便性を上げたわけですけど、実はアバンギャルドなのは、あの時代に家事という拘束から女性を解放した側面があるじゃないですか。便利になると自由な時間が増えるから、女性を中心に家事に従事している者が解放された。結果的に便利だから広まったのかもしれませんが、パナソニックさんが世の中に家電という「モノ」を通して提案したことは、当時は全く常識じゃなかった少し先の新しいライフスタイルですよね。
これはサービスデザインで言う「アダプション」という考え方につながります。サービスデザインという領域において、新しい意味を提案するような製品を世の中に出すときに、大事な2つのフェーズがあって、ローンチ、売り出しのときと、もう一つは「アダプション」なんです。多くの人は、新しい価値の提案を理解し、受け入れて採用するのにハードルがあるので、それをいかにアダプトされやすくするかという局面ですね。そこはやはり「モノ」と「コト」で切り離せない部分で、触ってみたいと思えるとか、手に届くところに売っているとか、そういうところまですべてデザインできてないと、世の中は基本的に変わっていかない。今のデザインには、守備範囲としてそこまで求められているんじゃないかなと思います。
井上:「こういう社会になったほうがいいよね」「こういう人生のほうが豊かじゃないか」という提案を、どう「モノ」として惹き付けるられるかと。説得力のある「モノ」であるうえに、一個一個の体系をそれに擦り合わせてつなげることも、デザインの力でできるということですね。
井登:上から目線過ぎちゃうと、「カッコいいこと言っているけど、それで何だよ」と思われるじゃないですか。かと言って、おもねるのが良いわけじゃない。このバランスがすごく難しいんですよね。簡単ではないからこそ、実現できているものはやっぱり評価されていると思います。
井上:ありがとうございます。最後の質問として、これからデザインの世界はどういう方向性に向かっていくのか。デザインの未来について抱く考えやアイデアをお聞かせください。
木村:私は「日本」という軸を持ち続けたいなと思っています。というのも、やはり日本の企業の存在感がどんどん縮退しているというのもありますし、われわれ自身もグローバルに存在感が弱まっているという危機感は抱いています。だけど、私たちが提供できる価値には、日本的な要素があると思うんです。今はこれだけインバウンドの需要があって、特に京都には世界から大勢の方が来て、めちゃくちゃ喜んで帰っていかれている。それを見ても、やはりわれわれが提供できる日本的な価値は、絶対にあるだろうなと思うんですよね。それを小さくこじんまりとパナソニックという企業で考えるのではなく、大きく日本という軸でとらえていけたら、すごく良いんじゃないかと思っています。
井登:今日のお話を振り返っても、結局は今の時代は「価値」が重要視されてきているわけですよね。その点でデザインパーソンは、「何が価値なのか」「どんな意味を再定義できるのか」「少し先に価値になりうるものは何か」を探し出すことを日々の営みとしてやっているはずなんです。だから、デザインパーソンが担う役割として、あらためてそれを問い続けて、次々とアイデアを試していくんでしょうね。企業の視点で言えば、そうした挑戦をなるべくゆるく許可して、「ダメだ」と言わない文化をどうつくるのか。習慣ができて、デザイナー的な人が増えていくと、企業も社会も価値はますます上がっていくと思います。
井上:どんどん試して、突き抜けて、価値にしていくという積み重ねの先に、未来があるのかなと感じました。本日はありがとうございました。