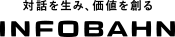創造性を引き出す「組織文化」をデザインするには?【佐宗邦威×井登友一「Designing for Orgculture」イベント・レポート】前編

昨今、「デザイン経営」「パーパス経営」「人的資本経営」など、経営にまつわる新たな視点が数多く提唱されています。そこに共通して求められているのは、企業が「人」を意識して、いかなる組織体制やエコ・システムを築き上げていけるか、という課題感ではないでしょうか。
インフォバーンは2024年3月14日に、『創造性を引き出す「組織文化」をデザインするには?』と題してウェビナー配信イベントを開催しました。同イベントでは、デザイン経営・デザイン思考の日本における先導者であり、戦略デザインファームBIOTOPEの代表を務める佐宗邦威さんをお招きし、インフォバーン副社長の井登友一がお話をうかがいました。
本記事では、前編/後編に分けて、イベントの模様をお届けします(前編/後編はこちら)。
コロナ禍で変化した「イノベーティブな組織」の在り方
井登友一(以下、井登):今日は「組織文化デザイン」をテーマに、主に「創造性」という視点から佐宗邦威さんとお話していきます。まずは簡単に、自己紹介をお願いします。
佐宗邦威(以下、佐宗):はい、BIOTOPE代表の佐宗邦威と申します。BIOTOPEは創業して8年になる戦略デザインファームで、ビジョンづくり、あるいはビジョンを起点にした新規事業開発やブランディング展開を支援する事業を中心的な領域としています。そのなかで、最近はいわゆるパーパスをどうインナーブランディングしていくか、組織文化として醸成していくか、といった取り組みへのご依頼が非常に増えています。私は一貫して、広義のデザインの力でどう経営や組織を創造的にできるか、という問いに基づいて仕事をしてきたと思っていますが、時代を経てそこで具体的に求められることはどんどん変わってきている感覚がありますね。
井登:ありがとうございます。さっそく本題に入りましょう。今回のテーマである「創造性にあふれた組織」というのは、常に「新しいコトやモノ」を発想し続けられる組織とも言えると思いますが、その文化はどうやったらつくれるのか。佐宗さんのお考えはいかがでしょう。
佐宗:これはコロナ前とコロナ後で、もしかしたら答えが変わってきているテーマかもしれません。前提として、新しいコトやモノを生む組織には、「新しいものをつくりたい」というイノベーターがいます。それもただいるだけではなく、そうした人たちが時に周囲とぶつかり合い、熱が生まれ広がることで、新しいコトやモノを生み出していく。その「リアルな場を介した熱の伝導」が、イノベーションの原動力になるイメージがコロナ前まではありました。
ところがオンラインでは、どうしても身体的な熱度が伝播しにくい。今はコロナ禍を経て、オフィス回帰した会社もあれば、リモートワークとリアルを組み合わせる会社もありますが、多くの組織でオンライン・コミュニケーションの比重は増していますよね。
そこで僕が思うのは、コロナ禍以降はバーチャルな場をどうつくるかとともに、〈文脈/コンテクスト〉の共有が今まで以上に大事になってきているということです。コミュニティ内で、いま面白いコト・モノとは何か、時代がどんな方向に向かっているのかといった文脈が、どれだけ共有されているか。個々人が好きにやりたいことを突き詰めやすい環境は整ってきているぶん、企業の側からすると、その熱を組織内部に持ち寄ってもらえる文化をつくる重要性も増している印象を持っています。
井登:非常に共感します。新しいコトやモノというのは、今までの常識やシステムとは外れた、従来では説明がつかない発想から生まれますよね。つまり、今までのルールから逸脱していても、「これがこれからの新しい価値だ!」と思えるような〈文脈/コンテクスト〉を、みんなが共有できている必要があります。
一方で、コロナ前後という観点を少し違う角度から見ると、コロナ前は対面の関係性が重要だったために、つながりや熱量は深い反面、上司と部下、同じ部署の同僚同士といったオフィシャルな組織体制下で構築される関係性が強かったと思うんですよ。それがコロナ禍以降、コミュニケーションの方法が多様になるにつれて、そこから外れたインフォーマルな関係性を築く機会が増えたのではないでしょうか。
株式会社リ・パブリックの田村大さんが、以前「イノベーションを起こせる組織は簡単につくれないけど、イノベーション・フレンドリーな組織にはできる」ということをおっしゃっていました。これは、イノベーションを画策する人たちが、既存のルールを逸脱するアイデアを出したときに、完全にバックアップはしなくても、拒絶しないで放っておく組織にする、ということです。そうした環境から、いずれ新しいコトやモノになっていくような種が出てくる。そう考えると、既存のシステムから逸脱した関係性が増えたことは、コロナ禍で生じた良い変化としてあるのかなとも感じています。
佐宗:なるほど。個人的な活動や副業など、ずっとオフィスにいたらできなかった活動がしやすくなっているという面でも、たしかに個人を中心にした多様性は広がっていますね。以前の日本の組織は、「空気」という名の〈場の文脈〉が強くて、無意識のうちに支配されていましたが、それがだんだん薄くなっている流れがある。
だからこそ、社員が持つ多様な視点やアイデアを組織に持ち寄ってもらうためには、それを「受け入れます」というメッセージを意識的に企業側が発信しなければならなくなっていると思います。なぜパーパスやビジョンがこれほど重要視されるようになったのかと言うと、「目の前の事業の先に、こういうビジョンを描いているから、そのテーマに関係する意見があればどんどん出してほしい」というメッセージを社員に伝える必要性が生じたことも、要因としてありますよね。
今まではリアルな場を介して勝手に集まってきた社員のアイデアを、組織側が意図的に引き出さなければいけなくなった。多様性と自律性が増すなかで、これは今の企業に問われている大きな課題だと思います。
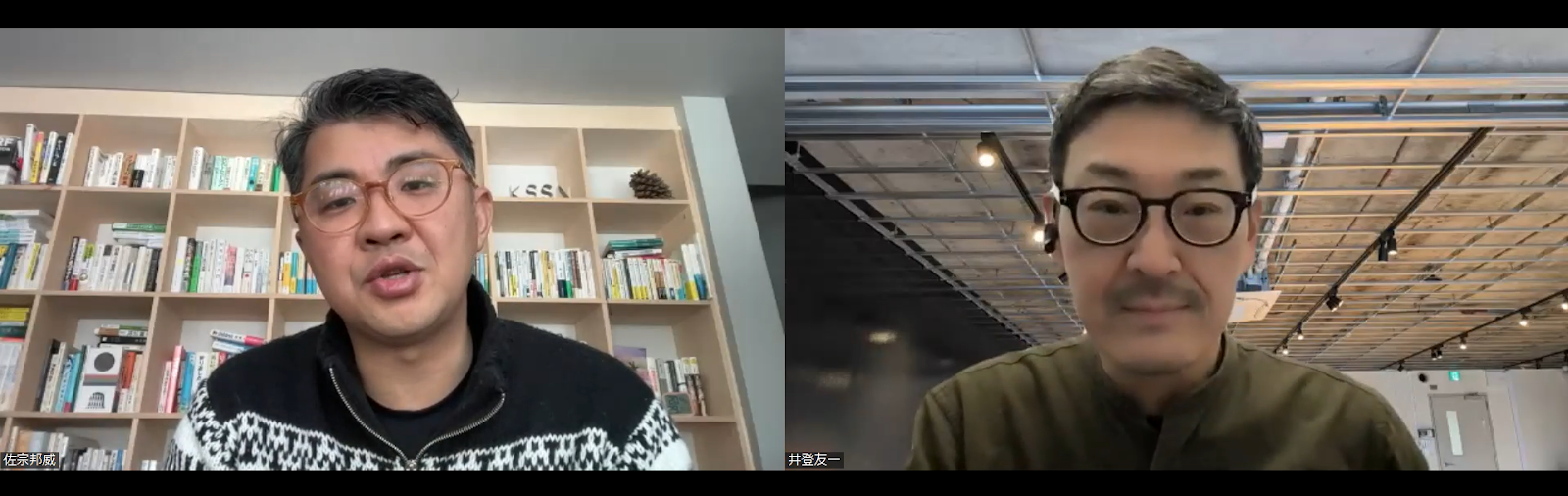
意識的な「モードの切り替え」が組織を左右する
井登:おっしゃる通りですね。社会イノベーションとサービスデザインの世界的権威であるエツィオ・マンズィーニは、人間のマインドセットには、「慣習モード」と「デザインモード」という2つがあると言います。人間は意識していないと「慣習モード」になる。既存の体制や仕組みのままに安定している状態ならそれで良くとも、不確実性の時代のなかでは、クリティカルに現状をとらえ、新しい価値を持ち込むための「デザインモード」に意図的に切り替えなければならない、という話です。佐宗さんのお話を踏まえると、社員だけでなく、会社自体も「デザインモード」に意図的に切り替えないといけない、ということですね。
佐宗:そうですね。似た話は『両利きの経営』(チャールズ・A・オライリー/東洋経済新報社)などでも言われていますが、既存事業をルーティンで回すモードと、いろいろなことにトライして新しい事業を生み出すモードは、まったく異なるものです。両者を組織体制として分ける考え方もあるでしょうし、Googleの「20%ルール」のように社員個人が意識的に使い分けていくやり方もありますが、いずれにせよ、この切り替えをどういう形で、どういう配分でやっていくかは、組織戦略上の重要なポイントだと思います。
特に、リモートワークが盛んになった今は、惰性で物事が進みやすくなっている時代じゃないかと個人的に思っているんです。雑談などのセレンディピティが少ないと、必然的に定型的な作業が優先されがちですよね。だからこそ、モードの切り替えを強制的にでも仕組み化する要請は、ますます強まっているんじゃないでしょうか。
井登:同感です。リモートワークで「生産性」は猛烈に上がると思うんですよ。一方で、これまでになかった新しいモノ・コトを生み出す「創造性」は、効率的という意味での生産性とは別のところにあります。リモートワークによって、サクサク仕事は進んでいくし、タスクの進捗はスムーズになっていく。だけど、それだけでは面白いものがあまり浮かび上がってこなくなる。
佐宗さんはご著書の中で、思考のモードの分け方として「自分モード」「他人モード」という表現も使われていますが、社員が、そして組織が、「他人モード」から「自分モード」へとモードチェンジするために、何が必要だと感じられていますか。
佐宗:オンライン会議をしていて、自分に課されたタスクの進捗を話しているだけでは、ずっと「他人モード」ですよね。しかも放っておくと、今の時代は仕事の大部分がそれになってしまう。かといって、「自分モード」になるのは簡単ではなくて、一人でいたらそうなるかというと、そうではない。やりたいことや自分の考えというのは、他人とのインタラクションがない限り、なかなか一人きりでは出てこないものだと僕は考えています。
最近、BIOTOPEでは月に一度のカルチャーデーを設けて、ケーススタディーやワークショップをする機会をつくっているんですよ。そこでのメンバー同士の会話のなかに、好きなことや推し、偏愛、興味があるテーマ、将来やりたいこと、といった話題を意図的に入れると、相手を鏡にして自分自身のことに気づくことがあります。
よくリーダーシップ研修という形で、自分の過去を振り返りながらリーダーシップスタイルを考え直したり、将来リーダーとしてありたい姿を探求したりするじゃないですか。それを研修ではなく、日常のチームで定期的にやっていくことが、個人が自分を出すうえで重要だし、組織においては「この人はこういうことがやりたい人なんだ」という〈文脈〉になる。そうした時間を定期的に取って継続することが、結果的に「自分モード」の社員が増え、それぞれのやりたいアイデアをどんどん仕事の場に集まってくる良い循環につながるのではないでしょうか。
井登:なるほど。先ほど佐宗さんがチラッと使われた「偏愛」という言葉は、僕も非常に好きな言葉です。我々は企業から依頼を受けて、よくワークショップやデザインセッションを開くんですが、最初のアイスブレイクの時間に私が好んで使うネタが、まさに「お互いの偏愛遍歴を語り合う」ことなんです。大人になると、偏愛する対象にも遍歴があるじゃないですか。昔は好きだったけど興味が薄れて、今は別のものになっているとか。逆に回りまわって、子どものころの偏愛に戻っているとか。
その偏愛遍歴を語り合ってもらうと、それぞれが偏愛する対象は共通していなくても、どこか通じ合える感覚が生まれるんです。なぜそれに偏愛してるのかという方向性が似ている、好きなものが変化していった流れが似ている、といった形で生まれる共感ですね。それは〈文脈/コンテクスト〉というとらえにくいものを共有するためにも、必要な感覚だと思います。
ただ、ワークショップのアイスブレイクタイムでは面白がって話す人でも、日常の業務に戻ると偏愛遍歴を語る機会はあまりない。でも、それを仕組み化してやり続けてしまえば、次第に誰もが疑わずに話すようになる。「ルーティン」という言葉は、ネガティブな文脈で語られがちですけど、「ルーティン」には良さもたくさんあると思っています。
佐宗:まさにおっしゃった通り、文化というのはルーティンによって生まれるものだったりします。最初は無意識に始めた行動かもしれないし、気づいたら惰性になっているかもしれないものですけど、そういう慣習が結果的に文化を生み出すことにつながる。その意味で、自分たちが持っているルーティンに何があるかを棚卸しすることも重要ですね。
〈後編につづく〉