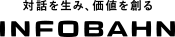創造性を引き出す「組織文化」をデザインするには?【佐宗邦威×井登友一「Designing for Orgculture」イベント・レポート】後編

インフォバーンは2024年3月14日に、『直感と論理をつなぐ思考法』『理念経営2.0』などの著者であり、戦略デザインファームBIOTOPEの代表である佐宗邦威さんをゲストにお招きし、『創造性を引き出す「組織文化」をデザインするには?』と題してウェビナー配信イベントを開催しました。
「創造的な組織」の在り方、そのための意識的な「モードの切り替え」について議論された前回記事に続けて、後編となるこの記事では、イベント後半で展開された「そもそも組織文化はデザインできるものなのか」という問いに対するディスカッションの模様を中心にお届けします(後編/前編はこちら)。
組織文化をあえて‟ローコンテクスト化”する
井登友一(以下、井登):ここからは、組織文化は意図的にデザインできるのか、という観点でお話していきましょう。組織文化デザインを非常に重要なものとしてとらえている我々だからこそ、あえてクリティカルに、批判的にも見ていきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
佐宗邦威(以下、佐宗):文化/カルチャーというのは、社会的につくられた「行動様式」の体系だと、チャールズ・A・オライリーが定義しています。そこには大きく3つの要素があって、1つは、何が許されて何がダメなのかが共有されていること。2つ目が、その行動についてどのくらいの人が合意できているか。最後に、正しいとされる行動から外れたときにどれだけ抵抗や罰があるか。
日本はもともと同調圧力が強くて、「これをやっちゃダメだ」という暗黙のルールがたくさんある組織が多かったと思います。それに対して今の時代は、「これは望ましい/望ましくない」と明文化することによって、「空気を読まなくてもそれだけ守れば、逆にあとは自由にやっていいんだ」と感じさせるモデルに変えていく必要があるんじゃないかと思います。外部の人には理解されない一方で、内部にいる人ならよくわかる、というハイコンテクストな文化をローコンテクスト化していく。しっかりと言語化して、自分たちにとっての良い行動を明確に定義していく。さらに、その理由を文脈をもって伝えていく。
組織文化を完全にデザインすることはできないと思いますけど、明文化することで、組織文化の輪郭をはっきりさせるようなデザインはできるのではないかと考えています。
井登:面白いですね。自己自律的な組織が大事だと最近はよく言われますけど、そうした組織文化をつくろうとして余白を多くすると、ややもするとハイコンテクスト化していく傾向がありますよね。その結果、みんなが目に見えないルールに縛られ、空気を読みすぎてしまって、思考が止まったり、挑戦することにビビったりしてしまう。
真に自己自律的な組織にしたいなら、あえて必要最小限のルールを決めてローコンテクスト化していくことで、「これ以外はルール化されていないから、勝手にやっていいんだよ」というメッセージになる。最近は「心理的安全性」についてよく語られますが、みんなが安心して発言できたり、提案できたりするようになるには、「変に空気を読まなくていい」と意識的に明示する必要があるのと同じですね。
佐宗:そうですね。組織には自然と暗黙知が溜まっていくものなので、それを編集していくようなイメージです。たとえば、過去に起こった膨大なエピソードの中から、特定のエピソードを抽出することによって、組織にとって重要な〈文脈/コンテクスト〉が明確になります。そこで、どのエピソードを選ぶか、あるいは選ばずに削ぎ落とすかによって、同じ組織でも印象が大きく変わります。
デザインというのは、どこか引き算するものだったりもしますよね。膨大な組織文化の中から、必要となるエッセンスだけを抽出し、他を削ぎ落としていくことで、その組織の大事にしていることを明確化していく。そういう役割をデザインは担えるのではないでしょうか。
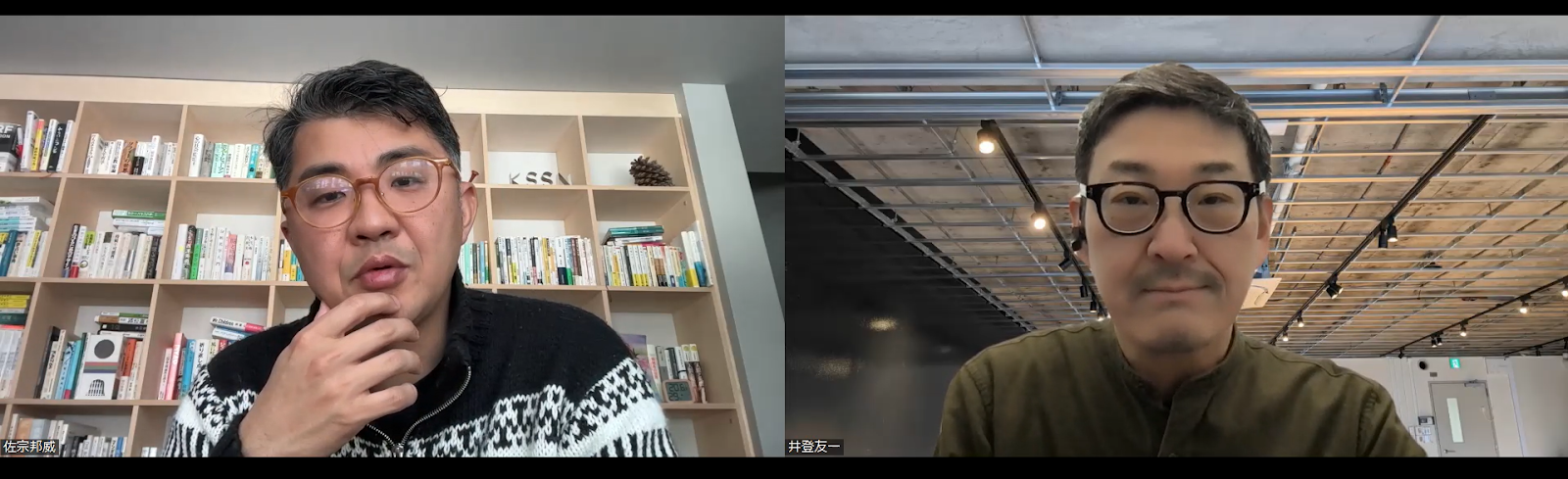
「庭師」としての組織文化デザイナーの役割
井登:うかがったお話と重なるところで、僕が考えていることがあります。どこかデザインには、「完成がある」というイメージを持たれがちですよね。形のあるプロダクトのデザインにせよ、無形のサービスのデザインにせよ、仕上がるタイミングがあって完成品を出すものだとついつい思われがちです。でも、本当はデザインには終わりがない。
もちろん工業製品は物なので、いったんは完成品が出来上がりますが、それだってどんどん改良されていきます。まして、体験や仕組みのような形にならないものまでデザインしていく時代には、デザインに終わりがなくなってきている。ずっとデザインし続けていった結果、ある瞬間、瞬間で、節目として形づくられるものがあるだけです。
最近、私はデザインではなく、「Designing」という言葉を意図的に使うようにしていまして、これは組織論の研究者であるカール・ワイクの発想から来るものです。彼は『センスメーキング イン オーガニゼーション』(文眞堂)という本の中で、「Organaizing(組織化)」という言葉を使っています。所与のものとして確固たる「Organaization(組織)」が存在しているのではなく、人々、制度、ルーティンといったさまざまな要素が絡み合いながら、現在進行形で「Organaizing(組織化)」されているものが組織だと。要するに、集まった人々の関わり合いのなかで、組織というのは常につくられ続けているんだ、ということです。
それを踏まえると、組織文化をデザインするといっても、それは組織としての完成形を目指すものではない気がします。あくまで変化を歓迎しながらも、そのなかで特徴的に浮かび上がってくる組織の「らしさ」や、組織の中で溜まる暗黙知をとらえ、組織文化として際立たせていくような営みなのではないでしょうか。
有名な老舗企業や、ブランド・イメージが強くある企業は、おそらくそれをやり続けてきたことによって、時代に合わせて変化しながら、根っこにある「らしさ」は簡単には揺るがないものになっている。この変化する部分と、一般化していく部分との兼ね合いを「Designing」していくことが、組織文化デザインというものではないかと考えています。
佐宗:やはりプロダクトなどをつくるときのデザイナーの役割と、UI/UXのような比較的インタラクティブ性がありつつも生成物は無機物なもの、組織文化のように人間を対象にするものでは、同じデザインナーという名前でも、役割や立ち位置は違うんだろうと思います。
僕は組織を扱うデザイナーというのは、庭師の感覚に近い気がするんです。庭って完成しないじゃないですか。土壌があって、その上に植物やいろいろな生態系が成る。それに向き合う庭師の仕事は、ただ樹木を植えることではないですよね。土壌を観察しながら、適度に植え、適度に間引きしていく。ずっと組織を観察しながら、組織に適度に関わり続け、時には手をつけない選択肢も取るという意味では、井登さんがおっしゃる「Designing」という考え方に近い感覚なのかなと思いました。
井登:「庭師」というのは、非常に適切でしっくりくる表現ですね。
佐宗:組織文化は、企業にとっての土壌になるものですよね。もともとカルチャーという言葉は、「cultivate=耕す」から来ています。だから、土とその上に成るもの、その両面を見ないと、組織文化の議論は片手落ちな感じがします。組織にある暗黙知や歴史といった土壌を耕しながら、その上に言葉や仕組みを植えていく。組織文化デザインというのは、この庭師的な目線が必要なタイプのデザインなんだろうと思います。
井登:なるほど。仮に組織文化デザイナーという存在がいるとしたら、それは特定の専門デザイナーだけではなく、組織の土を耕し、芽が生えてくる土台をつくる全員がそうなのかもしれませんね。そこに、デザイナーは庭師的な役割で関わっていく。それが良い組織文化をデザインするうえで、欠かせないポイントかもしれません。
佐宗:そう思います。まったくの荒れ地だったら、人はそこで何かしようとは思わない。ある程度の草木なり野菜なりが植わっていて、でもそこに余白もあるからこそ、人々は手入れをしたいと思えるようになります。実際の庭だって、すべて庭師がつくるわけじゃなく、庭の持ち主が生活のなかで育てていくのが基本ですよね。
組織文化をデザインをすることにおいて、媒介としてのデザイナーの役割を考えたときに、そのぐらいの距離感で自分の作品=組織と関わっていくのが良いのかなと思います。
〈おわり/前編はこちら〉