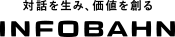「デザイン」のアプローチを用いて、クライアントの価値創造を支援する|アビームコンサルティング株式会社様とのサービス提供に向けて

アジア発のグローバルコンサルティングファームとして、あらゆる業界の企業に対し、経営戦略からITソリューションまで総合的な支援を行うアビームコンサルティング株式会社(以下、アビーム)。インフォバーンは、11月よりアビームと共同で、デジタルを活用した新規事業創出や事業変革を支援するサービスの提供を開始しました。
▼参考リリース
「アビームコンサルティングとインフォバーン、デジタルを活用した新規事業創出・事業変革を支援するサービスを提供開始」
この取り組みは、両社のケイパビリティを結集し、クライアントの事業創出・事業変革と新たな市場開拓を実現し、持続的な成長を図るものです。ポイントとなるのは、昨今ビジネスシーンでも注目を集める「デザイン」のアプローチ。インフォバーンはサービス提供開始に先立ち、アビームからのご依頼を受け、サービスデザインのプロセスを実践的に体験することを通じて、デザイン・ケイパビリティの向上を図る研修プログラムを提供していました。
本記事では、アビームが「デザイン」に注力した背景から、「サービスデザイン実践プログラム」の内容、両社による取り組みの狙いとこれからの展望について、インタビューした内容をお届けします。お話をうかがったのは、本プロジェクトの中核を担うアビーム「design X architect」セクターの下田友嗣様、辻祥史様、およびインフォバーン「イノベーションデザイン事業部」の木継則幸、山岸智子です。
写真撮影|伊藤圭
取材・執筆|木下衛(インフォバーン)
今なぜアビームは「デザイン」に着目しているのか?
――「デザイン」の話題に入る前段として、アビームが得意とするテクノロジー領域において、クライアントを支援するなかで感じられている変化について教えてください。
下田友嗣(以下、下田):かつては業務効率化や社内フローの最適化など、何らかのコスト削減を主な目的にテクノロジーは扱われてきました。それが、ここ十数年のビジネス環境の変化で、テクノロジーの使い方が経営戦略に直結してくるようになった。
ただ経営上の重要性が増しただけでなく、その色合いも大きく変わってきています。あくまで本業をバリューアップするために、いかにテクノロジーを使うかという論点から、今は自社のアセットやケイパビリティにテクノロジーを加えることで、「これまでにないビジネス」や「未来から逆算した新たな事業構想」をどう生み出していくのか、という論点に移っています。
――そうしたビジネス環境の変化に呼応して、アビームがコンサルティングする内容も変化しているわけですね。
下田:そうです。お客様から見たコンサルティングファームへの役割期待も変わってきています。われわれは従来、お客様が自社ではできない/やるべきではない領域で、PMO(プロジェクト・マネジメント・オフィス)支援やアドバイザリー支援、基幹システム刷新やシステム構築の業務を請け負っていました。いわゆるお客様の「ホワイトスペース(余白)を埋めるための存在」として、当社を含めたコンサルティングファームは認識されていたと思います。
しかし、最近ではお客様から、「身内だけで意見を出し合っても、似たような視点/限られた世界観での議論に留まってしまい、大きな変化を起こしにくい」と悩む声をよく聞きます。他ならぬお客様自身が、異能なものを取り込むことで化学変化を起こしていく必要性を感じられているわけです。そうなると当然、コンサルティングファームが果たすべき役割も、単なるホワイトスペースを埋める存在から、「ともに新たな事業や組織をつくり出していくためのパートナー」へと変わってきます。

「design X architect」セクター シニアマネージャー 下田友嗣さん
――そのなかで「デザイン」というキーワードが出てきたのはなぜでしょうか?
下田:お客様の期待に応えるためにわれわれがすべきことは、「アビームならではの問い」を立て、その問いに対する「アビームならではの解決策」を提案することだと考えています。「デザイン」に着目したのはそのためです。
私たちは今まで、いわゆるロジカルシンキングを使って、複雑な問題をクリアな問題へと整理したうえで、それを最短距離で解決することを得意としてきました。ところが、新たな価値をお客様とつくるうえでは、従来通りのやり方ではうまくいきません。これまでの延長線上にはない発想を生み出すためには、答えのないなかで探求する「デザイン的なアプローチ」が必要だと考えたわけです。
――課題解決といっても、その課題の捉え方自体が大きく変わっているわけですね。
下田:たとえば製造業は、モノを販売することを生業とされていたと思います。モノの販売はヒットすれば大きな市場規模をつくりやすい反面、売りつくしていくうちにピークアウトしていく。伝統的なグッズドミナントロジック(企業が提供する価値を製造した商品自体にのみ求める考え方)で考えれば、これは当然のことです。
もう10年以上前から「モノからコトへ」と語られてきたように、今はサービスドミナントロジック(企業が提供する価値をすべてサービスとして捉え、その価値は顧客との共創で生まれるとする考え方)を起点にした事業転換が求められていますが、だからといって表面的にビジネスモデルだけを変えてもうまくいかないと考えています。
製品に新たなサービスを付加したり、新たな販売モデルを取り入れたりしても、組織的に回らずにクレームが増えるだけの結果に終わるなど、失敗例は無数にあります。結局、企業内の文化や人を無視して目の前のビジネスだけを必死に考えても、それを支える人や組織も変えていかなければ、新しい価値は生み出せないわけです。
――アビームさんが考える「デザイン」の対象とは、どのようなものでしょうか?
下田:いわゆる色・物・形のデザインを指しているわけではないです。お客様がどういう社会や未来をつくりたいのか。そこに向けた事業に必要なビジネスモデル、組織体制やチーム編成、人材はどのようなものか。あるいは、今は1社単独で事業の成功を目指す時代でもありません。エコパートナー/エコシステムを築くために、時には企業間のコラボレーションも必要です。総じて企業が持続的、安定的に成長していくために必要なビジネスやテクノロジーを考え、具現化することが、われわれにとっての「デザイン」ですね。
将来に向けた「design X architect」のミッションとは?
――下田さん、辻さんが所属されている「design X architect」について教えてください。
下田:「デジタルテクノロジービジネスユニット」という事業部門内に新設された組織です。クロスインダストリー、クロステクノロジーで、ビジネスとIT両方の知見を持ちながら、その事業や変革に最適なビジネスモデル、IT、アジャイルを含むプロジェクトアプローチをデザインし、並行して最適なビジネス、データ、アプリ、テクノロジーのアーキテクチャ(構成/構造)を総合的に判断する専門組織です。
「design X architect」ができた背景の1つには、ビジネスもテクノロジーも急変する時代のなかで、未来の顧客体験・企業価値・働き方をもたらすアーキテクチャ、テクノロジーをアビームの武器とするには、より少ない時間でより高い価値を提供しつつ、未来に投資する時間を確保し続けなければならないという危機感がありました。
その危惧のもと、未来に向けたある種の投資として組織化されたのが「design X architect」です。私たちには、クライアントを成功に導く再現性の高い「より優れた」取り組みを探求・実践し、アビーム社員のみならず、社外の多くの方々に広めることで、より多くのクライアントと社会を未来の成功へと導くミッションがあります。
その他に「design X architect」には、セクター内で閉じるのではなく、あらゆるビジネスユニットやセクター、世の中のエコシステムなど、多くの人と相乗効果を生む協働のあり方を探求していくミッションもあると考えています。

――事業部門でありながら、人と人をつなぎ合わせていく機能もあるわけですね。
下田:そうですね。「お客様が本当に実現したいこと」を引き出し、それを実現するための「より優れたデザインとアーキテクチャ」を描き、実現できるためのビジネスとIT両方の有識者、専門家をつなぎ合わせ、実現できるように導くともいえると思います。
ですので、他部門との関わりも多く、たくさんの社内からの問い合わせに答えています。たとえば、ひと口にテクノロジーを使うと言っても、どのようなアーキテクチャにしたらよいか、どのようなソリューションを組み合わせるべきなのか。数千人月規模の基幹システム刷新をどのようなアプローチで進めていけばリスクが軽減されるか、成功しやすくなるのか。お客様の課題ごとに最適な方法はそれぞれです。そうした多種多様な社内からの相談事を受け止め、色がない状態に色をつけていく旗振り役も一部担っています。
あるいは、アビームには各領域における専門人材がいますので、たとえば最先端のマーケティング手法を知りたいというお客様がいれば、社内からCX戦略に長けた者を連れ出して引き合わせるなど、ハブとなって社内外の人をつなぎ合わせることもミッションの一つです。
――セクター名に「design」だけでなく、「X architect」と付けているのは?
下田:事業創出や組織改革を実現するには、ビジネス面でもテクノロジー面でも、強固な「アーキテクチャ」を築かない限り、骨なしで進むプロジェクトになってしまいます。われわれには「絵に描いた餅で終わらせない」というスローガンがあります。ただのアイデア提案に終わってしまっては、デザインは意味をなさないと考え、具現化することに強いこだわりを持っている。そうした姿勢を表すために、「design X architect」と名付けています。また、「デザイン」と「アーキテクト」には、課題を解決するうえで決まったやり方がないという共通点もあります。
互いを高め合えるパートナー同士として
――そんなアビームが、デザイン領域におけるパートナーを探されたのはなぜでしょうか?
下田:先ほど「アビームならでは」の問いと解決策を提示する、という話をしましたが、その価値を高めるためには、逆に「自社で完結しようとしない」ことが重要だと考えているからです。アビームは全社的にエコパートナー戦略に貪欲ですが、ことデザイン領域においてはあまりパートナーがいなかったので、頼れる相手をずっと探していました。
――「アビームならでは」を出すためにパートナー戦略を取る、というのは逆説的で面白い考えですね。
下田:たとえば、OSS(オープンソースソフトウェア)にまつわる論争は常にありますが、ソフトウェア産業の歴史を見ても、自社単独に拘泥したサービスの多くは衰退の道をたどっていますよね。誰でも無料で使えたり、外部に開かれたものが成長している。
歴史は繰り返すと言いますが、自前にこだわっていては変化を起こせない。その意味で今回の両社による取り組みは、「アビームならでは」をつくるためであり、「インフォバーンならでは」を発揮していただくためでもあります。そうした協力関係を築けない限り、これからの社会でデジタルを活用した事業創出は難しいという戦略的な判断があります。
辻祥史(以下、辻):事業創出の性質を考えたときに、今ある事業の周辺領域にある別の業界・業種に踏み出す機会が増えていきます。その際に、外部の知見を積極的に取り入れたい。特に、デザインの領域では、多様な意見や視点を取り入れ混ぜ合わせるべきだと考えています。

「design X architect」セクター マネージャー 辻祥史さん
――共同プロジェクトのパートナーとして、インフォバーンを選ばれた理由は?
下田:アビームにも、われわれのお客様にもフィットする会社を探すなかで、インフォバーンさんは理想的な相手でした。長年、大手企業のクライアント支援をされてきた実績への信頼もありますが、それ以上に惹かれたのはインフォバーンの企業文化や考え方です。
インフォバーンは、日々プロジェクトワークに取り組まれながら、そこで培った経験を方法論化/メソッド化するアセットワークもされていますよね。自らの提供価値を持続的に高めていこうとするマインドに、信頼できる会社だと惚れ込んだんです。
辻:実は最初に社内でインフォバーンを提案したのは私なんです。その仕事ぶりは昔から存じ上げていたので、デザイン領域で協業パートナーを探すとなった際に真っ先に思い浮かびました。
下田の言う通り、ともにプロジェクトを進めるうえで、特定の社員に依存する企業がパートナーではなかなかスケールが大きくなりません。価値観が合うという確信がありましたし、個人技を抜きにした会社全体としても信頼できる存在として、声をかけさせてもらった次第です。
それともう一つ、パートナーを探す際に意識したのは、協業を通じて双方ともにバリューアップできる関係性でした。そのためには両社のケイパビリティが被らないほうが良い。互いの長所を活かしながら不足を補えるWin-Winの関係であることが、お客様のためにもなると考えています。
木継則幸(以下、木継):価値創造という観点で言うと、まさにクライアントにとってのバリューチェーンのサイクルが循環することが大事ですね。
インフォバーンは、大きく3つのデザイン活動が提供できると考えています。一つはビジョンデザインで、未来を起点にプロジェクトや事業の方向性を決めていく。二つ目はサービスデザイン。製品やサービスを構想し、具現化していく。最後がマーケティングデザインで、つくった価値を正しく伝えて市場を開拓しながら、フィードバックを得る。そのフィードバックは、また別の価値創造につなげるリサーチ活動にもなります。
逆にインフォバーンに足りないのは、ITなどシステム周りやビジネスモデルの構築、アジャイル的なアプローチなど、アビームさんの強みの部分です。お互い足りないピースがブリッジされることで、それぞれの強みを活かすようなサイクルが回ればと思います。

「デザイン人材」はどのように育成できるのか?
――共同支援を始める以前に、インフォバーンからアビームさんに「サービスデザイン研修実践プログラム」をご提供していました。
下田:「design X architect」のメンバー9人で受講させていただきました。冒頭にお話しした通り、私たちはすでにある複雑な課題をクリアにし、解決策を考えることには長けていますが、「複雑なものを複雑なまま考える」というのはまだまだ苦手です。
複雑に絡み合った線を解きほぐさずに、その中から1本の線を見つけてストーリーラインとして描き出す。すぐに答えを出さず、物事の見方を変えるためにリフレーミングしてみる。そうした力をメンバーに身につけさせたかったので、インフォバーンに研修をお願いしました。
山岸智子(以下、山岸):提供したのは、7日間をかけてサービスデザインの一連のプロセスを実践的に体験していただくプログラムです。サービスデザインの体系的な理解が深まるように構成しつつ、特に「課題探索」に注力してプログラムを設計しました。
3つのチームに分かれ、それぞれに用意した「トライブレポート(特定の志向を持った先駆的な生活者像をまとめたレポート)」をもとに、インサイト導出に向けたリサーチ、新たな問いや解決策のアイデア発想、提案サービスの価値を伝えるためのプロトタイピングを行う、というのが大まかな流れです。

木継:サービスデザインを体系的に学ぶことは、これからのビジネスに必要なデザイン・ケイパビリティを獲得することにつながると考えています。
というのもサービスデザインには、持続的な価値創出のためのエッセンスが含まれているからです。ヒューマンセントリック(人間中心)に考えること。ホリスティック(全体的)な視点、つまり自社や顧客だけでなく、さまざまなアクターやファクターの関係性を紐解きながら、あらゆるステークホルダーにとって望ましい状況を構想すること。あるいはイテレイティブ(反復的)な試み、モノをつくりながら発見・理解を得ることを繰り返して新しい洞察を得ること。そうしたいくつかの原則が、サービスデザインにはあります。
実践しながらその原則を体験することで、下田さんがおっしゃった「複雑なものを複雑なまま考え」ながら、未来に向けた新しい価値、ビジョン、状況をイメージするか、という発想につながっていきます。
辻:私も参加しましたが、普段とは使う頭が違うので、脳が筋肉痛になるような感覚が湧きました。時にロジカルな思考とデザインの思考を切り替えながら、両者を行き来する作業はすごく新鮮でしたね。
――最近は「デザイン人材」を求める声も多く聞かれますが、「デジタル人材」という言葉に比べても、抽象的で捉えどころのなさも感じます。
下田:たしかに言葉が先行しているところはあるかもしれませんね。明確にデザイン人材の要件を整理して「こういうスキルが必要です」とエクセルにまとめ、従業員に習得をうながすようなものかと言えば、そうではないと思います。
その点で、アビームの人材育成論には、そもそも「銀の弾丸」となる答えは提供しないという大前提があるんです。私は入社した社員に向けて方法論の講義を行っていますが、「これを正解として、そのままやってはダメだ」と強調しています。「お客様やプロジェクトのステークホルダーの状況を踏まえて、どこをどうテーラリングすべきかを考えるのがみなさんのミッションです」と必ず言うんです。
あくまでもポイントや考え方、標準的なプロセスを伝えるだけで、単一の「銀の弾丸」があるかのように誤解させない。それは、「デザイン」においても同じです。
木継:私も、デザイン的なアプローチをビジネスシーンで浸透させるためには、暗黙的なノウハウを一般化し共有する必要があると考えています。その枠組みのひとつがサービスデザインのプロセスですが、それをただアウトプットを出すスキームと捉えては本質からズレてしまう。
理論性に縛られずに、プロセスのなかで湧き出る特殊性や異質性、クリエイティブジャンプといった理論的でないユニークな価値を、共通認識として持つことが育成においても肝になるはずです。
――研修プログラムが講義による座学ではなく、「実践的な体験」に重きをおいて設計したのもそのためですね?
木継:そうです。実際に今回の研修プログラムを通じて、アビームさんのデザイン・ケイパビリティが上がったと感じました。理論的な「分析(=Analysis)」の対義語として「統合(=Synthesis)」という概念があり、これはデザイン・アプローチにおいて重要な力です。プログラムが後半へと進むにつれ、みなさんは前者から後者へと見事に視点をシフトしていかれましたよね。
具体的には、「健康」をテーマに課題探索をされたチームは、健康を阻害する要因を分析するのではなく、「不健康な奴はだいたい友達」というコンセプトを立て、不健康な者同士の一体感を社会的価値に転換するにはどうすればよいか、と発想を転換されていました。「防災」をテーマにしたチームもそうです。どう災害を防ぐかではなく、避けられないものとして受け入れたうえで、どう日常生活の中でレジリエンスを高めるか、という問いを立てていました。こうした発想の転換は、分析だけでは生まれない、まさに統合的なアプローチです。
辻:サービスデザインのプロセスとして、世間一般に整備されたものがなかったので、今回の研修プログラムはとても刺激になりました。
アビーム×インフォバーンの力で価値創造のサイクルを

――ロジカル思考に比べ、デザイン思考によるアイデアは「再現」するのが難しいイメージがありますが、そのあたりはいかがでしょうか?
木継:デザイン的思考の特徴の一つに「主観性」があります。今回のプログラムでも、トライブというエクストリームの行動から、顧客のこだわりや義憤を読み解くなかで、自ずと主観性が生まれ自身のナラティブが物語られる体験をしていただきました。そうした未来の兆しとなるような違和感を日常の中で見つけるための主観性を持つことでも、アイデアの再現性につなげることができると思います。
あるいは「アブダクション(abduction)」という仮説の思考法を取ることも重要です。演繹的、帰納的に考えるのではなく、非連続な仮説をつくり、その仮説が成立するための新しい発想、アイデアを導き出していく。
そうしたロジカルとは対極にある「主観的」な考えや「アブダクション」の発想を、業務プロセスのなかに意識的に取り入れることは大事ですね。
下田:主観性に関連して、私も「何を美しく感じるか」という美意識や美学は大事だと思っています。その点でわれわれには「最小の取り組みで最大の価値を出す」というある種の美意識とも呼べる感覚があります。
たとえば、「経営層と現場で意見の相違があるので、知見を聞かせて欲しい」といった要望に応じて、1時間だけお客様と打ち合わせさせていただくケースもあります。たった1時間ですが、われわれのノウハウ、知見、メソッドがきっかけとなり、お客様の中で変革が動き始める……となれば、その打ち合わせが生み出す価値は1時間以上の価値が生まれると考えています。
このようなアウトプットを生むために、自分なりに問いを立て、日々の探究・実践をしていくことが重要だと、セクターのメンバーには1on1で直接伝えるようにしています。
木継:組織論では、タスクを分散して効率的に処理していく「情報処理理論」と対比して、いわゆる「知識創造理論」が引き合いに出されます。そこには、複数の場が連鎖することで、多様な文脈が動的に共有されるという考え方があります。
「desgin X arichitect」は、その連鎖を起こす存在だと思うんですよね。他部門と接続しながら、「問い」を通じて文脈を多様に重層的に積み重ねていく作業をしている。それを他の部門の人が体験的に実感することによって、デザイン的な考え方や美意識も伝播していくのではないかと思っています。
――最後に、これからの協業に向けて意気込みをお教えください。
辻:これまでのインフォバーンさんとの活動で育んできたことを、早く一緒にプロジェクトで実践していきたいですね。お客様の事業創出や事業変革に向けて実践するなかで、われわれがデザインのケイパビリティを身につけることにもつながると思いますし、提供サービスの強化ポイントも明確になってくると思うので、より良いサービスになるよう一緒に取り組めていけたらなと思っています。
下田:まずは私たちが組むことで生まれるパワーをお客様に示して、信頼関係を築きたいです。そのうえで、お客様のパワーが組み合わさることで、生活様式を変えるようなサービスを生み出し、日本の社会を良くしたい、というのが私の想いです。
木継:アビームさんは理論づけるだけではなく、しっかり実践してスピーディに成果を出すところにすごさを感じています。そうした方と一緒に、価値創造のサイクルを回していくことが非常に楽しみです。
業界とサービスラインの双方に広いカバレッジを持つアビームさんと組むことで、新たな領域でデザインの力を発揮するチャンスも増えると思いますので、両社の力でデザイン的アプローチを広く世の中に浸透させていきたいです。
山岸:インフォバーン・イノベーションデザイン事業部のアイデンティティの一つに、「トラブルメーカーであれ」というものがあります。クライアントの要望通りにただ動くのではなく、時に「それは本当に取り組むべきことですか?」と批判的な視点を伝えたり、「他にも方法はあるのではないでしょうか?」と議論をかき混ぜたり、クライアントが変化するための媒介になれるように、あえて良いトラブルを起こす。そうした存在であるという自己認識があるんです。
今日お話をうかがっていて、「design X architeict」のチームには同じようなマインドがあると感じました。トラブルメーカー同士がかけ合わさることで、どんな良いトラブルを巻き起こせるのか楽しみですし、両社ならではのユニークネスが出せるのではないかと思っています。