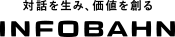「コンテンツ」を掘り起こす、その実態と心構えを見た

夏目漱石の随筆集『夢十夜』。漱石が夢枕に見た内容を綴った、オムニバス短篇集だが、その第六夜に次のような話がある。
鎌倉時代に名をなした仏師、運慶(うんけい)が、なぜか現代(作中では明治時代)まで生き残っていて、近くで仁王像を彫っているという。そこで散歩がてら、見物に行ったというエピソードだ。
やいのやいのうるさい他の野次馬にまじって、一連の作業を眺めていた主人公。いつしか運慶が「いかにも無遠慮に」掘りあげていく様子を見て、ひとつの感想を抱く。
そこで、「彫刻とはそんなものかと」思い始めた主人公は、家に戻って自分でも仁王を掘ってみる。しかし、積んである薪を片っ端から彫ってみても、ひとつも仁王は埋まっていない。そうして「明治の木にはとうてい仁王は埋まっていないものだと」悟ったという内容だ。
◆ ◆ ◆
本書『戦略的コンテンツマーケティング』を読み終えたとき、この『夢十夜』のストーリーが強く脳裏によぎった。夢の中の話だから荒唐無稽なのだが、なにか深く関連していそうな事柄がある。我々が着手すべき、コンテンツマーケティングとは、この運慶と仁王の関係にあるのではないか?
というのも、非才・浅学ながら、コンテンツ産業の末席を十年以上汚し続けてきた筆者。長年、同じことを続けていると、運良く、ごく稀にヒットの確信を含んだ記事やら企画やらを生み出せるときがあるのだ。
たいがい通常の記事や企画は、日々のローテーション作業の一環として、流れ作業的に生み出される。いや、もちろんプロである以上、つねにヒットを狙っているわけだが、なにしろ非才。どんなにひねり出しても、毎回思った通りのムーブメントを起こせるわけがない。というか、いつもどこか成功を信じきれていないのである。まるで、『夢十夜』の主人公が、自分で仁王を彫ってみたときのように。
ところが、実際にヒットする記事や企画を世に出せたときは違う。なんというか、ジグソーパズルのすべてのピースが連鎖的にハマっていく感覚。まさに一刀両断、「これ以外ない!」という形のものが即座に決まる。『夢十夜』の運慶のように、変な疑いを差し込むことなく、信じるままに記事や企画をスピーディに深掘りしていけるのだ。
◆ ◆ ◆
おそらく、本書を手にした人が抱えている疑問のひとつは、「なにを訴えればいいのか?」というものだろう。いつもの筆者と同じである。そのヒントとなることが、本書32ページ「■顧客は誰?」という見出しの章にあった。
そう、本書を手にとった時点で、すでにそれは存在している。いま広くPRしなくてはいけない、自社の新サービスや新製品。もしくはブランド認知かもしれない。おそらく、あなたは、それを本当にユーザーが求めているのか、自信が持てていないのだろう。そんな状態にいるはずだ。
それは「いかにして訴えるべきものの魅力をコンテンツとして具現化していくか?」という疑問に置き換えられるかもしれない。『夢十夜』の主人公になぞらえるとこうなる。
自社の新サービスや新製品は、掘り進むべき「薪」。そこから掘り起こさなくてはいけないのが、読者に届けるべきコンテンツ「仁王」である。だが、どうやって掘り進めるべきかわからない…そこで「明治の木にはとうてい仁王は埋まっていない」といいわけしてしまうような状態だ。
本書47ページ「第3章 旅を創造する:コンテンツの柱づくり」では、次のようなことが書かれている。「何を語るか?」について、1960年に著されたセオドア・レビット教授の論文『近視眼的マーケティング』を引用して、説明するくだりだ。
つまり、この場合「鉄道会社」が掘り進める「薪」。そして、マーケティングとして具現化しなくてはいけないものが「輸送業」という「仁王」になる。あるいは、仁王は「本質」と言い換えることができるかもしれない。あなたが抱える、PRしなくてはいけないものにも、そうした「本質」がきっと含まれているはずだ。さらに、本書40ページ「ペルソナを購買サイクルに重ねる」より抜粋しよう。
マーケティングにおける本質とは、ユーザーにいかに必要とされるかということなのだろう。別の言葉で表現すれば、「自分ゴト」化ということになる。それをユーザーに感じてもらうための手法が、本書『戦略的コンテンツマーケティング』に記されているのだ。
◆ ◆ ◆
「まるで土の中から石を掘り出す」ように、さもなんでもないような素振りで仁王を掘り出していた運慶。しかし、その背景には、膨大な努力とノウハウが注ぎ込まれているのは間違いない。しかも、それは端から見ると、自分でもできてしまうのではないかと錯覚を起こさせるほど、自然なものだ。
我々が行おうとしているコンテンツマーケティングもまったく同じ。ユーザーに届けられるストーリーは、さも当然のようにそこにある。しかし、その背景には緻密な計算とプランが張り巡らされていて、あたかもユーザーに「自分ゴト」と感じさせるように提供されなくてはいけない。
そこで大切になるのが心構えである。本書81ページ「第5章 まとめあげる」では、こんなふうに表現されていた。
たとえ、同じ薪でも、運慶は信じている。そこに仁王が眠っていることを。だから、我々も同じように、信じなくてはいけない。自らの仁王がそこにあることを。本書『戦略的コンテンツマーケティング』を読めば、それができるようになるはずだ。