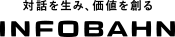要は、物語なのだ

マーケター必携の“参考書”
本書は、従来のマーケティングに新たな風を吹き込む注目のマーケティング手法、「コンテンツマーケティング」の戦略とプロセスとを、大局的な見地から示した手引き書である。タイトルにもあるように、企業自らメディアを有する「オウンドメディア」の観点から、各段階に応じた事細かな解説が行われているのが特徴だ。
その構成は、目次を眺めれば一目瞭然である。
2部構成からなる本書は、前半にコンテンツマーケティングの戦略づくりが述べられる。ビジネスケースづくりにはじまり、ペルソナづくりやコンテンツの考え方、多様化するインターフェイスへの対応、と一貫して「企業の物語をいかにして(誰に、どんな物語を、どこで)語るか」という点に紙幅が割かれている。一方、後半の第2部では、練り上げられた戦略をいかにマネジメントしていくのか、具体的なプロセスを通じて仔細に解説が与えられていく。
そう、まるで「教科書」のようではないか? ——ややくだけた筆の運びや、ときおり繰り出されるジョークやたとえ話の冗長さが、その教科書的な堅苦しさや権威性を緩和しているとはいえ。とくに自社のコンテンツマーケティングを実践している、あるいは実践したいと考える企業の担当者は、壁に直面する都度、そのときどきの該当ページを開かずにはいられなくなるはずだ。
もしかすると、「教科書」という「必読」レベルを超えて、「参考書」という呼び名がよりふさわしいのかもしれない。おそらく本書は、長年にわたりマーケター諸氏の手もとに置かれるだろう。まるで羅針盤のように、次の進路を確認するために何度も読み返される。そして、物質としての本は、経年とともに折れ曲がり変色してしまうばかりか、持ち主の書き込みであふれるだろう。それが、マーケターが手放せなくなる「参考書」たるゆえんだ。
「質のよいコンテンツ」がゴールではない
だが、多くの参考書がそうであるように、本書もまた、読むだけで試験での成功を収められるという類のものではない。プロセスどおりに筆が運ばれているので整理立てて読み進めることはできるが、すなわちそれは、あくまでも戦うための手法、いわゆる「型」を教えてくれる指南書に過ぎない。
第一、世の中には企業がごまんとあり、それぞれ置かれている立場や課題、目的がすべて異なる。それぞれの業界や目的別に向けた、より具体的な手引き書もあり得るのかもしれないが、それでもやはり「絶対」はない。そんなもの、「仕事」としてつまらないではないか。
本書の(そしてコンテンツマーケティングそのものの)醍醐味は、個々の企業が持つ資産を、いかに成功に向けて組み立てていくかという点に尽きるのではないかと思う。そして、アプローチの方法は、成功の指標となる目的を見失いさえしなければ、担当者によって千差万別となるはずだ。
この仕事の醍醐味を心の底から実感するためには、まず基本となる「型」を身につける必要がある。それらをマスターしたうえでスタートラインに立ち、一からコンテンツマーケティングを実践できたなら、数ある選択肢の中から戦略的に最適なアプローチを取り、成功に近づくことができるだろう。
だが、それだけでは「成功」には至らない。オウンドメディアが、従来の一般的な広告とは異なり、コンテンツが資産として蓄積されていく点にメリットが見出される長期的な手法であるからだ。長きにわたって運用し、コンテンツを重ねていくことによってオーディエンスの態度変容を促す。コンテンツマーケティングがこれまでのマーケティング手法と異なる大きな利点は、ここにある。
だからこそ、当初から長期的かつ戦略的なアプローチを積み上げていく必要があるし、どんなに優秀なプランだったとしても多くの場合、途中で見直しを求められる。実践の結果、見えてきた評価・分析結果から課題を抽出し、次なるアクションにつなげる、いわゆるPDCAサイクルの登場だ。トライアンドエラーを重ね、よりよい方法へとアジャストしていくこと。その方法論を持ち合わせて初めて、マーケターは成功を引き寄せることができる。
著者は、「質のよいコンテンツをつくることだけでは不十分」という。
本書が優れているのは、コンテンツマーケティングという手法の話だけでなく、具体的なマネジメントの部分にまで詳しく言及されているところではないかと思う。第2部では、コンテンツマーケティングのプロセスとして「制作・管理」「最適化・統合・キュレーション」「対話・傾聴」「評価・学習」といった4つの要素に分類されているが、コンテンツづくりの後についても(プロセスを実行するうえでの体制づくりやツールの選び方、効果測定の仕方など)具体的に書かれている。ふつうなおざりにされがちな細かい点であり、また国内ではあまり例がないだけに、未経験の「型」を習得していくのにとても役立つであろう。
マーケターとしての「語り方」を学ぶ
ところで、本書ではたくさんのページで「体制」や「役割」について言及されている。制作会社に所属し、コンテンツディレクターとして産声を上げたばかりの私としては、コンテンツマーケティングにおけるクライアントとの体制づくりの必要性については非常に痛感している。コンテンツマーケティングは「長期戦」であり、社内・社外にかかわらず所属を超えた連帯がなければ破綻を来してしまうからだ。主に、コンテンツマーケティングを行う企業の目線から本書は描かれているが、体制づくりにおいては「相性や性格を重視すべき」と書かれていることに、非常に納得する思いがした。
また、体制を整えることによって、これまで課題だった企業内における連携や風通しのよさを実現することもできる。とくに第12章においては、マーケティングの先にあるものとして「企業内の協働」が挙げられていて、個人的な経験として既視感を覚えるとともに、驚きを禁じ得なかった。今後、コンテンツマーケティングが普及・進化していくのに伴い、より鮮明に副次的な効果がもたらされることが報告されるのではないかと思う。個人的には、この点にも可能性を感じているので、注目していきたい。
最後に、コンテンツディレクターとしては、コンテンツのつくり方に言及しないわけにはいかない。少しだけ、手もとの「参考書」の書き込みから拾ってみたい。
本書では、企業がもつ資産を使って、「説得力ある物語を伝えるべき人に伝えること」が繰り返し述べられていた。「人を引きつける経験を生み出し」、「感情を起こさせることに注力する」……。要は、物語なのだ。
それはペルソナづくりにも当てはめることができると思う。実は一冊を通じてもっとも勉強になったところは、ペルソナのつくり方だった。とくに、これでもか、と仔細に描かれるペルソナは、まるで小説の登場人物であるかのように感じた。でも、冗談ではなく、本当にそこまでやらなくてはいけないのだろう。――私たちは「語り手なのだから」。
おそらく、こうした書き込みは、読むたびに形を変えていくだろう。そして、その都度、血となり骨となっていくのだろう。あるいは、いつもつまずくウィークポイントが見つかるかもしれない。これらを整理しなおすことで、ワンランク上のコンテンツマーケティングの使い手として成長を実感できるはずだ。
「型」を習得するために、私はまた、繰り返し本書のページをめくっていく。